「え?またこの戦法…うざい!」
将棋を指していて、そんな気持ちになったことはありませんか?
初心者や中級者が対局中に感じる「うざい戦法」には共通点があります。
読みにくく、対応しづらく、そして心を乱される。
本記事では、ネットやSNS、将棋ウォーズなどで話題の「うざい」と感じやすい戦法を徹底的に分析。
さらに、それらに対する対策や考え方、上達するためのマインドセットまで解説します。
「うざい」と感じた戦法は、実は成長のチャンスかもしれません。
対策を知って、冷静に勝てる力を身につけましょう。
将棋の戦法一覧|初心者向けから最強戦法・奇襲型まで完全解説!


◆アプリダウンロード数4,000万突破!


将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、
【 ABEMA
プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。
>> 将棋見るならABEMA
初心者が「うざい」と感じやすい将棋戦法ベスト5
将棋の実戦やオンライン対局で初心者が「これはうざい!」と感じやすい戦法は、必ずしもプロ棋戦でよく登場するものとは限りません。
それどころか、一部の変則戦法や奇襲戦法は、初心者や慣れていない人にとって強烈なストレスとなることがあります。
ここでは、将棋ウォーズ・将棋クエスト・将棋倶楽部24などの実戦データやSNSの声を元に、初心者が特に苦手と感じる「うざい戦法」ベスト5を紹介し、それぞれの特徴と攻略ポイントを解説していきます。
第1位|鬼殺し戦法(おにごろし)
- 特徴:序盤から桂馬で飛び出して角交換を狙う奇襲型戦法。玉の守りを犠牲にしてでも一気に攻めに出る。
- なぜうざい?:通常の定跡から大きく外れた手順で仕掛けてくるため、対策を知らないと数手で負けることも。
- 対策のポイント:角道を止め、しっかり囲ってから攻めに転じる。急いで受けに回らず、冷静に中央を固めるのがコツ。
鬼殺しは将棋を始めたばかりの人が「最初に出会う“壁”」とも言えます。
数手で一方的に崩されると、「自分の努力が全部無駄になった」と感じてしまうのも納得です。
第2位|筋違い角戦法(すじちがいかく)
- 特徴:角をわざと本来の筋から外して指すことで、相手の予測を乱しながら中盤以降で勝負する。
- なぜうざい?:序盤での違和感が大きく、なぜその手が強いのか理解しにくいため不気味。角がどこからでも狙ってくる。
- 対策のポイント:序盤で角交換を避けて無理に攻め込まない。玉の囲いを優先して安定を目指すことが重要。
相手の角が自分の玉側にいる不安は、初心者にとって非常にプレッシャーになります。
しかも一見すると悪手に見えるため、対応を間違えやすい点も「うざい」と感じる理由の一つです。
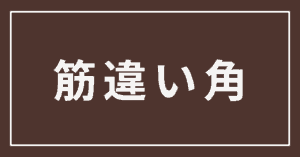
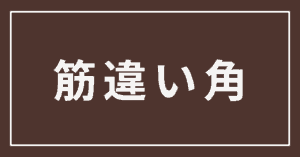
第3位|原始棒銀(げんしぼうぎん)
- 特徴:飛車先の歩を突き、銀を一直線に押し出すだけのシンプルな攻撃型戦法。
- なぜうざい?:あまりに単純すぎるゆえに、それでも負けると「なんでこんな戦法に…」と納得できない。
- 対策のポイント:歩を突き合わず、飛車先を固めることで簡単に防げる。無理に戦わず、カウンター狙いも有効。
原始棒銀は「戦法の暴力」とも言えるほど一直線。
にもかかわらず、初心者相手にはとにかく強く、「勝てばスッキリ、負ければイライラ」の典型的うざ戦法です。
第4位|中飛車左穴熊(なかびしゃひだりあなぐま)
- 特徴:中飛車で主導権を取りつつ、玉を左側の穴熊に囲って鉄壁の布陣を作る。
- なぜうざい?:中央で攻めてきて、玉は反対側。反撃しても全然届かない。
- 対策のポイント:飛車先の歩を突いてカウンターを狙うか、玉を自陣中央〜左に寄せて受けやすくしておく。
中飛車左穴熊は中盤までにペースを握られやすく、慣れていないと一方的展開になりがち。
「一人で将棋してるみたい」と言われるのも納得の構成です。
第5位|右四間飛車(みぎしけんびしゃ)
- 特徴:右側(玉側)に飛車を回して四間飛車に構える奇抜な変則振り飛車。
- なぜうざい?:見慣れない配置に混乱し、対応を間違えるとあっという間に潰される。
- 対策のポイント:飛車を意識しつつ、自陣の囲いとバランスよく守りを固める。慌てず全体を見渡すことが重要。
右四間飛車は通常と逆の配置で違和感が強く、実力者が使うと極めて厄介。
初心者にはとっては「何をされているのか分からないうちに負けた」と感じる典型例です。
「うざい戦法」に共通する特徴とは?
将棋初心者や中級者が「うざい!」と感じる戦法には、いくつかの共通した特徴があります。
単純に“強い”とか“勝てない”という理由だけではなく、「気づいたら負けていた」「自分のペースを乱された」という心理的な負担や動揺が背景にあることが多いのです。
以下では、特に多くの戦法に共通する「うざさの構造」をひも解きながら、なぜそう感じるのか、そしてどう対処すべきかを解説していきます。
定跡外から攻める「奇襲型」が多い
うざい戦法の多くは、相手の準備や知識を逆手に取る「奇襲型」です。
- 初心者が覚えたばかりの定跡や囲いを使う暇もなく攻められる
- 型破りな一手で、序盤から頭が真っ白になる
- いきなり角交換や飛車先突破など、想定外の展開に焦る
例)鬼殺し戦法、筋違い角、トマホーク など
こうした奇襲型は、自分が思い描いた将棋の“設計図”を壊されることにストレスを感じます。
その結果、「うざい」「嫌い」となるのです。
対応を知らないと一方的に攻められる
多くのうざい戦法は、対策を知らないと対応不能に陥ります。
たとえば筋違い角。
慣れている人には怖くない戦法でも、対策を知らない初心者は「角がどこにでも飛んでくる感じがする…」と混乱します。
棒銀にしても、たった数手で銀が飛車前まで迫ってくる怖さに耐えられず、防御が崩壊することもしばしば。
ポイントは以下の通り、
- 「定跡ではこうしろ」と習った対応が通用しない
- 一手でも間違えると一方的に攻め込まれる
- 知らない戦法ほど、精神的プレッシャーが倍増
受けが甘いと一気に崩れるプレッシャー戦法
うざい戦法は、受け間違えただけで致命的な差がつくものが多いです。
たとえば中飛車左穴熊や風車戦法などは、こちらが囲いを整える前に一方的に攻め込まれます。
これにより、
- 慣れないうちは序盤から手詰まりになる
- 受けミス=一瞬でゲームオーバー
- 「もっとゆっくり進めたいのに…」という焦燥感
という、精神的な焦りが生まれます。
これが“うざさ”の正体でもあります。
戦法そのものより“心理的ストレス”がうざさの原因
結局のところ、「うざい」と感じる本質は自分のミスや知識不足に対する無意識のストレスです。
「負けたくない」「理解できない」「ペースを乱された」など、心理的な不快感が“戦法”に転嫁されるのです。
つまり、
- 「相手のせい」にしたくなる気持ち
- 自分が主導権を握れないイライラ
- 「またこの戦法かよ」というトラウマの蓄積
こうした感情が、戦法そのものを「うざい」と思わせる大きな要因です。
自分で使うとうざい戦法は有利になる?
「うざい」と感じる戦法。
実はそれらを自分で使うと、思った以上に勝てることがあります。
これは、相手が対応を知らない、またはペースを乱されることにより、心理的な優位に立てるからです。
このセクションでは、「うざい戦法」を使うメリットと注意点、そしてどうやって勝ちにつなげるかを具体的に見ていきましょう。
奇襲戦法は“準備不要で主導権が取れる”
鬼殺し、筋違い角、原始棒銀などは、「覚えることが少なく、少ない手順で攻められる」点が魅力です。
| 戦法名 | 主な攻め筋 | 攻め出しまでの手数 | 必要な定跡知識 |
| 鬼殺し | 角交換からの桂馬、飛車突撃 | 5〜7手程度 | 最低限でOK |
| 原始棒銀 | 飛車先突破+銀突き | 6〜8手程度 | 最低限でOK |
| 筋違い角 | 角の変則配置から中盤へ | 7〜9手程度 | 少し必要 |
こうした戦法は、定跡よりも奇襲力で勝負する構成になっており、相手が戸惑えばそのまま押し切れます。
特に将棋ウォーズや将棋クエストなどの短時間対局では非常に有利です。
心理的に揺さぶりをかけられる
うざい戦法は、「相手の考える時間を奪う」力を持っています。
角道を止めない、玉を囲わないなどの“普通じゃない動き”に、相手は構え直しを迫られます。
- 「え、なんでここでこの手?」
- 「ちょっと待って、これどう受ければ…」
- 「囲うべき?攻めるべき?」
このような“迷い”を与えることが最大の武器になります。
短時間で判断を迫られた相手は、ついミスをしてしまいます。
使う側にもリスクあり!その戦法、ちゃんと理解してる?
ただし、うざい戦法はリスキーでもあります。
- 定跡外れが多いため、対応されると即崩壊する
- 守りが弱く、玉がスカスカになりやすい
- 一手のミスが致命的になる
特に鬼殺しは、角交換後の桂馬・飛車・玉の位置関係が絶妙で、少しでも間違えると逆に「即詰み」にされる危険性があります。
自分で使うなら、“なぜこの形になるのか”を理解してから使うことが大前提です。
対策を知られてしまうと通用しない
ネット将棋で同じ戦法ばかり使っていると、対戦履歴を見た相手にバレることもあります。
また、将棋ウォーズでは一定ランクになると「鬼殺しはこう受ける」と理解した相手が増えてきます。
うざい戦法が通用するのは、“相手が知らないうち”だけ。
通用しなくなったと感じたら、定跡型の居飛車・振り飛車などにシフトする柔軟さが必要です。
おすすめは“ハイブリッド戦法”
最も効果的なのは、「うざい要素を少しだけ取り入れた定跡ベースの構え」です。
例)
- 原始棒銀 → 銀は出すが、玉はしっかり囲う
- 筋違い角 → 序盤だけ奇抜、途中からオーソドックスに
- トマホーク → 攻めは左、でも囲いは美濃囲い
こうすることで、
- 奇襲力と安定感の両立
- 対策されにくく長持ちする
- 相手の動揺を誘いながら、自分は崩れない
という、理想的な展開を作り出せます。
SNSやネットで話題の“うざい戦法”一覧
SNSや将棋系のYouTubeチャンネル、掲示板などでは、プロの定跡とは違った“うざさ全開”の戦法がたびたび話題になります。
これらの戦法は奇抜でインパクトがあり、勝ち筋が明確な分、初心者から中級者にとっては非常にやっかいな存在です。
このセクションでは、特にネットで注目を集めた“うざい戦法”を紹介し、その特徴や対策も合わせて解説します。
風車戦法(ふうしゃせんぽう)
- 特徴:飛車を右に回し、その後金銀で囲いながらゆっくり攻める独特な振り飛車。
- SNSでの評判:「見た目が意味不明」「囲いに見えないのに固い」「風車回ってるw」など、ネタ感も強い。
- うざさポイント:構えが独特で、どこから攻めればいいか分かりづらい。意外と堅い。
- 対策:飛車の位置を意識し、序盤から速攻を仕掛けるのが有効。
ごりごり金
- 特徴:中盤で金をどんどん前に出していくゴリ押し型の攻撃戦法。
- SNSでの評判:「金の暴力」「こんなんアリ?」「見た目がウケる」など。
- うざさポイント:理屈無視のパワープレイ。固い守りを金で強引に崩してくる。
- 対策:金が前に出てきた瞬間を狙ってカウンター。守りが薄くなるため反撃しやすい。
トマホーク戦法
- 特徴:角を斜めに構え、飛車と銀を連携させて“トマホーク”のように斜めから突き刺す攻撃。
- SNSでの評判:「名前がかっこよすぎ」「見た目が派手」「刺さると一瞬」など人気高。
- うざさポイント:対応を間違えると銀が飛び込んできて崩壊。斜めからの攻撃が読みづらい。
- 対策:銀の進路を事前に遮るような駒組みを意識する。
カニ銀(かにかにぎん)
- 特徴:銀がカニのように横歩きしていく異色の戦法。居飛車寄りの構えで意表を突く。
- SNSでの評判:「見てる分には面白い」「指されるとマジで腹立つ」「銀がカニ歩きw」など。
- うざさポイント:定跡から外れてるのに、妙に堅く、攻めが的確。特に対振り飛車に強い。
- 対策:銀が動き出す前に早めに主導権を握る。穴熊などで受け切って反撃するのが有効。
ダイレクト向かい飛車
- 特徴:囲いを作る前にいきなり飛車を4筋に移動する速攻型向かい飛車。
- SNSでの評判:「マジで攻撃しか考えてない」「囲わないのに強いのズルい」「これに勝てん」など。
- うざさポイント:囲わず、開戦が早い。相手の囲いを待たずに一方的に攻める。
- 対策:守りを優先し、受けきってから反撃。相手の玉は薄いので冷静に攻め返すことが大事。
話題性ランキング(SNS評価)
| 戦法名 | SNSうざさ評価 | 難易度 | 対策難易度 |
| 風車 | ★★★★☆ | 中級 | 高め |
| ごりごり金 | ★★★★☆ | 初級 | 低め |
| トマホーク | ★★★★★ | 中級 | 中 |
| カニカニ銀 | ★★★★☆ | 中級 | 高め |
| ダイレクト向かい飛車 | ★★★★★ | 初級〜中級 | 中 |
うざい戦法に振り回されないための3つの心得
うざい戦法に出会うと、頭が真っ白になったり、「どうせまたこの戦法か…」と気分が下がってしまうこともあります。
ですが、正しい心構えと準備があれば、どんなうざい戦法でも怖くありません。
ここでは、「うざい戦法に振り回されないための3つの心得」を紹介します。
将棋の上達にもつながる考え方なので、ぜひ取り入れてください。
① うざさの正体は“知らなさ”と“焦り”
まず大前提として、うざさを感じる最大の原因は「知らないこと」と「思い通りにいかないこと」です。
- 相手の手が見えない
- 予想していた展開と違う
- 自分の戦法が崩された
これらは、知識と経験でカバーできるものです。
感情的にならず、まずは「なぜこの戦法がうざいのか」を冷静に見つめ直すことが第一歩です。
◆アドバイス
定跡サイトや将棋YouTubeなどで、代表的なうざい戦法の対策を一つずつ学ぶだけでも、不安感がぐっと減ります。
② 囲いとバランスで“盤面を安定化”させる
うざい戦法は、序盤から揺さぶりをかけてきます。
だからこそ、自分の陣形を安定させる囲いを作っておくと、かなり安心感が違います。
| 代表的な囲い | 特徴 | 対うざい戦法効果 |
| 美濃囲い | 振り飛車向き、早囲いが可能 | ★★★★☆ |
| 舟囲い | 初心者でも作りやすい、柔軟な形 | ★★★☆☆ |
| 銀冠 | 攻守バランスよし、中盤も強い | ★★★★★ |
| 居飛車穴熊 | 完成すれば最強だが時間がかかる | ★★★☆☆ |
基本の囲いをしっかり作るだけで、「対応を間違えてすぐ崩れる」リスクが激減します。
③ “自分から攻める”意識を持つ
うざい戦法に対して受け身になると、どんどん主導権を握られて負けてしまいます。
「うざいからこそ、こちらから動いて主導権を取る」という意識が大切です。
- 無理に攻めず、相手のミスを待つ
- 囲いを整えたらカウンターを狙う
- 対応に慣れた戦法なら、序盤から積極的に交換
◆コツ
たとえば原始棒銀に対しては、飛車先を逆に突いて戦場を変える、など相手のペースを崩す動きを意識すると、主導権を握り返せます。
補足:将棋は“負けて学ぶ”ゲーム
将棋で一番成長できる瞬間は、負けたときに「なぜ負けたか」を考えたときです。
うざい戦法に負けたら、その戦法を調べ、次は勝つために一つ学ぶ。
それを繰り返せば、自然とうざい戦法は怖くなくなります。
まとめ|うざい戦法とうまく付き合おう
将棋における「うざい戦法」は、一見すると理不尽だったり、邪道に見えたりするかもしれません。
しかし、そうした戦法にもれっきとした戦略や勝ち筋があり、多くのプレイヤーが実際に使って成果を出しているのも事実です。
今回の記事を振り返ると、うざい戦法には以下のような特徴がありました。
本記事の要点まとめ
| ポイント | 内容 |
| よくあるうざい戦法 | 鬼殺し、筋違い角、原始棒銀、風車、ごりごり金など |
| SNSで話題のうざい系 | トマホーク、カニカニ銀、ダイレクト向かい飛車など |
| うざい理由 | 意表を突く・囲わない・攻撃が早い・定跡外など |
| 対策ポイント | 心構え・囲いで安定・主導権を奪い返す |
| 自分でも使える? | 使えるが、リスクもある。習熟が必要 |
| 成長への近道 | 「負け→学び→対策」のループを繰り返すことで苦手を克服できる |
「うざさ」は、将棋上達のチャンス
うざい戦法にイライラしたときこそ、成長のチャンスです。
その戦法を調べて、実際に自分でも指してみることで、対策が自然と身につきます。
「うざい=嫌なもの」ではなく、
「うざい=強くなるための通過点」と考えて、前向きに取り組んでみてください。
あなたのペースで将棋を楽しもう
将棋は、自分のスタイルを見つけるまでが少し難しいゲームです。
でも、今回紹介したような戦法の特徴や心理戦を知ることで、より深く、もっと楽しく将棋が指せるようになります。
あなたの成長に、この記事が少しでも役立てば幸いです。
将棋の三間飛車とはどんな戦法?石田流との違い・組み方・対策まで徹底解説
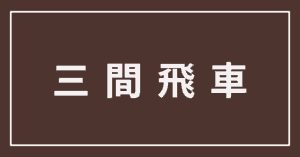
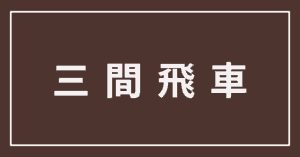


将棋初心者におすすめの戦法5選|やさしく覚えて勝ちやすくなる基本戦術
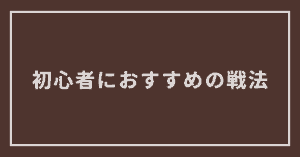
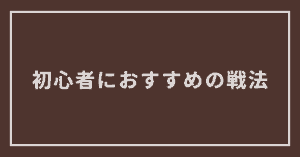
将棋の戦法一覧|初心者向けから最強戦法・奇襲型まで完全解説!

