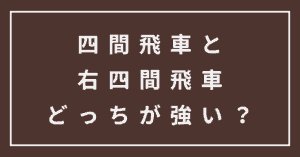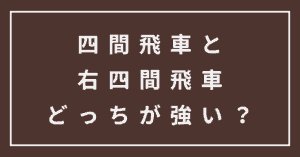四間飛車を本格的に学びたいけど、どの本から手をつければ良いのかわからない…そんな悩みを持つ将棋ファンに絶大な支持を得ているのが、藤井猛九段の著書『四間飛車を指しこなす本』シリーズです。
将棋界では“ミシュラン三ツ星級”の定跡書とも呼ばれるこのシリーズ。しかし一方で「難しい」「古い」と感じる声もあり、初心者には敷居が高いと感じられるかもしれません。さらに、同じ著者による『四間飛車の急所』との違いに迷う方も多いでしょう。
この記事では、『四間飛車を指しこなす本』の全体像から各巻のレビュー、使い方や効果的な学習法、そして電子書籍版の情報まで、あらゆる角度からわかりやすく解説します。これから四間飛車を学ぶあなたにとって、最適な一冊を選ぶための参考になれば幸いです。
将棋の戦法一覧|初心者向けから最強戦法・奇襲型まで完全解説!


『四間飛車を指しこなす本』とは?藤井猛九段の名著
『四間飛車を指しこなす本』は、四間飛車戦法を代表するプロ棋士・藤井猛九段が執筆した定跡書シリーズです。初心者〜中級者まで幅広い層に向けて書かれており、四間飛車の基本から応用までを体系的に学べます。
全3巻の構成と出版年|古いけど今でも使える?
『四間飛車を指しこなす本』シリーズは、以下のように4巻で構成されています。
| 内容 | 出版年 | |
| 第1巻 | 四間飛車の基本(対居飛車穴熊) | 2000年 |
| 第2巻 | 急戦対策(棒銀・左美濃急戦) | 2000年 |
| 第3巻 | 振り飛車側からの攻め筋の掘り下げ | 2000年 |
著者・藤井猛九段の功績と四間飛車への影響
出版年を見ると「古いのでは?」と感じるかもしれませんが、定跡の骨格は今でも有効です。特に藤井システムの基本思想は、現代の四間飛車にも応用可能です。
藤井猛九段は、1990年代〜2000年代にかけて振り飛車党の中心的存在として名を馳せた棋士です。彼が考案した「藤井システム」は、四間飛車で居飛車穴熊を打ち破る革命的な戦法として話題を呼びました。
『四間飛車の急所』との違いは?
彼の書籍は、「戦法の背景にある思想」まで解説されている点が特徴です。単なる手順解説にとどまらず、「なぜその一手を指すのか」という深い理解が得られます。
同じく藤井猛九段が執筆した『四間飛車の急所』との違いもよく聞かれるポイントです。
| 書名 | 対象者 | 内容の特徴 |
| 四間飛車を指しこなす本 | 初〜中級者 | 四間飛車の基礎から丁寧に解説 |
| 四間飛車の急所 | 中〜上級者 | 最新の形や鋭い変化を多く収録 |
『急所』の方がより実戦向きで細かい変化に踏み込んでおり、『指しこなす本』を読んでから手に取ると理解が深まります。
レビュー・評価|「難しい」「ミシュラン級」は本当?
『四間飛車を指しこなす本』は、将棋ファンの間で長く愛されている名著ですが、「難しい」と感じる読者も少なくありません。一方で、その内容の濃さから“将棋書籍界のミシュラン”と称されるほどの高評価も受けています。
読者レビューまとめ|「難しいけど勉強になる」の声多数
以下は実際の読者レビューの要約です。
| 評価 | 内容 |
| ★★★★★ | 「考え方まで丁寧に書かれていて、何度も読み返している」 |
| ★★★★☆ | 「難しいが、じっくり読み込めば力になる。図が多いのが◎」 |
| ★★★☆☆ | 「初心者にはちょっとハード。将棋用語の理解が必要」 |
特に第1巻は、居飛車穴熊対策としての四間飛車の考え方が徹底的に解説されており、しっかり理解すれば大きな力になります。
「四間飛車のバイブル」と呼ばれる理由
本書が「バイブル」と言われる理由は、単なる定跡の解説書ではなく、“四間飛車をどう使いこなすか”を教えてくれることにあります。
- 守勢に回ったときの考え方
- 組み上げるまでの細かいポイント
- 玉の位置・飛車のさばき方
など、局面ごとの「考え方」や「判断基準」を明示してくれているのが特徴です。
また、藤井九段独特の語り口も魅力で、専門的な内容ながら親しみやすく読める工夫も施されています。
難易度は高め?初心者でも読めるかを検証
正直に言うと、初心者がいきなり読むには少し難しい内容です。
- 将棋用語の理解
- 基本的な定跡パターンの把握
- 手筋の知識
これらがある程度ないと、読み進めるのに時間がかかる可能性があります。ただし、繰り返し読むことで内容が腑に落ち、四間飛車の本質的な考え方が身につくという評価が多いのも事実です。
「一度読んでわからなければ、二度、三度と読めばいい。そう思わせてくれる価値がある本」
という声もあり、じっくり読み込む意欲のある方には間違いなくおすすめできる一冊です。
使い方・活用法|どのように読めば上達できるか?
『四間飛車を指しこなす本』は、単に読み流すだけではなく、実際に将棋盤やアプリで並べながら学ぶことで、理解度が格段に深まります。ここでは効果的な使い方や活用法をご紹介します。
実際に並べて覚える|盤面での再現が理解を助ける
本書は変化図や局面図が豊富に掲載されているため、実際の将棋盤や将棋アプリで手順を再現しながら読むのがベストです。
おすすめの手順は以下の通りです:
- 読む前に軽く全体を流し読みしてテーマを把握する
- 図面ごとに一手ずつ並べていく
- なぜこの手が良いのか、書かれている解説を考えながら指す
- 途中の分岐点で自分でも考えてみる
- 一通り終わったら、棋譜を通しで並べてみる
このように実戦を意識しながら読むことで、頭ではなく体で覚える感覚が身につき、次第に自分の将棋に落とし込むことができるようになります。
巻数ごとの活用法|1〜3巻の読み分け方
『四間飛車を指しこなす本』シリーズは、各巻に明確なテーマがあるため、自分の棋力や苦手分野に合わせて読み進めるのがおすすめです。
| 巻 | 主なテーマ | 対象レベル |
| 1巻 | 基本の考え方と居飛車対策 | 初級〜中級 |
| 2巻 | 左美濃、急戦型への対応 | 中級 |
| 3巻 | 居飛車穴熊への戦い方 | 中級〜上級 |
特に3巻の「四間飛車の急所」に関する解説は評価が高く、居飛車穴熊に対して四間飛車側がどう戦えばいいのか明確にわかります。
また、読んだ直後に実戦や将棋ウォーズなどで試すことで、理解の定着が早まり、実力アップにも直結します。
電子書籍版の活用|スマホでも学べる便利さ
現在、『四間飛車を指しこなす本』シリーズは電子書籍版も販売されており、スマホやタブレットで手軽に読めるのも大きな魅力です。
- 移動時間やスキマ時間にさっと読める
- アプリの盤面と並行して使いやすい
- ページのスクショやメモも取りやすい
特に「Kindle」や「楽天Kobo」などのサービスで配信されており、購入後すぐに読める点も便利です。
初心者から中級者の方で、紙の本を持ち歩かずに勉強したい方には電子書籍版もおすすめです。
まとめ|『四間飛車を指しこなす本』は四間飛車党の必携書
『四間飛車を指しこなす本』シリーズは、四間飛車を指すすべての将棋ファンにとって、まさに“ミシュラン三ツ星級”の戦法指南書といえる内容です。シリーズ全体を通して「なぜこの手なのか?」という思考の裏側まで丁寧に解説されており、実戦での判断力や構想力の養成に役立ちます。
定跡理解+応用力が身につく構成
単なる手順の暗記にとどまらず、「この形はこういう理由で強い」といった思考の根拠まで学べる構成になっているのが、本シリーズ最大の魅力です。序盤だけでなく中盤〜終盤に至るまでの方針がわかることで、四間飛車の指し回しに自信がつきます。
たとえば、「四間飛車の急所」をピンポイントで突く解説や、「居飛車穴熊への対策」に特化した章立てなど、ライバルとの差を生む“現代的な四間飛車”の感覚を自然と吸収できます。
こんな人におすすめ!
以下のような方に特におすすめです。
- 四間飛車を本格的に指していきたい初級〜上級者
- 定跡書を読んでも「なぜこの手?」と悩みがちな人
- 実戦で勝てる力をつけたい将棋ウォーズ中毒者
- 古く感じない現代的な振り飛車を学びたい人
- 盤面を見て直感的に指せる力を身につけたい人
特に「四間飛車=古い」というイメージを持っている方にこそ、本シリーズの現代感覚と洗練された戦術を知ってもらいたいところです。
レビュー評価も高く、今も読み継がれている
発売から年月が経っても、将棋ファンの間での評価は高く、Amazonや楽天ブックスでも星4.5以上のレビューが並ぶロングセラーです。
読者レビューの一例:
「将棋初心者でしたが、手順だけでなく“なぜこの手なのか”まで分かるので理解が深まりました。」
「中盤の考え方が分かるようになって、指すのが楽しくなった。」
現在でも十分通用する内容で、「古い」という印象を覆す内容が詰まっています。四間飛車を本格的に学びたい方は、間違いなく手元に置くべき一冊といえるでしょう。
将棋の四間飛車と右四間飛車はどっちが強い?違いと特徴を徹底比較