将棋の戦法の中でも根強い人気を誇る「四間飛車」は、守りと攻めのバランスが絶妙で、多くのプロ棋士やアマチュアに愛されています。
特に初心者でも取り入れやすい点が魅力で、駒組みのパターンや狙いを理解すれば、実戦でしっかりと勝ちを目指せる戦法です。
本記事では、四間飛車の基本から応用、対策方法、定跡やおすすめの棋書まで、幅広く丁寧に解説します。
あなたの将棋力向上に役立つよう、実践的な内容をたっぷり詰め込みました。
四間飛車を極めたい方も、対策したい方も、ぜひ参考にしてください。
将棋の四間飛車と右四間飛車はどっちが強い?違いと特徴を徹底比較
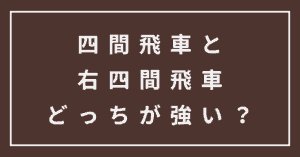
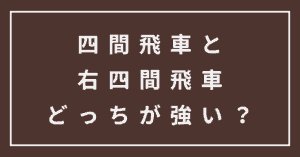
◆アプリダウンロード数4,000万突破!


将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、
【 ABEMA
プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。
>> 将棋見るならABEMA
四間飛車とは?将棋初心者でも扱いやすい戦法
四間飛車は将棋における代表的な「振り飛車」のひとつで、初心者でも比較的扱いやすい戦法として知られています。
ここでは、四間飛車の概要、構造、そして初心者に向いている理由を詳しく解説していきます。
四間飛車の基本構造と意味
四間飛車とは、自分の飛車を自陣の4筋(後手の場合は6筋)に振って戦う戦法です。
序盤から駒組みがしやすく、守備と反撃のバランスが取れているのが特徴です。
◆基本的な配置比較表
| 駒の名称 | 通常の初期配置 | 四間飛車での位置 |
| 飛車 | 2八(後手8二) | 6八(後手4二) |
| 玉 | 5八(後手5二) | 右側へ移動し囲う |
| 角 | 8八(後手2二) | 主にそのまま |
| 金銀 | 玉周辺に集める | 美濃囲いなどへ |
初心者が四間飛車を選ぶ理由
将棋を始めたばかりの人が四間飛車を選ぶのには、以下のような明確なメリットがあります。
◆初心者に優しいポイント
- 駒組みがパターン化されており、覚えやすい
- 美濃囲いなど、囲いの基本も一緒に学べる
- 自分のミスによる即敗北のリスクが少ない
- 振り飛車の中でも安定性が高く、攻守のバランスが良い
初心者が「どの戦法から学ぶか」と迷ったとき、最初に取り組む選択肢として四間飛車は非常に優れています。
四間飛車の攻守のバランスと奇襲性
守備的な印象のある四間飛車ですが、状況によっては意外性のある急戦にも持ち込めます。
特に角や銀の動きを活用した反撃が決まると、大きなダメージを相手に与えられます。
◆代表的な反撃例
- ▲6六歩から角道を開ける鋭いカウンター
- △4四歩を突かせて飛車で揺さぶる
- 美濃囲いの耐久力を活かした持久戦からの急襲
このように、守備だけでなく攻撃のチャンスも作りやすいのが四間飛車の大きな魅力です。
四間飛車の基本的な駒組みと将棋の指し方
四間飛車は、特定のパターンに沿って駒を組むことで守備と攻撃の両方を安定させる戦法です。
ここでは、駒組みの基本形と指し方のポイントをわかりやすく紹介します。
四間飛車の標準的な駒組み手順
四間飛車の駒組みにはいくつかの定番パターンがありますが、もっとも代表的なのが「美濃囲い」を使った形です。
以下に、一般的な四間飛車(後手番)の駒組み手順を簡潔に示します。
◆基本の駒組み手順(後手番)例
| 手数 | 指し手 | 説明 |
| 1 | △3四歩 | 角道を開ける |
| 2 | △4四歩 | 飛車を振る準備 |
| 3 | △4二飛 | 四間飛車の形が完成 |
| 4 | △3三角 | 角交換に備える |
| 5 | △6二玉 | 玉を囲い始める |
| 6 | △7二銀 | 美濃囲いの銀配置 |
| 7 | △5二金左 | 美濃囲いの基本完成 |
このように、飛車・玉・銀・金をバランスよく配置することで「守りながら攻める」構造を構築できます。
美濃囲いの基本形と派生形
美濃囲いは、四間飛車とセットで覚えるべき囲いです。
玉を右に寄せ、金銀をうまく配置することで非常に堅固な守りを実現します。
◆基本形:美濃囲いの配置図(後手番視点)
- 玉:8二
- 金:6一・5二
- 銀:6二
- 飛車:4二
この配置によって、相手の攻撃を受け止めながら、飛車と角のカウンターで反撃が可能です。
◆派生型:高美濃囲い・銀冠など
| 囲い名 | 特徴 |
| 高美濃囲い | 金を前に出し、上部の耐久性を強化 |
| 銀冠 | さらに銀を上げて、端攻め・上部からの攻撃に強くする |
四間飛車の指し方のコツと注意点
指し方にはいくつかの「型」がありますが、基本的には以下のような意識が大切です。
◆指し方のコツ
- 自陣のバランスを崩さずに駒組みを進める
- 相手の角交換や早仕掛けを警戒する
- 美濃囲いが完成するまでは無理な攻めを避ける
- 角道を空けたときのカウンターを狙う
◆注意点
- 相手の急戦(特に急戦棒銀)に弱い面もある
- 振り飛車らしく持久戦に持ち込むことを意識する
- 玉の移動が遅れると即詰みに繋がる危険性もある
四間飛車における代表的な将棋の囲い方と守り方
四間飛車は守りを重視した戦法のため、囲いの選択が非常に重要です。
ここでは、四間飛車と相性の良い囲いや、それぞれの特徴・守り方について解説します。
四間飛車に合う代表的な囲い一覧
以下に、四間飛車でよく使われる囲いとその特徴をまとめました。
| 囲いの名称 | 特徴 |
| 美濃囲い | 初心者におすすめ。バランスの良い守りで四間飛車と基本セットとなる形。 |
| 高美濃囲い | 金を進めて上部の耐久性をアップ。角交換や上からの攻撃に強い。 |
| 銀冠 | 銀を上に上げた強固な囲い。対抗形や持久戦に有利。 |
| 金無双 | 金を左に2枚、銀を右に構える囲い。見た目は堅牢だが玉の退路が狭い。 |
| 穴熊 | 玉を隅まで囲い最強クラスの防御力。ただし駒組みに時間がかかる。 |
初心者はまず美濃囲いから覚えるべき理由
四間飛車における囲いの基本は「美濃囲い」です。理由は以下の通りです。
- 駒組みが早く、形が整えやすい
- 攻めにも対応しやすく、応用が効く
- 他の囲いへの発展形に繋がりやすい
特に将棋初心者には、美濃囲いを通じて囲いの感覚や守りの意識を養うのに最適です。
対急戦には高美濃囲いや銀冠が効果的
急戦(例えば急戦棒銀など)を仕掛けてくる相手には、美濃囲いだけでは不安な場合があります。
そこで高美濃囲いや銀冠が有効です。
◆高美濃囲いの特徴
- 銀を前に出すことで、相手の角や飛車による攻撃に耐性がつく
- 美濃囲いからの発展型なので移行しやすい
◆銀冠の特徴
- 上部からの攻撃に非常に強い
- 飛車交換後も崩れにくく、持久戦向き
四間飛車穴熊は上級者向け
守備力最強といわれる「穴熊」も四間飛車と組み合わせることができますが、以下の点に注意が必要です。
- 駒組みに多くの手数がかかるため、早仕掛けに弱い
- 囲い完成前に仕掛けられると劣勢になりやすい
- 相手の玉が薄いときに使うと効果的
つまり、相手の動きを読んでから採用する必要があり、中級者〜上級者向けの囲いといえます。
囲いを選ぶときの判断基準
囲いは状況によって使い分ける必要があります。
以下に判断基準をリストアップします。
- 相手が急戦型 → 高美濃囲い or 銀冠
- 持久戦志向 → 銀冠 or 穴熊
- 柔軟性とスピード重視 → 美濃囲い
- 特殊な形や研究勝負 → 金無双
囲いは対戦相手の戦型・序盤の動きによって臨機応変に対応しましょう。
このように、囲い選びは四間飛車の勝率を大きく左右します。
四間飛車に有利な将棋の戦型と相性
四間飛車は柔軟な駒組みと守備力を兼ね備えた戦法で、さまざまな戦型に対応可能です。
このセクションでは、四間飛車と相性の良い戦型と、苦手とされる戦型について詳しく見ていきます。
対居飛車戦での相性と有利な戦型
相手が居飛車を選んだ場合、四間飛車側は持久戦を狙いやすく、以下のような展開が有利です。
- 相手が矢倉や左美濃などの囲いを選択 → 自陣を固めてじっくり戦える
- 端歩を突いてこない → 左銀を自由に使えるので攻め筋が多彩
特に、居飛車穴熊に対しては高美濃→銀冠→端攻めの順で崩しにいくのが定跡です。
| 相手の戦型 | 四間飛車の対策や相性 |
| 矢倉 | 互角〜やや有利 |
| 居飛車穴熊 | 銀冠〜端攻めで対抗 |
| 右四間飛車 | 相手の早仕掛けに要注意 |
対急戦には柔軟な対応力が求められる
急戦に出てくる相手には、序盤から積極的に攻撃してくるため、対応を間違えると不利になります。
- 急戦棒銀:右銀の早仕掛け。▲5七銀型や早めの▲6六歩で受ける
- 早繰り銀:銀冠に組むことで耐久力を高める
- 右四間飛車急戦:玉側からの攻撃。美濃囲いでは薄いため、高美濃へ発展させるのが有効
ポイントは「囲いを早めに固め、反撃の準備を整えておくこと」です。
対振り飛車同士では戦型が複雑化しやすい
相手も振り飛車を採用した場合、同じような戦法になるため、仕掛けのタイミングや細かい駒組みの差で勝敗が分かれます。
- 相振り飛車戦では居玉にせず美濃囲い以上を目指す
- 角の利きの活用が勝負の分かれ目
- 先手番での主導権取りが重要
また、相手の陣形に応じて「角交換型」にするのも一つの有効手です。
四間飛車に不利な戦型とは?
以下のような戦型は、四間飛車側にとってやや不利となる場合があります。
| 戦型・仕掛け | 不利な理由 |
| 超急戦(藤井システムなど) | 美濃囲い完成前に潰される危険 |
| 左美濃急戦 | 角道が止められて中央突破されやすい |
| 超速▲3七銀戦法 | 銀の早い展開で形を乱されやすい |
これらの対策としては、囲いの早期完成と角交換→中央反撃の意識が大切になります。
四間飛車に向いている戦型を選ぶための考え方
自分が四間飛車を使うとき、相手の出方に応じて対応を決めることが重要です。
以下のような指針が役立ちます。
- 相手が居飛車 → 美濃〜銀冠の持久戦で挑む
- 相手が急戦 → 囲いを高くし、序盤を慎重に
- 相振り飛車 → 玉の早囲いと角のライン調整を重視
- 相手が定跡形を外してきた → 自由度の高い駒組みを生かす
四間飛車は受け将棋ですが、「待つ」だけでは勝てません。受けに反撃する力をつけることが、勝率アップのカギとなります。
四間飛車の攻め筋と仕掛けの基本パターン
四間飛車は「受けの戦法」として知られていますが、相手の隙を見てタイミングよく仕掛けることで一気に優勢を築くことも可能です。
このセクションでは、基本的な攻め筋や代表的な仕掛けパターンを紹介していきます。
端攻めと銀冠による圧力
四間飛車の代名詞とも言えるのが「端攻め」です。
特に相手が居飛車穴熊や矢倉囲いを選んだ場合、端からの攻撃が有効です。
- 銀冠に発展させ、左銀を▲7七〜▲8六と繰り出す
- ▲9六歩、▲9五歩からの端歩交換で端をこじ開ける
- 香車を使った▲9八香→▲9六香の攻めも視野に入れる
| 手順例 | 内容 |
| ▲7七銀→▲8六銀 | 左銀を活用した攻め |
| ▲9六歩→▲9五歩 | 端歩を伸ばしてプレッシャーをかける |
| ▲9八香→▲9六香 | 香車でのサポート |
端攻めは玉から遠いため、リスクが少なく攻撃の起点にしやすいです。
角交換からの中央突破
角交換型四間飛車では、中央突破を狙う攻め筋も有効です。
- 初期段階で角交換を行い、相手の陣形を乱す
- ▲5五歩や▲4五歩と突いて中央に駒を集中
- 飛車を振り直して、中央に回すこともある(▲5八飛型)
この攻めは相手の守備陣が整う前に崩す戦法として効果的です。
飛車先交換からのタイミング攻撃
飛車先の歩を交換することで、相手の形に揺さぶりをかけることができます。
- ▲7六歩→▲7五歩→▲7四歩(歩の連打でプレッシャー)
- 飛車を▲7八→▲7五→▲7四と進出
- 歩切れを避けるため、タイミングには注意が必要
特に居飛車の陣形が未完成のうちに仕掛けると成功率が上がります。
左銀・左桂の活用による攻撃
四間飛車では左銀・左桂の活用が重要です。
受けだけでなく、攻めにも使える駒です。
- ▲7七銀〜▲8六銀の進出で端や中央を狙う
- ▲9七桂→▲8五桂で飛び込む攻撃ルート
- 銀桂両方が前線に出ていると、相手の玉を圧迫しやすくなります
銀や桂を前線に出す前に、自玉の囲いが十分かを確認することが大切です。
囲いからの脱却タイミングと仕掛け判断
仕掛けのタイミングで最も重要なのは「囲いが完成しているか」です。
| 状況 | 仕掛け判断 |
| 美濃囲い完成 → 相手が急戦型 | 受け重視、反撃の準備 |
| 高美濃〜銀冠完成 | 積極的に攻めるチャンス |
| 相手の囲いが薄い | 角交換からの急戦も可能 |
| 相振り飛車で囲いが同程度 | 駒得・形のバランスで判断 |
囲いが中途半端なまま仕掛けると、反撃で崩されるリスクが高まります。
このように、四間飛車は「受けるだけ」の戦法ではなく、守りが整った上での反撃や、適切な仕掛けタイミングを読む力が重要です。
定跡を理解し、実戦で繰り返し経験を積むことで、攻めの幅も広がっていくでしょう。
四間飛車の定跡と変化型の理解
四間飛車は長い歴史の中で多くの定跡(決まった進行パターン)が研究されており、相手の戦法に応じてさまざまな変化型が存在します。
このセクションでは、代表的な定跡とそのバリエーション、対抗策を解説します。
基本的な四間飛車の定跡進行
まずは四間飛車の代表的な進行を確認しておきましょう。
以下のような形が基本形になります。
| 手順 | 内容 |
| ▲7六歩 → ▲6六歩 | 角道開ける。四間飛車の布石 |
| ▲6八飛 | 飛車を6筋に振る |
| ▲3八銀 | 銀を引き締める守備 |
| ▲4八玉 → ▲3九玉 → ▲2八玉 | 美濃囲いを作るための玉移動 |
| ▲5八金左 | 美濃囲いの完成 |
このような進行をしながら、相手がどのような戦型を取るかを見極めていくことが重要です。
急戦に対する定跡(棒銀・右四間)
相手が急戦で仕掛けてくる場合、四間飛車側にはいくつかの受け方・定跡があります。
◆棒銀対策
- 相手が早めに▲2五歩・▲2四歩と仕掛けてくる場合
- こちらは▲7七角や▲6七銀などで受ける
銀を安易に動かさず、角と飛車の連携で丁寧に対応しましょう。
◆右四間飛車対策
- 相手が▲4五歩から▲5五歩と強く攻めてくる型
- 玉側に厚みを持たせて高美濃や銀冠で受ける
持久戦における変化(居飛車穴熊など)
相手が居飛車穴熊などの持久型を選んできた場合、以下のような作戦を取りましょう。
| 相手の囲い | 四間飛車側の作戦 |
| 居飛車穴熊 | 四間飛車穴熊 or 端攻め策 |
| 高美濃 or銀冠 | 高美濃〜銀冠 |
| 矢倉 | 穴熊 or 速攻 |
穴熊対穴熊は、持久戦の王道で、終盤勝負になることが多いです。
藤井システムの登場とその影響
四間飛車の定跡を大きく変えたのが「藤井システム」です。
藤井猛九段によって提唱されたこの戦法は、居飛車穴熊に対して非常に有効な対抗策となります。
◆特徴
- 早めに角交換を仕掛けて主導権を握る
- 左銀の活用と角道オープンが鍵
- 美濃囲いの強化版をベースに構成
| 藤井システムの利点 | 弱点 |
| 穴熊に強い | 角交換に慣れていないと不利になる |
| 終盤力が活かせる | 序盤・中盤でミスると危険 |
四間飛車の定跡をどう学ぶか?
定跡は丸暗記ではなく、意味を理解しながら学ぶことが重要です。
◆おすすめの学習ステップ
- 基本の美濃囲い型定跡を理解
- 急戦への対応パターンを覚える
- 持久戦における組み合いの形を研究
- 藤井システムなどの発展型を試す
- 自分の棋風に合う変化型を採用する
定跡本だけでなく、実戦譜やYouTube、将棋ウォーズの棋譜解説を活用するのも効果的です。
四間飛車の勝率とプロ・アマでの採用率
四間飛車はアマチュア将棋ファンに人気の戦法として知られていますが、実際の勝率やプロ棋士の採用状況はどうなのでしょうか。
ここでは、統計的な視点から四間飛車の実力と現状を詳しく解説していきます。
将棋ウォーズ・将棋クエストにおける四間飛車の勝率
オンライン将棋アプリ「将棋ウォーズ」や「将棋クエスト」では、多くのプレイヤーが四間飛車を使っています。
◆勝率データ(将棋ウォーズ:初段〜三段帯)
| 戦法 | 採用率 | 勝率 |
| 四間飛車 | 約15% | 約52〜54% |
| 三間飛車 | 約8% | 約50% |
| 居飛車急戦 | 約20% | 約55〜57% |
四間飛車は非常に安定した勝率を誇っており、特に「美濃囲い」や「藤井システム」に精通しているユーザーは、さらに高い勝率を上げている傾向があります。
プロ棋士による四間飛車の採用事例
近年、プロ棋士による四間飛車の採用率は減少傾向にありますが、過去には多くのトップ棋士が積極的に採用していました。
◆四間飛車(振り飛車)を得意とする代表棋士
- 藤井猛 九段:藤井システムの創始者。1990年代〜2000年代にかけて四間飛車旋風を巻き起こす。
- 久保利明 九段:自在な振り飛車使い。四間飛車穴熊などの構想が有名。
- 糸谷哲郎 八段:対抗形にも明るく、居飛車党の中でも四間飛車経験が豊富。
最近は角交換型振り飛車やノーマル振り飛車が中心になっており、純粋な四間飛車は少なめですが、定跡を熟知した棋士により時折採用されます。
アマチュアにおける四間飛車の有効性
アマチュアにとって、四間飛車は「学びやすく勝ちやすい戦法」として人気があります。
特に以下のような特徴が理由です。
◆アマチュアに人気の理由
- 美濃囲いがシンプルで強い
- 定跡が比較的少なく覚えやすい
- 相手の出方を見て柔軟に対応できる
- 対急戦・対穴熊どちらにも対応策がある
将棋ウォーズや将棋クエストでは、勝率50%以上を安定して維持できるプレイヤーも多く、「四間飛車で初段を目指す」などの戦略にも向いています。
勝率アップのために意識すべきポイント
四間飛車を用いたときに勝率を高めるためには、以下の点を意識することが大切です。
| 重点項目 | 解説 |
| 美濃囲いの完成を 最優先にする | 中盤戦前までに玉を3八(or7二)まで移動させる |
| 相手の戦法を見極める | 急戦か持久戦かを早い段階で判断する |
| 銀の運用 | 銀を早く捌かず、守備と攻撃のバランスを取ること |
| 飛車の再活用 | 中盤以降、中央や端に飛車を再配置して主導権を握る |
| 角の活用 | 角道を開ける・閉じるの判断が勝敗に直結する |
単なる囲いの完成だけでは勝てず、局面ごとの駆け引きや形勢判断ができるようになると勝率が一段と上がります。
四間飛車の苦手な戦法とその対策
四間飛車は柔軟性があり人気の高い戦法ですが、特定の戦型や急戦策に対しては不利になりやすい場面もあります。
ここでは、四間飛車が苦手とする戦法を具体的に挙げ、その対策方法もあわせて解説します。
苦手とされる急戦の種類
特に対四間飛車で有効とされる急戦策は、以下のようなものがあります。
| 戦法名 | 概要 |
| 急戦棒銀 | 居飛車側が棒銀で早めに仕掛ける。角交換も狙われやすい。 |
| 居飛車穴熊急戦 | 鉄壁の囲いから一気に銀桂で攻められる |
| 山田定跡 | 銀を活用し角を引いてから端攻めを行う |
| ミレニアム対策 | 固く囲ってから飛車・角の両方でバランスよく攻めてくる |
これらの戦法は、四間飛車が玉を囲う前に早仕掛けで潰しにかかるのが特徴です。
急戦棒銀への基本対策
急戦棒銀は四間飛車にとって最もポピュラーな対策のひとつです。
対応を間違えると一方的に押し込まれてしまうので、以下の点に注意しましょう。
◆対策ポイント
- 早囲いせず、角道を止めて棒銀を牽制する(▲7七角〜▲6八玉型など)
- 銀を引かせるように間合いを取る(美濃囲い完成を急がない)
- 角交換に備え、飛車先の歩交換を済ませておく
特に▲7七角と上がって角交換を拒否する構えは、急戦に強く柔軟な布陣です。
居飛車穴熊に対する戦い方
居飛車穴熊は受けの硬さが抜群ですが、攻撃力はそこまで高くありません。
四間飛車側は長期戦に持ち込まず、持久戦を避けるのがコツです。
◆対策の工夫
- 速攻で仕掛ける「藤井システム」や「斜め棒銀」などの急戦策を選ぶ
- 銀冠や高美濃囲いに移行してバランスを取り、攻め合いを避ける
- 歩交換で相手の飛車を制限し、桂跳ね・端攻めの隙を狙う
また、角交換からの飛車先突破を防ぐため、▲7七角型や▲6六歩で角筋を限定しておくのも有効です。
ミレニアムなどの新型囲い対策
近年登場した「ミレニアム囲い」や類似のバランス型囲いは、四間飛車にとって対応が難しいとされています。
◆対策のコツ
- 自玉を早めに囲って、囲い合戦を制する(高美濃 or 銀冠に移行)
- 飛車先を突かず、中央からの攻めを視野に入れる
- 角交換を避けて、角道封鎖で持久戦を有利に運ぶ
ミレニアムは強いが重たい囲いなので、スピード勝負に持ち込むことで崩しやすくなります。
四間飛車側がやってはいけない失敗例
四間飛車は受けから攻めに転じる戦法ですが、間違った手順を踏むと一方的に攻め込まれてしまいます。
| 失敗パターン | 解説 |
| 早囲いしすぎる | 美濃囲いを急ぎすぎて中央を疎かにすると潰されやすい |
| 角道を早く開ける | 角交換後の飛車先突破を招く |
| 銀を中央に出しすぎる | 相手の急戦に対する受けが間に合わなくなる |
| 玉の囲いが中途半端 | 一手の緩みが致命傷になることもある |
特に「角道を開けたまま囲う」ミスは、棒銀や早繰り銀の格好の餌食になります。
苦手戦法を逆手に取る戦術的発想
相手が急戦や居飛車穴熊で来ると予想できるなら、その特性を逆に活かすことも可能です。
◆実践的な逆手戦法
- 相手の早仕掛けに対して「引き飛車」構えで待ち構える
- 意図的に角交換を誘い、飛車を回ってカウンターを狙う
- 中央の位を取ってから、玉頭戦に持ち込む(△4五歩など)
このような構想を持つと、苦手な戦法にも「慣れ」が生まれ、勝率を落とさずに済みます。
四間飛車をさらに深めるための勉強法とおすすめ書籍
四間飛車を使いこなすには、定跡の理解だけでなく、実戦経験や局後の検討も大切です。
このセクションでは、四間飛車を上達させるための勉強法と、初心者から上級者まで使えるおすすめ書籍・動画を紹介します。
初心者におすすめの勉強法
将棋を始めたばかりの方が四間飛車を学ぶ場合、いきなり高度な変化を追うのではなく、基礎を固めることが最優先です。
◆学習ステップ
- 定跡の流れを覚える
美濃囲いまでの囲い方や、基本的な仕掛けを反復練習します。 - 短い対局で実践する
将棋ウォーズや81Dojoなどで10分以下の対局を多くこなし、実戦で慣れましょう。 - 負けた対局を振り返る
囲いが完成しているか?角交換への備えは十分か?毎回検証します。
最初は「形を作る」ことに集中し、無理な攻めは避けるよう心がけると上達が早まります。
中級者向けの学習法とポイント
四間飛車にある程度慣れてきたら、局面ごとの判断力や中盤の構想力を磨いていくことが重要です。
◆中級者の課題と克服法
| 課題 | 対策法 |
| 構想がわからない | 有段者の対局を並べて、手の意味を解説付きで理解する |
| 相手の急戦に対応できない | 棋書やYouTubeで「対急戦」の章に特化した解説を学ぶ |
| 指し手が単調になりがち | 同じ形ばかりではなく、穴熊・高美濃・銀冠など囲いを使い分けて柔軟性を高める |
また、棋譜並べや「詰将棋」も思考力を養うのに非常に効果的です。
おすすめの四間飛車関連書籍・動画
四間飛車に関する良質な教材は多く出版されており、自分のレベルに合ったものを選ぶのがポイントです。
◆初心者向け書籍
| 書名 | 著者 | 特徴 |
| 四間飛車を指しこなす本【1〜4巻】 | 藤井猛 | 定跡+戦略をシリーズ形式で学べる。藤井システムの理解にも◎ |
| 将棋・基本戦法まるわかり事典 | 週刊将棋編 | 基本的な定跡の流れが図解で理解しやすい |
| 見て覚える四間飛車入門 | 所司和晴 | 写真付きで視覚的に理解しやすく、全体像が掴める |
◆中上級者向け教材
| 書名 | 著者 | 特徴 |
| これが最前線!振り飛車破り | 渡辺明 | 対四間飛車の視点で、弱点をどう突くかが学べる |
| 最新戦法マル秘ファイルシリーズ | いろいろなプロ | 各年のトレンドや新構想が載っており、実戦で役立つ |
| 相振り飛車で勝つ! | 野月浩貴 | 四間vs四間など、相振りの研究に役立つ |
◆おすすめ動画・YouTubeチャンネル
- 将棋放浪記(プロ棋士藤森哲也五段)
四間飛車対急戦を丁寧に解説しており、定跡だけでなく考え方も学べます。 - 将棋YouTuberアゲアゲさん
実戦形式で四間飛車を多く採用しており、動画のテンポも良好。 - プロ公式配信(ABEMA将棋、将棋連盟Live)
タイトル戦などでプロが四間飛車を選択する局面もあり、研究の参考になります。
勉強の優先順位と戦法の絞り方
たくさんの戦法がある中で、何から勉強するか迷うことも多いはずです。
特に振り飛車派の中では、四間飛車を極めるだけでも非常に奥が深いです。
◆優先順位のつけ方
- 美濃囲いの基本形をマスター
- 角交換対策(▲7七角型や角道封鎖)の定跡を習得
- 居飛車急戦・穴熊に対する複数パターンを習得
- 攻め筋(端攻め・銀の繰り出し)を身につける
複数の囲いや構想を知っておくと、相手の戦型に合わせて戦法を「絞る」ことができ、柔軟な対応が可能になります。
学んだことを実戦で活かす方法
インプットだけでは上達しません。
アウトプットとして、日々の対局の中で使ってみることが何より大切です。
◆実戦活用法
- 将棋ウォーズやぴよ将棋で「テーマ局面」からスタートし、特定局面の繰り返し練習をする
- 検討機能を活用して、悪手・疑問手の理由を毎回振り返る
- 学んだ戦法を日記やブログ、X(旧Twitter)でアウトプットする
自分の思考を言語化することで、再現性の高い将棋を指せるようになります。
四間飛車の魅力を再確認しよう
四間飛車は、初心者からプロ棋士まで幅広く愛される戦法です。
このセクションでは、ここまでの内容を振り返りながら、四間飛車がなぜこれほど人気なのか、その魅力を再確認していきましょう。
四間飛車の戦術的魅力
四間飛車の最大の特徴は、バランスの取れた攻守一体の構えにあります。
- 美濃囲いの堅さ:相手の攻めを耐えつつ、反撃を狙える囲いとして非常に優秀。
- 角の活用幅が広い:後手でも主導権を握りやすく、自由な発想が活かされる。
- 柔軟な戦術対応:急戦・持久戦・相振りなど幅広い展開に対応可能。
このように、四間飛車は「受けから攻めへ」の切り替えがスムーズで、まさに“万能型”の戦法といえるでしょう。
四間飛車で得られる上達効果
四間飛車を学ぶことで、将棋そのものの理解も深まります。具体的なメリットは以下のとおりです。
| 上達ポイント | 内容 |
| 駒組みの力 | 美濃囲いや銀冠など、基本的な囲いが自然に身につく |
| 守備感覚 | 相手の攻め筋を先読みし、受けを厚くする思考が育つ |
| 終盤力 | 反撃を含んだ寄せ筋を意識するようになるため、詰めの力も養われる |
初心者でも手順を覚えればすぐに指し始められ、繰り返すことで自然に“将棋脳”が鍛えられるのが大きな魅力です。
自分だけの四間飛車を見つけよう
四間飛車には多くの派生や進化形があり、自分のスタイルに合った形を見つける楽しさがあります。
例えば
- 穴熊+四間飛車:守備を最優先した構成で、粘り強い勝負ができる。
- 藤井システム型:積極的な角交換と仕掛けで、主導権を握る。
- 高美濃・銀冠型:攻守のバランスをさらに高めた発展型。
このように、四間飛車は“型にはまらない柔軟性”こそが醍醐味。
戦術の幅を広げ、自分だけの戦い方を見つけていく過程そのものが、将棋の面白さにつながっていきます。
将棋ライフに四間飛車を取り入れてみよう
四間飛車は、単なる「戦法」にとどまりません。
将棋を長く楽しみ、強くなっていくための“入り口”としても最適です。
- 将棋が楽しくなるきっかけをくれる
- どんな相手にも戦える自信がつく
- 上達するプロセスが実感できる
初心者でも気軽に始められる一方で、極めれば深淵な世界が広がっている。
それが四間飛車の最大の魅力です。
◆まとめ:四間飛車は将棋上達への最短ルート
最後に、四間飛車を学ぶべき理由をまとめておきます。
- 初心者でも構えやすく、囲いと攻めの基本が学べる
- 美濃囲いによる守備の堅さと、角の位置を活かした攻め筋が秀逸
- 急戦や持久戦、相振りにも柔軟に対応できる
- 書籍・動画・アプリが豊富で独学でも伸びやすい
- 自分なりの工夫を加える楽しさがある
「これから将棋を始めたい」「振り飛車を極めたい」「勝率を上げたい」という方には、間違いなくおすすめの戦法です。
あなたも今日から、四間飛車で将棋の楽しさを広げてみてはいかがでしょうか?
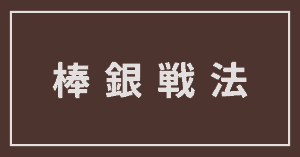
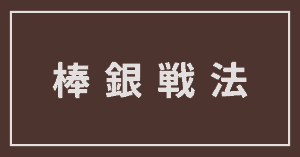
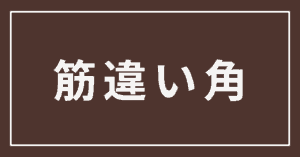
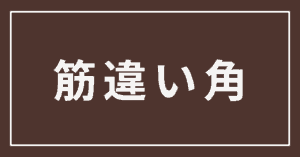
将棋の相掛かりの定跡・対策・棋譜まとめ|初心者にもわかりやすく
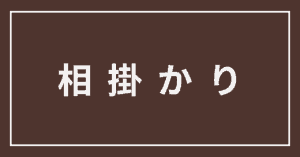
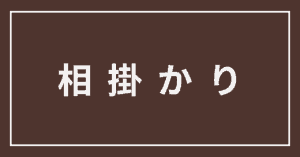
将棋の中飛車・ゴキゲン中飛車を徹底解説|最新定跡・対策・評価の真相とは?


将棋の三間飛車とはどんな戦法?石田流との違い・組み方・対策まで徹底解説
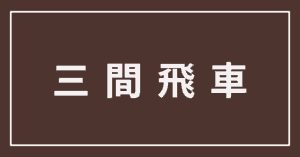
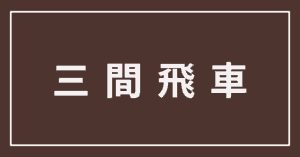
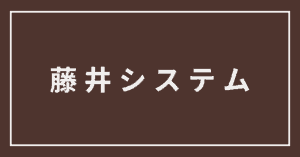
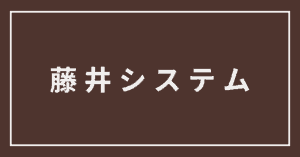
将棋の戦法一覧|初心者向けから最強戦法・奇襲型まで完全解説!

