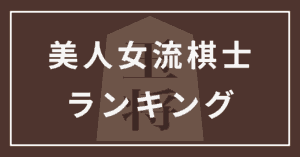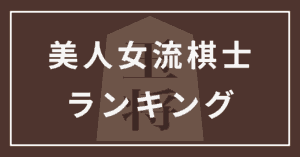将棋を指していると、なかなか勝てない時期が続き、「もう向いていないのかもしれない」「辞めた方がいいのでは」と感じることがあります。特に初心者のうちは、何をどう改善すれば良いのかがわからず、イライラしたり、将棋がつまらなく思えてしまうこともあるでしょう。
しかし、将棋が難しいのは当たり前であり、誰もが最初は負けから始まります。実際にプロ棋士でも、将棋を始めた頃は何度も負けて学びを重ねています。大切なのは、負けた原因を振り返り、正しい方法で少しずつ改善していくことです。
この記事では、「将棋で勝てない」と悩む方に向けて、その原因と対処法を段階的に解説していきます。初心者・中級者どちらにも役立つ内容なので、辞めてしまう前にぜひ読んでみてください。
◆アプリダウンロード数4,000万突破!


将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、
【 ABEMA
プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。
>> 将棋見るならABEMA
将棋で勝てない初心者が最初に見直すべき基本
将棋を始めて間もない時期は、ルールを覚えただけではなかなか勝てません。感覚に任せて指してしまうことが多く、相手の狙いや自分の陣形を意識せずに進めてしまうからです。まずは土台となる基本を見直すことが、勝率アップの第一歩になります。
目的を意識して指すことの重要性
将棋の目的は相手の王様を詰ませることですが、実際に対局をしていると、その目的を見失いがちです。たとえば、目先の駒を取ることに夢中になったり、自陣の守りを疎かにして攻めだけに意識が向いてしまったりすると、あっという間に逆転されてしまいます。
駒を動かすときは、「この手は勝ちに向かっているか」「相手の狙いを消しているか」を考えることが大切です。なんとなく動かすのではなく、一手一手に意味を持たせるだけでも、結果は大きく変わります。
駒の価値を理解する
初心者がよくやってしまうのが、駒の損得を無視した交換です。たとえば、飛車と金を交換したり、角と銀をただで取られたりするなど、駒の価値を理解していないと、自然と不利な展開になります。
以下のような目安で駒の価値を捉えておくと、損得の判断がしやすくなります。
| 駒 | 価値の目安 | 解説 |
| 歩 | 1点 | 取って打つだけでも強力 |
| 香車 | 3点 | 一方向だが、端攻めでは重要 |
| 桂馬 | 4点 | 独特な跳ね方で攻めに有効 |
| 銀 | 5点 | 攻守に使える柔軟な駒 |
| 金 | 6点 | 玉を守る要、守備に必須 |
| 角行 | 8点 | 斜めに効く、攻撃力が高い |
| 飛車 | 10点 | 最強の攻撃駒、守りにも使える |
駒の価値を把握しておくと、交換の際の判断がぶれなくなり、自然と有利な展開が作れるようになります。
自陣の守りを疎かにしない
攻めることばかりに気を取られて、自玉の囲いを忘れてしまうと、相手の反撃を受けたときに一気に負けてしまいます。特に初心者は、矢倉囲いや美濃囲いといった基本的な囲いを覚えていないまま対局を始めてしまうことが多いです。
基本的な囲いを一つ覚えておくだけで、玉の安全度は飛躍的に上がります。序盤でいきなり攻めるのではなく、まずは囲いを整え、玉を安全な場所に移してから戦うようにしましょう。
たとえば以下のような囲いが、初心者にも扱いやすい基本形です。
| 囲い名 | 特徴 | おすすめ度 |
| 矢倉囲い | バランスが良く中央に強い | ★★★★☆ |
| 美濃囲い | 振り飛車に最適、囲いやすい | ★★★★★ |
| 舟囲い | 簡単に組めるがやや脆い | ★★★☆☆ |
囲いは“守りの構え”だけでなく、“攻めの準備”でもあります。守りが堅ければ堅いほど、攻めにも余裕が生まれるのです。
駒を無駄に動かさない意識
初心者のうちは、たくさん駒を動かすことが良いことだと思いがちですが、実は無意味な手が増えれば増えるほど、自陣が乱れて勝ちにくくなります。
たとえば、序盤で歩を4筋も5筋も突いてしまい、結果的に守りが崩れてしまうケースがあります。駒は「動かすこと」ではなく「使うこと」が大切です。
動かす前に「この手は何を狙っているのか」「次の手につながっているか」を一度確認するようにすると、無駄な手が減り、自然と手の質が上がります。
将棋で勝てない時期に起こるスランプと抜け出し方
将棋を継続して指していると、ある時期に急に「全然勝てなくなった」と感じることがあります。序盤も中盤もそれなりに指せているのに結果が出ない、以前より負けが増えた気がする——そんな時期は「スランプ」に入っている可能性が高いです。
スランプの原因は、技術的なものだけでなく、心理的・習慣的なものもあります。この章では、将棋におけるスランプの原因と、その脱出方法について解説していきます。
焦って勝とうとするとミスが増える
勝てない時期が続くと、どうしても「次こそは勝たなきゃ」と気持ちが焦ってしまいます。しかし、この“勝ちたい”という思いが強すぎると、冷静な判断ができなくなり、かえってミスを誘発してしまいます。
例えば、自分が不利だと感じた局面で、無理に攻めに転じた結果、相手の反撃を受けて一気に敗勢に陥ることがあります。本来なら受けて形勢を保てた局面なのに、「とにかく逆転したい」という気持ちが前のめりになっているのです。
将棋は感情で指すものではなく、理性で組み立てるものです。だからこそ、勝てないときほど「丁寧に」「自玉の安全を優先して」「リスクを避ける」ような指し回しが必要になります。
戦型を変えて新鮮な気持ちで臨む
スランプが続いているときには、思い切って普段と違う戦型を指すのも有効です。たとえば、普段は居飛車党の人が、あえて振り飛車に挑戦してみることで、局面の進行が変わり、思考がリセットされます。
同じ戦型ばかり指していると、自分でも気づかないうちにワンパターンな展開に陥っていたり、よく負ける局面に誘導されやすくなったりします。
以下のような戦型変更はおすすめです。
| 現在の戦型 | 試してみる戦型 | メリット |
| 居飛車(矢倉) | 四間飛車・中飛車 | 構想力や柔軟性が身につく |
| 振り飛車(美濃) | 居飛車急戦 | 守備意識や攻め筋を逆側から学べる |
| オールラウンド | 細かく絞った定跡 | 定跡を深掘りして読みの精度を高める |
新しい形に取り組むことで、脳が活性化し、将棋そのものが楽しくなります。それがスランプ脱出の第一歩です。
勝敗よりも「学び」を意識する
スランプ時は「また負けた」と勝敗ばかりに気を取られがちですが、この時期こそ「何を学べたか」に目を向ける姿勢が重要です。
たとえば、以下のようなことを意識してみてください。
- 自分の指した悪手はどこだったか
- 相手の手で「気づかなかった一手」はあったか
- 中盤の駆け引きで、どちらが主導権を持っていたか
これらは単なる反省ではなく、次の一局に確実につながる“経験値”です。勝ち負けではなく、「昨日よりも読みの精度が上がった」「受けの手筋を1つ覚えた」という視点を持つと、将棋がまた面白くなってきます。
スランプは決して後退ではなく、成長の“途中経過”です。いわば、勉強でいう“伸び悩みの壁”と同じで、その先には必ず新しい世界が待っています。
将棋がつまらないと感じるのは伸びしろの証拠
勝てない時期が続くと、将棋そのものが「つまらない」と感じてしまうこともあります。ですが、これは単に“慣れてしまった”ことによる停滞であり、ある意味で成長段階にいる証です。
将棋の本質的な楽しさは「勝つこと」よりも、「考えて、工夫して、わかった瞬間」にあります。勝てない局面を振り返って、「この一手、こう指していれば勝てたかも」と気づけた時、それは実力が着実に伸びている証です。
つまらないと感じたら、それは停滞期。もう一段上の将棋に進む準備ができたサインでもあるのです。
終盤で逆転されて将棋に勝てない人の共通点
将棋で「あと一歩までいったのに負けた」という経験は誰にでもあります。序盤・中盤を有利に進めていたはずなのに、最後の最後で逆転されてしまう。こうした終盤の逆転負けは、ただの運ではなく、明確な理由が存在します。
このセクションでは、終盤で勝てない人に共通する弱点と、その改善方法について解説します。将棋において終盤力は勝率を大きく左右する重要な要素です。
詰みを読まずに攻めると逆転される
多くの人がやりがちなのが、「相手の玉が詰んでいないのに攻め続ける」というミスです。詰むと思い込んで無理に攻めを続けた結果、攻めきれずに持ち駒を使い切り、逆に自玉が寄せられてしまう。これが逆転の典型例です。
詰みがあるかどうかを判断せずに攻めると、相手に反撃のチャンスを与えることになります。詰みの有無をしっかり確認することが、終盤における大前提です。
対策としては、「詰みがあるか」ではなく「詰みがないことを確認したか」という逆の視点を持つことです。相手玉に迫る際には、少なくとも「3手詰」「5手詰」の確認を毎回する習慣をつけましょう。
寄せの形を知らないと勝てない
「寄せ」とは、詰みの直前まで相手玉を追い詰めていく一連の手順のことです。詰将棋と違い、相手が自由に逃げられる局面で、どうやって捕まえるかが問われます。ここが曖昧なままだと、リードを活かせずに逆転されることになります。
寄せの基本パターンは、ある程度“形”で覚えることが可能です。例えば、以下のような寄せ筋は多くの実戦で使われています。
| 寄せパターン | 特徴 |
| 飛車と金での頭金 | 初心者にも分かりやすい基本形 |
| 角打ちで玉の逃げ道封鎖 | 持ち駒の使い方として頻出 |
| 駒を捨てて誘導 | 最短で詰ますためのテクニック |
寄せが下手だと、「攻めはうまくいっているのに勝てない」という感覚になります。これは非常にもったいない状態です。詰将棋と合わせて「寄せの手筋」も学んでいくと、勝ちきる力が身につきます。
おすすめは以下のような教材です。
- 書籍『寄せの手筋200』
- 詰将棋アプリ『詰将棋パラダイス』
- YouTubeの「寄せ特化」解説動画
こうしたツールで少しずつ寄せの形を覚えると、終盤で焦ることが減り、冷静に勝ち切れるようになります。
短い詰将棋を毎日解くことが終盤力を鍛える近道
終盤に強くなるための最も効果的な勉強法が「詰将棋」です。特に一手詰・三手詰といった短い問題を日課にすることで、詰み形を自然に覚えることができます。
詰将棋は単に「詰みを解く練習」ではありません。以下のような力を養うことができます。
- 局面を正確に見る力
- 効率的に手を読む思考習慣
- 相手玉の逃げ道を塞ぐ感覚
初心者であれば、まずは以下のようなセットをおすすめします:
| 詰将棋レベル | 推奨教材 | 1日量の目安 |
| 1手詰 | 『1日1題 詰将棋』 | 10〜20問 |
| 3手詰 | 『3手詰ハンドブック』 | 5〜10問 |
| アプリ | 将棋アプリ「ぴよ将棋」 | 毎日1〜2局でOK |
このように、日々の習慣として取り入れるだけで、終盤での詰みを逃すことが大幅に減り、勝てる将棋をしっかり勝ちきれるようになります。
また、短手数の詰将棋は隙間時間でも学習できるので、無理なく継続できます。将棋は継続した学びが実力に直結するゲームです。詰将棋に毎日1分でも取り組むことは、将来の勝率を大きく左右する投資といえます。
定跡や読みが浅くて将棋に勝てない理由と対策
将棋でなかなか勝てないと感じる理由のひとつに、「定跡が曖昧」「相手の狙いが読めない」といった読みの浅さがあります。駒の動かし方や囲いの知識はあっても、次に起こる展開を想像できなければ、対応が後手に回って形勢が不利になりがちです。
この章では、定跡や読みの力がなぜ重要なのか、そしてそれらをどう鍛えていくべきかを解説していきます。
相手の狙いを読む習慣がないと形勢を見失う
将棋は「自分のやりたいことを押し通す」だけでは通用しません。なぜなら、相手にも計画があり、こちらの構想を妨害してくるからです。
つまり、相手の狙いを読むことが防御と攻撃の第一歩になります。
たとえば、自分が囲いを作っている最中に、相手が角道を空けてきたとします。その意味を考えずに構わず指していると、次の数手で角交換から自陣が崩される展開になるかもしれません。
相手の手を見て、「これは何を狙っているのか」「何手後にどんな攻撃につながるのか」を想像する習慣をつけるだけで、終盤の読み合いにも強くなります。
おすすめは、対局後に以下のような項目を記録しておくことです。
- 相手のこの手は自分の何を狙っていたのか
- それに対する自分の手は有効だったか
- 次回、同じ局面でどう受けるべきだったか
この振り返りを繰り返すことで、自然と「相手の意図を読む力」が育っていきます。
定跡を「形」として覚えていないと戦いに遅れる
定跡(ていせき)とは、過去のプロの膨大な実戦や研究によって確立された“最善手の流れ”です。もちろん定跡だけで将棋に勝てるわけではありませんが、序盤〜中盤で明らかに形勢が傾くようなミスを減らすための重要な指針となります。
しかし、「定跡を覚えた」と言っても、それが“意味として理解されていない”場合には意味がありません。ただの手順の丸暗記では、少しでも変化が起こると対応できなくなるからです。
たとえば矢倉戦法で6七銀型に構える定跡があるとしても、なぜその銀がそこにいるのか、どんな狙いを持っているのかが理解できていないと、相手が少し違う手を指しただけでパニックになります。
以下のような順序で定跡を学ぶのがおすすめです。
| ステップ | 内容 |
| ① 図で形を覚える | まずは駒の配置を目で覚える |
| ② 解説つき動画を見る | 手の意味を理解する |
| ③ 実戦で試してみる | 自分で指して感覚をつかむ |
| ④ 変化形の解説を読む | 相手の応手による変化に対応する |
定跡は「知識」ではなく「使える技術」として学ぶことが大切です。最初からすべてを覚えようとせず、自分の得意戦法だけでも深く理解することから始めましょう。
「慣れ」で指しているうちは勝てない
初心者〜中級者が陥りやすいのが、「いつもこの形にしてるから」「なんとなくこう指しているから」というような“慣れ”による手の選択です。これでは、相手が変則的な手を指してきたときに対応できず、混乱してミスを連発してしまいます。
将棋は、局面に応じて最適解を考え続けるゲームです。「形を覚えたら強くなれる」と思いがちですが、実際には形から外れた時の判断力こそが勝敗を分けます。
この“慣れ”を打破するためには、以下のような訓練が効果的です。
- 同じ戦法でも毎回違う指し方をしてみる
- 意図的に形を崩してみて、新しい対応策を考える
- 指した手に対して「なぜこの手を選んだか」を毎回説明してみる
こうした思考訓練を続けていくと、局面の変化にも柔軟に対応できる力が育ち、「勝てない」から「勝ちにいける」将棋へと変わっていきます。
実戦不足で将棋に勝てない人のためのアウトプット習慣
将棋の勉強を本や動画で真面目にしているのに、なかなか勝てない。そう悩んでいる人の多くが見落としているのが、「実戦(アウトプット)の不足」です。どれだけ知識を詰め込んでも、それを使う経験が足りなければ意味がありません。
この章では、将棋においてインプットとアウトプットのバランスをどう整えるか、そして実戦力を高めるための習慣化の方法を紹介します。
勉強熱心でも、頭でっかちでは勝てない
詰将棋や定跡の勉強、プロ棋士の対局観戦、将棋YouTuberの解説動画視聴——これらはすべて重要なインプットですが、それだけで強くなれるわけではありません。
「知っているけど、指せない」という状況に陥る原因は、実戦経験の不足です。つまり、知識があっても、それを使う場面で正しく引き出す練習が足りていないということです。
知識は道具です。しかし、それをどの場面でどう使うかは、実戦でしか身につきません。将棋は手を読むスポーツであり、実際に「間違える経験」を積み重ねることで上達していきます。
毎日1局でいい、実戦を日課にする
実戦を習慣化する最も手軽な方法は、「1日1局だけ指す」と決めることです。将棋アプリやオンライン対局なら5〜10分で終わるものもあり、忙しい人でも継続できます。
おすすめの将棋アプリ例
| アプリ名 | 特徴 | 所要時間 |
| 将棋ウォーズ | 初心者〜上級者まで幅広い | 3分切れ/10分将棋など |
| 将棋クエスト | 無料・登録不要・気軽 | 10分持ちなど |
| ぴよ将棋(スマホ) | AIと対戦・分析機能あり | 自分のペースで可能 |
大切なのは、「完璧に指そう」としすぎず、とにかく指すことを習慣にすることです。失敗してもいいので、盤面を見て、考えて、手を指す。この積み重ねこそが実戦力を育てます。
負けた対局を振り返るクセをつける
「対局後の振り返り」ができるかどうかで、成長スピードは大きく変わります。特に自分がなぜ負けたかを理解することは、勝つことよりも学びが多いのです。
振り返りのポイントは以下の3点です。
| 振り返り項目 | 内容 |
| 序盤 | 不利な展開にした一手はどこか? |
| 中盤 | 読みのズレや駒の損失はなかったか? |
| 終盤 | 詰みを逃した、受けを間違えた、など |
たとえば、将棋ウォーズやぴよ将棋などのアプリには「棋譜解析」機能があるため、評価値の上下や悪手・疑問手が一目でわかります。負けた対局をただ消化するのではなく、「どこが悪かったのか」「次にどう直すか」を自分の言葉で整理することが重要です。
また、勝った対局も復習することで、「なぜうまくいったのか」を再現できるようになります。これを繰り返すことで、着実に“自分の型”ができていきます。
実戦こそが最高の勉強になる
プロ棋士も、アマチュアも、最終的には「実戦でどれだけ手を読めるか」が勝負になります。知識を使う練習は、実戦以外ではできません。
特に以下のような能力は、実戦でしか養えません。
- 時間配分(どこで考え、どこで感覚的に指すか)
- 相手の意図を読み取る力
- 緊張感の中でのミス回避
- 勝ちきる力、粘り強く戦う力
これらの感覚は、いくら本を読んでも、動画を見ても、身につくものではありません。経験の積み重ねだけが、盤上での“強さ”を形作っていくのです。
最初のうちは負けても構いません。大事なのは「指し続けること」と「振り返ること」。それだけで、あなたの将棋は確実に強くなります。
受けが苦手で将棋に勝てないと感じたらやるべきこと
「攻めは得意だけど、守りが弱い」「先手を取っていたはずなのに、相手の反撃で一気に負けてしまう」
そんな経験がある方は、「受け」の力が足りていない可能性があります。将棋は攻めと守りのバランスが勝敗を分けるゲームです。攻めるばかりで自陣が手薄になってしまうと、少しの反撃で簡単に崩されてしまいます。
この章では、受けが苦手な人に共通する思考の癖と、それを克服するための実践的な方法を解説していきます。
相手の攻めを受け止める意識を持つ
将棋では、攻めを成功させるためにも「相手の攻め筋を受け止める意識」が必要です。受けとは、単に守るだけではなく、攻められても崩れない形を作ること、そして反撃の布石を打つことでもあります。
たとえば、相手が飛車を自陣に成り込んできたとき、焦って無理な攻めに転じようとすると、すぐに自玉が危険になります。こうした局面では、まず冷静に相手の攻めを止め、時間をかけて体勢を立て直す必要があります。
受けは「堪える力」でもあり、将棋の本質に非常に近い要素です。すぐに効果が出るものではありませんが、意識を変えるだけでも、勝率に大きく差がつくポイントです。
「読み」と「形」をセットで鍛える
受けの力を高めるには、ただ受けの手を指すだけでは不十分です。読みの精度と囲いの形、どちらも重要な要素として意識する必要があります。
まず、「読み」とは、相手の攻めがどこまで続くか、何手先まで見通せるかという力です。受けの場面では、「この手を指したら、次にどんな攻めが飛んでくるか」を想像し、その攻めをすべてしのげる手を探すことが求められます。
一方、「形」は、囲いの堅さや金銀の連携といった“構造的な守り”を指します。たとえば美濃囲いや矢倉囲いなど、定跡で知られる囲いは、形としての強さが証明されているものです。
| 代表的な囲い | 特徴 | 向いている戦型 |
| 美濃囲い | コンパクトで堅い | 振り飛車向き |
| 矢倉囲い | 中央への耐久力が高い | 居飛車向き |
| 舟囲い | 組みやすいが脆い | 初心者向け・急戦型 |
守備の形を知っているだけでも、相手の攻めに動じにくくなります。また、囲いは崩された後の「粘り」も重要で、簡単には負けない将棋を作る助けになります。
プロの受けを真似するところから始めよう
受けが苦手な人に最も効果的な学習方法のひとつが、「プロの棋譜を真似る」ことです。特に守備が強い棋士の棋譜を見ることで、「この局面でなぜ受けたのか」「どの駒を動かして受けを成立させたのか」といった、実戦的な判断基準が学べます。
守りの強いプロ棋士の例
| 棋士名 | 受けの特徴 |
| 羽生善治九段 | 攻守のバランスが極めて高く、受けの粘りが深い |
| 渡辺明九段 | 矢倉での受けに強く、反撃までの構想力に定評あり |
| 永瀬拓矢九段 | 「受け将棋」の代名詞、相手の攻めをすべて潰して反撃 |
YouTubeでも、プロ棋士による「受けの妙手」を紹介している解説動画が多数あります。最初は難しく感じるかもしれませんが、ひとつひとつ真似していくことで、自分でも受けを選べるようになります。
また、感想戦を丁寧に見て、「プロがどんな視点で受けを選んでいるか」を確認することも大切です。実際に将棋連盟の公式YouTubeやABEMA将棋チャンネルには、参考になる動画が多数あります。
攻めを活かすための“受け”という視点を持つ
「受けが苦手」と感じている人の多くは、「受け=後ろ向きな手」と捉えていることがあります。しかし実際には、受けは次の攻めを成立させるための“準備”です。
たとえば、自陣の守りを固めてから相手に攻めさせ、その隙に反撃する。これは非常に理にかなった戦い方であり、プロの将棋でも多く見られます。
将棋は「どちらが先に攻めるか」だけでなく、「どちらが相手の攻めをさばけるか」という勝負でもあります。だからこそ、受けを学ぶことは、攻めを強化することと同義なのです。
受けができるようになると、自信を持って攻めに出られるようになり、将棋全体のバランスが劇的に向上します。
将棋で勝てないときの“イライラ”と上手な付き合い方
将棋を続けていると、勝てない期間にストレスを感じたり、自分の弱さに腹が立ったりすることがあります。特に真面目に学んでいる人ほど、「こんなに頑張っているのになぜ勝てないんだ」とイライラしてしまうものです。
しかし、将棋は冷静な判断が求められるゲームです。感情の揺れがそのまま指し手の乱れにつながり、負けをさらに引き寄せてしまうという悪循環にもなりかねません。
この章では、将棋で勝てないときに感じるイライラとの付き合い方や、気持ちをリセットする具体的な方法を解説します。
感情がブレると、指し手もブレる
将棋は理性で指すゲームです。相手の手を冷静に読み、自分の計画と照らし合わせながら、一手一手を積み上げていく必要があります。ところが、イライラしていると判断が雑になり、無理な攻めや不必要な手待ち、安易な交換など、悪手が増えてしまいます。
「前局で負けた相手に勝ちたい」と思って無理攻めをしてしまったり、「早く勝ちたい」という焦りから詰めを見落としたりと、感情によるブレは将棋の質を確実に下げてしまいます。
冷静さを保つことが強さにつながる。これはプロの世界でも変わらない鉄則です。
イライラの正体は「上達したい」という強い思い
イライラするということは、それだけ将棋に対して本気で取り組んでいる証でもあります。どうでもいいと思っていたら、負けても何とも思わないはずです。
つまり、イライラ=上達の伸びしろです。
その感情を無理に抑え込もうとするのではなく、視点を少し変えてみましょう。「今の自分では納得いかない」からイライラするのであれば、それは明確な課題を認識しているということです。むしろ成長のチャンスと捉えるべきです。
大切なのは、そのエネルギーを「次どうするか」という改善思考に変換することです。
冷静さを取り戻すための習慣を持つ
勝てない日や連敗が続く日ほど、自分自身の気持ちを整理する時間を意識的に作る必要があります。以下は、実際に多くの将棋プレイヤーが取り入れている“気持ちの切り替え習慣”です。
| 習慣 | 効果 |
| 対局後に5分だけ深呼吸・ストレッチ | 身体を落ち着かせて心をリセットできる |
| その日のベスト手を1つだけメモ | ポジティブな学びで締めくくれる |
| SNSやアプリから一時的に離れる | 無意識に比較してしまうのを防ぐ |
| 棋譜を分析せずに寝かせて翌日見る | 感情が抜けた冷静な視点で振り返れる |
また、1週間に1日だけ「将棋をしない日」を作るのも効果的です。気持ちの余白が生まれると、視点が整理され、次に対局するときに驚くほど冷静になれます。
自分を責めず、感情を受け止めることが第一歩
勝てないときに「自分は才能がない」「向いてない」と責めてしまう人もいますが、それはまったくの誤解です。将棋は一朝一夕で結果が出るものではなく、時間をかけて積み上げていくものです。
また、実力が上がってくると、相手も強くなり、簡単には勝てなくなっていきます。勝率だけを見て落ち込むのではなく、「負けながらも内容が良くなっているか」「自分の課題が見えてきているか」を見ていくことが、健全な成長につながります。
感情を感じること自体は悪ではありません。その感情に飲み込まれず、自分の気持ちを客観視することが、結果的に勝率アップにもつながります。
将棋がつまらないと感じたときに試したい見直し法
将棋を続けていると、「最近なんだかつまらない」「指していても楽しくない」と感じることがあります。これは珍しいことではなく、将棋が生活の中で“習慣”になったときや、勝てない時期が続いたときに特に起こりやすい現象です。
この章では、将棋がつまらなく感じる理由を整理し、再び楽しさを取り戻すための考え方と実践法を紹介します。
惰性で続けると将棋が義務になる
将棋に限らず、どんな趣味でも「習慣」になった途端に“義務”のように感じてしまうことがあります。特に「毎日1局」「1日5手詰めを解く」といったルーティンを課している場合、モチベーションよりも“やらなきゃ”という気持ちが先行しがちです。
その結果、将棋が本来持っている「考える楽しさ」「読みが当たったときの快感」といった面白さを感じにくくなります。まるでタスクをこなすように将棋を指してしまうと、当然ながら楽しくなくなってしまうのです。
まずは「なぜ将棋をやっているのか」を自分に問い直すことが大切です。
- 強くなりたいから?
- 勝ったときの達成感が嬉しいから?
- 誰かと共有したいから?
その動機を思い出すことが、つまらなさから抜け出す第一歩になります。
楽しさを再発見するための工夫
将棋の楽しさを思い出すためには、あえて“日常と違う角度”から将棋に触れてみるのが効果的です。以下は、実際に効果があったとされるリフレッシュ法の例です。
| 方法 | 内容と効果 |
| 好きなプロ棋士の対局観戦 | 美しい手や構想を見て将棋の魅力を再認識できる |
| 子ども・初心者に教えてみる | 将棋の基礎の面白さを再発見できる |
| 普段と違う戦型で遊ぶ | 慣れた手順から解放されて自由な発想を取り戻せる |
| 詰将棋をアートとして楽しむ | 問題の美しさや構成の妙を味わえる |
将棋は「勝ち負け」以外にも、構想・芸術性・歴史的背景・人間ドラマといった、さまざまな側面を持っています。そうした多様な魅力に触れることで、「つまらない」と感じていた気持ちが次第にほぐれていきます。
「伸び悩み」は飽きではなく上達の前兆
将棋がつまらないと感じるもう一つの理由は、伸び悩みです。これは非常に重要なサインです。実は、一定の段階まで実力が上がった人がその次の壁にぶつかると、「飽きた」と錯覚してしまうことが多くあります。
- 勝率が横ばい
- 覚えることが多すぎて混乱
- 勉強してもすぐに成果が出ない
これらはすべて、成長の“踊り場”にいる証拠です。スランプの一種とも言えますが、ここを乗り越えると一段上のレベルに進むことができます。
この時期に大切なのは、「進み方を変える」ことです。たとえば、以下のような見直しが有効です。
| 見直しポイント | 対応策 |
| 勉強法がマンネリ化している | 新しい教材・アプリ・動画講座を試す |
| 対局が作業化している | 目的を持った1局(戦型練習など)に切り替える |
| 強くなっている実感がない | 昔の自分の棋譜を見て変化を確認する |
少しずつでも変化を取り入れていけば、「また指したくなる」将棋が戻ってきます。
無理に続けないことも“楽しさ”を守る手段
どうしても将棋が楽しく感じられないときは、無理に続けないことも大切です。少し離れて他の趣味に時間を使う、将棋から完全に離れるのではなく「観る将棋」や「読む将棋」に切り替えてみるのも選択肢のひとつです。
大事なのは、「続けること」ではなく「やりたいときに戻ってこられる状態」を作ること。離れている間に、自分がどれだけ将棋を好きだったかに気づくことも少なくありません。
そして戻ってきたときには、きっと以前よりも深く、将棋の面白さを味わえるようになっているはずです。
将棋を辞めたいと思ったときの考え方と判断基準
将棋を長く続けていると、「もう辞めたほうがいいのかな」と思う瞬間が訪れることがあります。勝てない期間が続いたり、モチベーションが下がったり、他のことに時間を割きたくなったりと、その理由は人それぞれです。
このセクションでは、「将棋を辞めたい」と感じたときに立ち止まって考えたい視点や、辞めるかどうかの判断基準について整理します。辞めることが悪いわけではなく、「自分にとって必要な選択かどうか」を見極めることが何より大切です。
一時的な感情か、長期的な意思かを見極める
まず最初に確認したいのは、「辞めたい」という気持ちが一時的なものなのか、それとも長期的な意思に基づいているかという点です。
一時的な感情でありがちなのは以下のようなパターンです。
- 連敗が続いていて心が折れそう
- SNSで強い人と比べて落ち込んだ
- 他の趣味に時間を奪われている
これらは感情が一時的に揺れているだけの可能性が高く、時間が経てば「やっぱり将棋を指したくなった」と気持ちが戻ることもよくあります。
逆に、次のような気持ちが続いている場合は、本格的に辞めるかどうかを考えるタイミングかもしれません。
- 将棋を指しても全く楽しくない
- 日常に支障が出るレベルで将棋が負担
- 明確な目標をすでに達成し、次の興味が他にある
感情と習慣のバランスを見直すことで、自分にとって最適な距離感を見つけられます。
辞める前に「変える」という選択肢を持つ
将棋を辞めたいと感じる理由が「つまらない」「成果が出ない」などであれば、辞める前に「今のスタイルを変える」ことも選択肢の一つです。
以下に、変化を加えることで再び将棋を楽しめるようになった事例を紹介します。
| 現状の悩み | 試した変化 |
| 勝てない・飽きた | 定跡ではなく“感覚”で自由に指してみる |
| 時間が取れない | 1日1局から、週末の1局に減らす |
| 勉強がつらい | 動画や漫画など“観る将棋”に切り替える |
| 一人で孤独 | オンライン将棋会や大会に参加して仲間を作る |
将棋は「プロを目指す」だけが目的ではありません。自分に合った楽しみ方を模索することが、結果的に続けられる秘訣になります。
将棋が人生にもたらしてくれたものを振り返る
辞めるかどうか迷ったときには、これまで将棋から得たことを振り返ってみるのも効果的です。
たとえば…
- 読む力がついた
- 論理的に考える習慣がついた
- 忍耐力や集中力が身についた
- 共通の趣味を通じて仲間ができた
こうした経験は、たとえ将棋から離れることになっても、人生の中で価値のある財産として残り続けます。「辞めたら無駄になる」と思うのではなく、「すでに多くのものを得ている」と前向きに捉えることで、気持ちも楽になります。
辞めることは“悪”ではない
何かを辞めるとき、人は「続けなければいけない」「途中で投げ出すのはよくない」と思いがちです。しかしそれは、必ずしも正解ではありません。
将棋はあくまで趣味や自己表現の一つであり、義務ではありません。人生の中で優先したいことが変わったり、価値観が変化したりすれば、将棋との関わり方も変わって当然です。
大事なのは、「納得して辞めること」「また戻りたくなったらいつでも戻れる状態でいること」です。辞めたとしても、それまでの経験や思い出が消えるわけではありません。
いつ辞めるかを決めるための3つの基準
最後に、将棋を辞めるかどうかを自分で判断するための基準を3つ紹介します。
- 続けることで自分にとっての利益や喜びがあるか?
- 将棋のせいで他の大切なことが犠牲になっていないか?
- 今後も将棋とどう関わりたいか明確なイメージが持てるか?
この3つを自問自答してみて、「今は離れる時期だ」と思えたら、それも立派な決断です。逆に「やっぱりもう少し続けてみよう」と思えたなら、それもまた尊重すべき意思です。
将棋を辞める“時期”の見極めと他への活かし方
将棋に一区切りをつけようと考えたとき、多くの人が迷うのが「辞めるタイミング(時期)」です。早すぎても後悔しそうだし、続けすぎても苦しくなる。そんな気持ちの揺れにどう折り合いをつけるかが大切です。
このセクションでは、「辞める時期をどう見極めるか」と「将棋で得た力を今後どう活かすか」について深掘りしていきます。
こんなときが“辞め時”のサイン
将棋を辞める時期には個人差がありますが、以下のようなサインが複数重なっている場合、自然なタイミングかもしれません。
| 状況 | 辞め時のサイン |
| 心が動かなくなった | 勝っても負けても何も感じない |
| 続ける意義を感じない | 強くなっても嬉しくない |
| 負担が大きすぎる | 将棋に割く時間・お金・精神が生活に影響している |
| 別の夢ができた | 他に集中したいことができた |
これらのサインは、「あなたが成長した証」とも捉えられます。将棋を通じて得られた学びや視点が、新しい世界へ向かう足がかりになるのです。
将棋の経験は人生のあらゆる場面で活きる
将棋を辞めるとしても、これまで費やした時間や努力が無駄になることはありません。将棋で培ったスキルは、実生活や他の分野で活かすことができます。
| 将棋で得た力 | 活かせる場面 |
| 論理的思考 | 仕事の分析・問題解決能力 |
| 集中力・継続力 | 資格勉強、スポーツ、語学習得など |
| 忍耐と冷静さ | 人間関係や困難への対応力 |
| 読みの力 | ビジネス交渉・市場の先読みなど |
特に、ビジネスパーソンや学生にとっては、将棋の思考法を活かすことで他分野でも成果を出しやすくなります。
“辞める”は終わりではなく“形を変える”こともできる
辞める=完全に将棋と縁を切る、というわけではありません。以下のように、形を変えて将棋と関わり続ける道もあります。
- プレイヤーから観戦者(観る将)へ
- 実戦から詰将棋や棋書の読書へ
- オンライン対局から地元の将棋サークルへ
- ゲーム感覚で将棋アプリを楽しむだけにする
人生のステージによって、将棋との距離感も変わって当然です。大切なのは、自分にとって心地よい関わり方を見つけることです。
いつでも戻れる場所としての“将棋”
将棋の魅力のひとつに、「何歳になっても、どんなレベルでも楽しめる」という普遍性があります。一度離れても、また指したくなったときにすぐに戻ってこられる世界です。
将棋界では、10年・20年のブランクを経て復帰する人も珍しくありません。むしろ、再開後に以前より深く楽しめるケースも多く、将棋は生涯続けられる趣味の代表格とも言えるでしょう。
まとめ:辞める時期を見極めたら“次”へ進もう
将棋を辞める時期は、「将棋があなたに何を与えてくれたか」「これから何をしたいか」を見つめる絶好の機会です。無理に続けず、自分の意思で選択することこそが、人生の質を高める第一歩になります。
そして、たとえ辞めたとしても、あなたの中に将棋の知識や経験は確かに残っています。それは今後の人生において、知的な武器として、思考の軸として、きっと役立ってくれるはずです。
まとめ|将棋で勝てないときの心構えと向き合い方
将棋は、知性・集中力・持久力が問われる奥深い競技です。勝てない時期やイライラする局面、つまらないと感じる瞬間があるのは当然のことです。しかし、それをどう受け止め、どう乗り越えるかが、将棋の本当の魅力を知る鍵となります。
以下に本記事の要点をまとめます
- 勝てないと感じたら、まずは基本の見直し(駒の損得、王の安全、定跡の理解)
- つまらないときは、指し方や戦法、対局環境を変えてみる
- 将棋がイライラの原因になるなら、少し距離を置くことも大事
- 辞めたいと思う自分を責めず、感情の整理と将来の意志で判断を
- 辞める時期は、生活や気持ちへの影響度から見極める
- 将棋で得た力は、人生や他の分野でも活かせる
- 将棋はいつでも戻れる場所。「辞める」ことは終わりではない
将棋との関係性は、人によって違います。大切なのは、「自分がどうしたいか」を正直に見つめて選ぶことです。将棋の世界は広く深く、あなたの人生に寄り添う形で、何度でも関わり直すことができます。
【2025年最新】かわいい美人女流棋士ランキング|将棋界の魅力を徹底解説