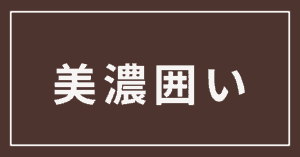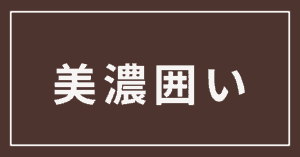「穴熊(あなぐま)」という囲いを聞いたことはあるでしょうか?
将棋界では「最強の囲い」として知られ、初心者からプロ棋士に至るまで幅広く使われている定番の囲いです。その硬さは圧倒的で、一度完成するとそう簡単には崩れません。
しかし一方で、「つまらない戦法」「終盤が単調になりがち」といった評価もあり、評価は分かれるところ。現代将棋ではAI研究も進み、「穴熊の限界」や「崩し方」についての研究も盛んに行われています。
本記事では、穴熊囲いの基本から最新定跡、崩し方や対策、そして初心者が取り入れる際のポイントまでを、わかりやすく丁寧に解説していきます。
定跡を学び、囲いを正しく理解することで、将棋の実力もぐんとアップするでしょう。


◆アプリダウンロード数4,000万突破!


将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、
【 ABEMA
プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。
>> 将棋見るならABEMA
H2:穴熊とは?|最強囲いと呼ばれる理由
初心者にもわかりやすく、「穴熊」とは何か、その魅力と評価の背景を紹介していきます。
穴熊囲いの意味と語源|なぜ“熊”なのか?
「穴熊(あなぐま)」という名前は、動物のアナグマに由来しています。アナグマは自ら掘った深い巣穴にこもって身を守る習性があることから、「深く守って動かない囲い」の代名詞として名づけられました。
将棋における穴熊囲いも、玉将を右端(もしくは左端)に深く囲い、金・銀・香・桂といった駒でカチカチに守ります。その硬さは将棋界随一といわれ、特に「囲いの完成形」に到達した際の耐久性が魅力です。
穴熊の特徴|最強とされる理由とその堅さ
穴熊が「最強」とされるのは、以下のような点にあります。
- 玉が隅に追いやられており、詰まされにくい構造
- 金銀3枚による鉄壁の守り
- 相手の攻撃をしのいだ後、カウンターを狙いやすい
特に持久戦や相手の攻撃を誘って受けるスタイルにおいては、穴熊は絶大な力を発揮します。一方で囲いに時間がかかるため、速攻に弱い一面もあります。
居飛車穴熊と振り飛車穴熊の違いとは?
穴熊囲いには大きく分けて2種類があります。
| タイプ | 主な戦型 | 特徴 |
| 居飛車穴熊 | 対振り飛車に強い | 玉を右奥に囲う。手数は多いが堅い |
| 振り飛車穴熊 | 対居飛車に強い | 左奥に玉を囲う。美濃囲いから発展 |
- 居飛車穴熊:主に四間飛車や三間飛車といった振り飛車戦に対して使われます。右辺に玉を深く囲い、相手の端攻めを誘って受けるスタイルが特徴です。
- 振り飛車穴熊:主に角道を止める戦法で用いられ、従来の美濃囲いから発展して玉をさらに深く囲む形です。
どちらもじっくり戦うのが得意なプレイヤーに向いている囲いといえるでしょう。
穴熊の基本の組み方と定跡手順
このセクションでは、穴熊の具体的な組み方や、将棋の定跡としての手順を解説します。初心者にもわかりやすく、代表的な形を図解とともに紹介していきます。
居飛車穴熊の組み方|定跡通りの構築手順
居飛車穴熊は、主に相手が振り飛車を選んできた場合に構築する囲いです。以下に、組み方の基本的な流れを示します。
▼基本手順(先手の場合)
| 手順 | 指し手 | 解説 |
| 1 | ▲7六歩 | 角道を開ける初手 |
| 2 | ▲6八銀 | 銀を上げて囲いの準備 |
| 3 | ▲7七銀 | 銀で角頭を守る形 |
| 4 | ▲5八金右 | 金を中央に寄せ、バランスを取る |
| 5 | ▲6八玉 → ▲7八玉 → ▲8八玉 | 玉を右奥に移動していく |
| 6 | ▲8八銀 → ▲9八香 → ▲9九玉 | 最終的に玉は9九に収まる |
この一連の流れで玉を最も安全な場所に配置し、金銀が上下から玉をカバーする構えが完成します。
▼ポイント
- 玉を右隅まで逃すため、玉の早逃げが重要です。
- 銀が壁になりすぎると攻撃に使えないため、配置には注意。
- 敵の端攻めに備えて、香車や歩の位置も整えておくと強固になります。
振り飛車穴熊の組み方|美濃囲いからの移行パターン
振り飛車穴熊は、美濃囲いからの派生形であり、以下のようにして進化します。
▼基本構築ステップ(後手四間飛車の場合)
| 手順 | 指し手 | 解説 |
| 1 | △3四歩 | 振り飛車の基本形 |
| 2 | △4二銀 → △3三銀 | 美濃囲いの初期形 |
| 3 | △3二金 → △4一金 | 金を中央に寄せる |
| 4 | △5二金左 → △6一玉 → △7一玉 → △8二玉 | 玉を左奥に誘導 |
| 5 | △8一銀 → △9二香 → △9一玉 | 玉が9二に到達で穴熊完成 |
▼ポイント
- 美濃囲いから穴熊に移行する場合、玉の移動タイミングが重要です。
- 相手の動きを見ながら、攻めが来ないうちに組み上げるのが理想。
- 香車と銀の連携で端攻めにも強くなる点が大きな魅力。
穴熊の定跡手順と最新研究のトレンド
近年、AI将棋やプロ棋士の研究により、穴熊の定跡もアップデートされています。特に注目されているのは以下のようなテーマです。
最新定跡の例:
- 対四間飛車における速攻組み上げ型
→ 相手の構築を待たずに先に完成させて圧力をかける - 端歩の突き捨てによる攻守のバランス調整
→ 端攻めを受けつつ、自分からの反撃も視野に入れる構成 - AI研究から生まれた金の柔軟配置
→ 従来の金銀3枚型をアレンジし、カウンター重視の構えに
AIの台頭により、定跡は常に進化しており、「一手の遅れ」が致命的になるケースもあるため、最新の形を知っておくことが非常に重要です。
穴熊のメリットとデメリット|評価の分かれる理由とは?
ここでは、穴熊囲いが持つ強みと弱みを整理し、なぜ評価が分かれるのかを解説します。他の囲いとの比較を通じて、あなたの棋風に合うかどうかを見極める材料にしてください。
堅さ・柔軟性・攻守のバランスを評価
穴熊囲い最大の魅力は「鉄壁の堅さ」です。玉が盤の隅に位置し、金銀でガッチリと固められた形は、他の囲いではなかなか見られない守備力を誇ります。
しかしその反面、柔軟性には欠けるのが事実です。囲いを完成させるまでに時間がかかり、途中で攻め込まれると対応が難しい場面も出てきます。
穴熊の特徴評価(5段階)
| 評価項目 | 穴熊囲い | 解説 |
| 堅さ | ★★★★★ | 最強クラスの守備力 |
| 柔軟性 | ★★☆☆☆ | 組み替えが難しく一度組んだら戻せない |
| 攻撃力 | ★★★☆☆ | 反撃には強いが速攻には不向き |
| 組みやすさ | ★★☆☆☆ | 手数がかかり、リスクもある |
| バランス | ★★★☆☆ | 安定型だが局面によって不利になる場合あり |
穴熊は、「受けてから反撃する」スタイルに合った囲いです。攻め合いを好む人には向かないこともあります。
他の囲い(矢倉・美濃・船囲い)との比較
他の代表的な囲いと比べてみましょう。目的や戦型によって使い分けることで、戦略の幅が広がります。
囲い別比較表
| 囲い名 | 強み | 弱み | 向いている戦法 |
| 穴熊 | 超堅固、防御力最強 | 組むまでが遅く、端攻めに弱い場合も | 対振り飛車、持久戦 |
| 美濃囲い | 柔軟、早く組める | 耐久力がやや低め | 振り飛車、急戦 |
| 矢倉 | 中央を守る好配置 | AIで対策が進んだ | 居飛車同士の戦い |
| 船囲い | コンパクトで素早い | 脆さが目立つ | 急戦、奇襲型 |
このように、穴熊は他と比べても守備力は群を抜いています。ただし、形がバレやすく、戦略が読まれやすいという欠点もあります。
穴熊が向いている棋風とは?
どんな囲いも「棋風に合っているか」が最も大事です。穴熊は以下のようなプレイヤーにおすすめです。
向いている人の特徴
- 相手の攻めを受け切る展開が得意
- 守備に自信がある
- じっくり戦って終盤勝負に持ち込むタイプ
- 攻め急がず冷静に構えられる人
逆に、序盤から積極的に攻めたい、テンポの良い将棋を指したい人には不向きかもしれません。穴熊は堅実さと我慢強さが試される囲いです。
穴熊への対策と崩し方|端攻めは本当に有効?
ここでは、強固な守備力を誇る穴熊囲いにどう立ち向かうかを解説します。端攻めをはじめとする具体的な攻め筋と、実戦での注意点を学ぶことで、勝率アップにつながります。
基本は端攻め|定番の攻略ルートを理解しよう
穴熊囲いに対して最もよく使われる崩し方が「端攻め」です。特に9筋(後手なら1筋)からの圧力は有効とされ、端歩の突き捨て・香車の前進・角の活用が組み合わされることが多いです。
端攻めの基本手順は次の通り:
- 端歩を突き越す(9六歩~9五歩)
- 香を上がる(9七香)
- 桂馬で飛び越える(8五桂など)
- 玉の逃げ道を封鎖しつつ、角や飛車で圧力をかける
ただし、相手が「端玉穴熊(端に逃げる穴熊)」の場合は逆効果になる可能性もあるため注意が必要です。
中央突破で一気に攻める方法
端攻めが通じにくい形や、序盤から相手の玉が端に寄っていない場合は、中央突破による攻めが有効です。特に角交換からの**▲5五歩や▲6五歩(後手なら△5五歩など)**を起点に、銀や飛車を絡めた攻撃が機能します。
中央突破のメリット:
- 相手の囲いに手をつける前に主導権を握れる
- 守備駒を中央に引き出させ、穴熊の堅さを崩すきっかけになる
- 端攻めと見せかけたフェイントとしても使える
相手の対応を見ながら、攻める筋を切り替えられるようにしましょう。
実戦での崩し方の注意点と読みの深さ
穴熊を崩す際に最も大切なのは、**「玉を詰ますのに何手かかるか」**を常に意識することです。堅さゆえに1手でも攻めを間違えると逆襲を受けやすくなります。
攻めの基本ポイント:
- 香・桂・歩をフル活用して玉の逃げ道を封鎖
- 飛車・角の成り込みを焦らず狙う
- 序盤から持ち駒を蓄える意識を持つ(端攻めに歩3枚以上は必要)
また、囲いの外堀を壊しただけで満足せず、必ず詰めまでの構想を持つことが重要です。逆にカウンターを受けてしまうと、堅さを活かした相手の攻めが止まらなくなります。
穴熊囲いは初心者にもおすすめ?|選び方と注意点
ここでは、将棋を始めたばかりの初心者や初級者にとって、穴熊囲いがどのような選択肢になるかを解説します。囲いの中でも特に評価の高い穴熊ですが、使いこなすにはポイントがあります。
初心者が使う際のポイントと注意点
穴熊囲いは「最強の囲い」として知られていますが、初心者が使う場合には慎重な構築とタイミングが重要です。囲いを完成させるまでに多くの手数を要するため、相手の攻めが早いと間に合わずに潰されることがあります。
初心者が意識すべきポイント:
- 穴熊の完成を焦らない(玉を囲う途中で攻められることも)
- 相手の攻め筋を意識しながら組み上げる
- 相手が速攻型の場合は、急戦への切り替えも視野に
また、角道が開いていない構えで穴熊を目指すと、飛車先交換などで不利になりやすいため、角の位置や守備駒の配置にも注意が必要です。
組みやすさと学習難易度を他囲いと比較
囲いごとの「組みやすさ」と「堅さ」のバランスを理解することは、戦型選びにおいて重要です。以下の表に代表的な囲いとの比較をまとめました。
| 囲いの種類 | 組みやすさ | 堅さ | 初心者向き度 | コメント |
| 美濃囲い | ◎ | △ | ◎ | 振り飛車での基本囲い。手数少なめ。 |
| 矢倉囲い | ○ | ○ | ○ | 居飛車の基本。バランスが良い。 |
| 穴熊囲い | △ | ◎ | △ | 最強の囲いだが、手数が多く難易度高め |
| 舟囲い | ◎ | △ | ◎ | 急戦用。速攻狙いの時に有効。 |
穴熊は堅さは随一ですが、完成に時間がかかるため、状況判断が重要です。まずは美濃囲いや矢倉で囲いの基本を学び、その後に穴熊に挑戦するのも一つの方法です。
覚えておきたい基本パターンと応用形
穴熊囲いを使いこなすためには、いくつかのパターンを暗記しておくと実戦での組み立てがスムーズになります。
■ 代表的な基本形(居飛車穴熊)
- 玉を右隅(1一または9九)に移動
- 金銀を囲いに寄せる(▲8八銀、▲7八金、▲6八金 など)
- 香車を上がって(▲9八香)、角道や飛車道を確保
■ 応用形の例
- 左美濃→穴熊に移行するパターン
- 角交換型での穴熊構築
- 中住まい風から穴熊に組み替える柔軟性
局面や戦型に応じて、「穴熊一本」ではなく他の囲いと併用する柔軟性も覚えておきましょう。これにより対応力が増し、勝率アップにもつながります。
穴熊を学べるおすすめの本・動画まとめ|初心者〜上級者別
ここでは、穴熊囲いの組み方や対策、実戦での応用を深く学びたい人に向けて、書籍・動画・YouTube講座などの学習リソースを紹介します。初心者から上級者まで幅広く対応しています。
初心者におすすめの入門書と基本本
初心者がまず読むべきは、囲いの種類や狙いを分かりやすく解説している入門書です。特に図解が多いものや、振り飛車・居飛車の基本とともに穴熊を扱っている本がおすすめです。
▼ 初心者に人気の穴熊関連書籍
| 書籍タイトル | 著者 | 特徴 |
| 『駒落ち定跡と囲いの基本』 | 勝又清和 | 囲いの全体像が分かりやすい構成。 |
| 『将棋・穴熊戦法徹底ガイド』 | 佐藤康光 | 穴熊に特化した解説で丁寧な内容。 |
| 『将棋の基本 囲いと戦法』 | 屋敷伸之 | 入門者向けの囲いと戦法を網羅。 |
これらの本は図と手順の説明が豊富で、初心者でも直感的に理解できる構成になっています。
中級者以上におすすめの定跡本・実戦解説本
中級〜上級者になると、実戦での使いどころや組み替えの判断、相手の囲いに対する対応策も学ぶ必要があります。
▼ レベルアップに効果的な本
- 『最新穴熊戦法大全』(著:渡辺明)
- 『矢倉・穴熊・美濃囲い徹底比較』(著:久保利明)
- 『急戦穴熊で勝つ!』(著:斎藤慎太郎)
これらは定跡を深く掘り下げた解説や、プロの実戦譜を交えた分析があり、理解を一段階深めるのに最適です。
YouTubeや将棋講座で穴熊を学ぶなら?
最近では、YouTubeでもプロ棋士や人気YouTuberが穴熊戦法を丁寧に解説しています。音声と映像で学べるため、本よりも理解が進む人も多いです。
▼ おすすめYouTubeチャンネル
| チャンネル名 | 内容 |
| 将棋放浪記(プロ棋士藤森哲也五段) | 居飛車・振り飛車双方の穴熊解説が豊富 |
| アゲアゲ将棋実況 | 実戦での穴熊の使い方を実況形式で解説 |
| 羽生善治チャンネル | 穴熊を含む囲い全般についてプロ目線で学べる |
また、将棋連盟公式の講座動画や、将棋ウォーズでのプロ棋士の実戦アーカイブなども参考になります。
まとめ|穴熊を極めれば将棋の実力がワンランクアップ!
最後に、穴熊囲いの魅力や将棋上達への影響をまとめて振り返ります。ここで紹介した内容を繰り返し復習することで、囲いの理解だけでなく将棋全体の実力アップが期待できます。
最強の囲いとしての安心感と勝率アップ
穴熊囲いはその絶対的な堅さと守備力によって、初心者からプロまで幅広く使われる定番囲いです。特に居飛車穴熊は、完成すれば終盤まで持ちこたえる力があり、勝率向上に大きく貢献します。
戦型に応じた柔軟な囲い選びの重要性
穴熊が強力とはいえ、すべての局面で万能というわけではありません。相手の戦法や展開の流れによって、矢倉や美濃囲いなどへの切り替えも重要です。囲いを学ぶことで、柔軟な戦術の選択肢が広がります。
他の囲いとの比較記事もぜひチェック!
本ブログでは他にも、「矢倉囲い」「美濃囲い」「左美濃」「高美濃」「ミレニアム囲い」などの解説記事を公開しています。囲いの比較や選び方の参考になるので、ぜひあわせてご覧ください。
将棋の矢倉囲い完全ガイド|組み方・戦法・攻め方・崩し方まで徹底解説
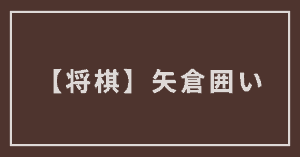
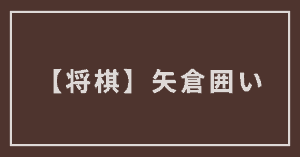
将棋の美濃囲いとは?種類・作り方・崩し方・銀冠との違いまで完全ガイド