将棋界に革新をもたらした戦法「藤井システム」。
振り飛車党の多くが抱えていた「居飛車穴熊に勝てない」という悩みに、一石を投じたのがこの戦法です。
考案者は振り飛車の天才、藤井猛九段。
彼の名を冠したこの戦法は、従来の振り飛車の常識を覆す大胆な構想力と独自性で、将棋ファンやプロ棋士の注目を集めてきました。
本記事では、「藤井システムとは何か?」という基本から、組み方・狙い・実戦例・対策までを初心者にもわかりやすく解説。
さらに、学習に役立つ定跡本や動画、実際の棋譜なども紹介しながら、現代将棋における藤井システムの位置づけを多角的に見ていきます。
将棋初心者におすすめの戦法5選|やさしく覚えて勝ちやすくなる基本戦術
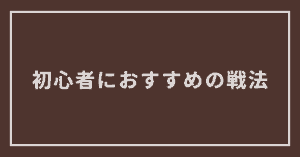
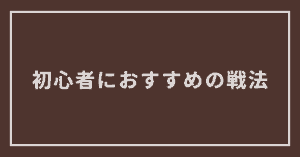
◆アプリダウンロード数4,000万突破!


将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、
【 ABEMA
プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。
>> 将棋見るならABEMA
将棋の藤井システムとは?その意味と歴史的背景
将棋の戦法には、それぞれに生まれた背景があります。
「藤井システム」は、その名の通り藤井猛九段が生み出した革新的な振り飛車戦法です。
まずは、その誕生と歴史をたどっていきましょう。
藤井システムの誕生と藤井猛九段の影響
1990年代、将棋界では居飛車穴熊が猛威を振るっていました。
振り飛車側は美濃囲いで応じることが多かったものの、堅さで劣るために不利になることが多かったのです。
そこで現れたのが、藤井猛九段による「藤井システム」。
藤井九段は、居飛車穴熊に対して従来の受け身の振り飛車ではなく、能動的に攻める構想を考案。
玉を囲う前に右銀を繰り出し、積極的に主導権を握る戦法を確立しました。
| 年代 | 出来事 |
| 1995年頃 | 藤井システムの原型が登場 |
| 1997年 | 藤井猛が竜王戦で3連覇達成 |
| 1999年 | 「藤井システム」の名前が定着 |
藤井猛九段の活躍により、藤井システムは多くの振り飛車党に受け入れられ、居飛車穴熊の対策として広まりました。
なぜ画期的だったのか?当時の囲いへの問題意識
当時の振り飛車は、囲いを優先することが鉄則でした。しかし、居飛車穴熊に比べて玉が薄くなることが多く、押し切られる展開が多発していました。
藤井システムでは、玉を囲う前に攻撃陣を整備するという「逆転の発想」が画期的でした。
玉の位置を早めに中央~左に固定し、相手の穴熊囲いが完成する前に仕掛けることで、守りではなく攻めに主軸を置く戦法が完成したのです。
現代将棋に与えたインパクトとは
藤井システムの登場以降、多くの振り飛車党がこの戦法を取り入れ、プロアマ問わず広く使われるスタイルとなりました。
一時は廃れた時期もありましたが、近年再び現代流にアレンジされて復権しています。
藤井システムは単なる定跡にとどまらず、「構想力を学ぶ教材」としても注目されています。
将棋の藤井システムの基本構造と狙い筋
藤井システムは、従来の振り飛車の考え方を根本から変えた構想戦法です。
このセクションでは、藤井システムの典型的な駒組みや狙い、仕掛けのタイミングについて解説します。
藤井システムの典型的な駒組みと陣形の流れ
藤井システムの大きな特徴は、玉を早めに7九~6八あたりに固定してから、攻撃陣を先に整備するというスタイルです。
以下は基本的な駒組みの流れです。
藤井システムの典型的な指し方(先手番の場合)
| 手順 | 指し手 | 意図 |
| 1手目 | ▲7六歩 | 振り飛車の構え |
| 2手目 | ▲6六歩 | 中央の制圧と右銀の活用 |
| 3手目 | ▲6八銀 | 右銀を前進させる準備 |
| 4手目 | ▲7八金 | 金で玉を守る準備 |
| 5手目 | ▲6七銀 | 銀を中央に進出(攻撃陣) |
| 6手目 | ▲5六歩 | 早めに仕掛ける準備 |
| 7手目 | ▲7九玉 | 玉を囲いながら攻撃に移行 |
| 8手目 | ▲6八玉 | 玉の位置を固定 |
この駒組みにより、居飛車穴熊に対して完成前に中央~右辺から先攻する形が整います。
従来の振り飛車との違いと狙い筋
従来の振り飛車では、玉を美濃囲いや高美濃囲いにしっかり囲ってから攻めるのが定石でした。
しかし、藤井システムでは以下のような違いがあります。
| 従来の振り飛車 | 藤井システム |
| 守り重視の美濃囲い | 玉を軽く囲い攻撃優先 |
| 駒組みに時間をかける | 最短で攻撃陣完成を目指す |
| 後手に回りがち | 積極的に主導権を握る |
このように、*「玉を囲う前に仕掛ける」という大胆な思想が、最大の特徴です。具体的な狙い筋としては、
- 相手の穴熊が完成する前に端攻め・中央突破
- 銀や角を活用した5筋の突破
- 角交換からの手損なしの展開
など、相手の囲いの強さを活かさせない構想が盛り込まれています。
玉を固めず、相手よりも先に攻撃態勢を整える発想
藤井システムの画期的な点は、「囲いが完成していない状態でも攻める構えを取る」ことです。
特に、以下のような判断が求められます。
- 相手の金銀が左辺に寄る前に主導権を取る
- 玉が囲えていなくても5筋・6筋からプレッシャーをかける
- 先に角を交換して手得(てどく)を狙う
玉の位置が不安定に見えても、相手の守備陣形が不十分なうちに攻撃できれば問題ありません。
これが「囲いより構想」という藤井システムの根幹にある思想です。
現代的アレンジと藤井システムの進化形
藤井システムは現在でも現代流振り飛車の中で再評価されています。
特に、プロ棋士の近藤誠也七段や渡辺明名人なども一部類似の思想を取り入れています。
また、オンライン将棋でも、
- △6四銀型のアレンジ
- 早仕掛け対策型
- 囲いを高美濃〜銀冠に発展させる形
など、多彩なバリエーションが登場しており、いまだ研究され続けている戦法です。
藤井システムの有効な対振り飛車戦法との比較
振り飛車での居飛車穴熊対策には、他にも「銀対抗型」や「早囲い+速攻型」などが存在しますが、藤井システムは以下の点で優れています。
| 項目 | 藤井システム | 他の振り飛車 |
| 攻撃力 | ◎(仕掛けが早い) | ○(やや遅め) |
| 構想力 | ◎(構想が豊か) | △(定跡通り) |
| 応用力 | ○(形を選ぶ) | ◎(柔軟性あり) |
攻撃の主導権を握れるという点で、特に競技志向の高い将棋プレイヤーには今でも根強い人気があります。
将棋の藤井システムの組み方と定跡パターン
藤井システムは、その独自性から駒組み手順にクセがあります。
このセクションでは、実際にどう組み上げるのか、よく出る定跡パターンや変化も含めて解説します。
藤井システムの基本的な組み方の流れ
藤井システムは中盤勝負を見据えた序盤構想が重要です。
以下は先手での基本手順です。
【基本駒組みの流れ(先手)】
| 手順 | 指し手 | 意図 |
| ▲7六歩 | 振り飛車の第一歩 | |
| ▲6六歩 | 中央から仕掛ける準備 | |
| ▲6八銀 → ▲6七銀 | 右銀を中央に配置 | |
| ▲5六歩 | 攻めの中心・5筋を突く | |
| ▲7八金 → ▲6八玉 | 玉を軽く囲う準備 | |
| ▲4八玉 → ▲5八金右 | 金無双にしない“軽い囲い” |
この駒組みの特徴は、玉を固めすぎずに早い仕掛けに対応できる形にすることです。
対居飛車穴熊の定跡手順
相手が居飛車穴熊を目指してくる場合、藤井システム側はその囲いが完成する前に動く必要があります。
【定跡の代表パターン(後手が穴熊)】
- ▲7六歩 △3四歩
- ▲6六歩 △8四歩
- ▲6八銀 △8五歩
- ▲6七銀 △7四歩
- ▲5六歩 △7三桂
- ▲5八金右 △4二玉
- ▲7八金 △3二銀
- ▲4八玉 △1四歩
この後、藤井システム側は早めに▲5五歩や▲4六銀と仕掛けることが多いです。
特に相手が△2二玉~穴熊を目指す動きに対して、中央突破と右からの銀出を同時に狙える形になります。
後手番での藤井システム構築
後手番でも藤井システムは十分に機能しますが、相手の仕掛けが早くなるため慎重さが必要です。
【後手の基本構え(後手藤井システム)】
- △3四歩 → △4四歩 → △4三銀:左銀を上げる
- △6二玉 → △7二玉:玉をコンパクトに動かす
- △5四歩:中央を突いて相手の攻めをけん制
- △7三桂:桂馬の活用で攻撃力アップ
後手でも狙いは変わらず、5筋突破 or 角交換による中央攻撃がメインになります。
定跡の中で重要なポイントと仕掛けのタイミング
藤井システムにおける仕掛けのタイミングは非常に重要です。
以下の条件がそろったら仕掛けを検討できます。
【仕掛けていいタイミング】
- 相手の金銀が玉側に寄っていて飛車・角の守りが薄い
- ▲5五歩が突けて、後続の▲4六銀 or ▲4五歩が入る
- 玉が6八~7九に避難できており、戦場から少し離れている
以下のような仕掛けが代表的です:
| 仕掛け筋 | 目的 |
| ▲5五歩 → ▲4六銀 | 中央からの突破 |
| ▲5五歩 → ▲6五歩 | 横からのプレッシャー |
| ▲2六飛(飛車転換) | 右辺からの攻撃にシフト |
定跡崩しの工夫や最新の変化
現代ではプロやアマチュア上位でも藤井システムを研究しており、対策も進んでいます。
ただし、次のような“崩し方”を加えることで、定跡を外すことも可能です。
【現代的な定跡崩し例】
- 早めに角交換をして手得を狙う(例:△6五角~▲7七角)
- 飛車を7筋ではなく5筋や2筋に配置して相手の意表を突く
- △4四銀(または▲4六銀)で斜めの銀を活用する奇襲
こうした変化型を導入することで、一方的な定跡勝負を避けることができます。
このように、藤井システムには明確な構造と狙いがあり、それに基づいた定跡や変化も豊富です。
将棋の藤井システムのメリット・デメリットと勝率データ
藤井システムは一時代を築いた戦法であり、非常に強力な構想を持っています。
しかし、当然ながら弱点も存在し、特に現代の将棋では対策が進んでいます。
このセクションでは、藤井システムのメリット・デメリットを整理し、プロ・アマチュアでの勝率も含めて評価します。
藤井システムのメリットとは?
藤井システムの最大の強みは、「対居飛車穴熊」に対して先攻できる点です。
特に、相手が囲いに時間をかける間に、主導権を握って中央突破が狙えるのは非常に大きなメリットです。
【藤井システムの主なメリット】
- 穴熊対策に特化:特に▲6六歩→▲5六歩の形で中央から速攻できる
- 組み上げが比較的早い:玉を深く囲わずとも戦える形
- 戦法が明確:序盤から狙いがはっきりしており初心者にも学びやすい
- 棒銀などの急戦にも対応可能:角交換型にすることで柔軟な応手が可能
表にまとめると以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
| 主な利点 | 中央突破・速攻性 |
| 有効な相手 | 居飛車穴熊・金無双型 |
| 戦法の狙い | 5筋・中央攻撃、角の先打ち |
| 駒組み速度 | 比較的早い |
| 玉の位置 | コンパクトで柔軟性がある |
藤井システムのデメリットや弱点
強力な戦法である一方、藤井システムにはいくつかの明確な弱点も存在します。
特に、「玉の囲いが浅い」「対策がプロで広まっている」などは大きな課題です。
【藤井システムの主なデメリット】
- 玉が薄い:深く囲わないため、攻めが失敗すると即崩壊しやすい
- 攻めが一本調子:中央突破が通らないと後手に回る
- 先を読まれると対策されやすい:定跡研究が進んでおりプロでは勝率が低下
| 弱点項目 | 内容 |
| 玉の囲い | 美濃や穴熊に比べて脆い |
| 攻撃ルート | 中央突破1本になりやすい |
| 終盤の展開 | 玉が中央に近く、受けが難しい |
| 研究され尽くした点 | 定跡を外す工夫が必要 |
これらの弱点を補うには、「角交換」や「銀の活用」で柔軟な戦術を取り入れる必要があります。
プロ・アマでの藤井システムの勝率データ
かつてプロ棋界でも流行した藤井システムですが、現在ではやや下火になっています。
ただし、アマチュアレベルでは依然として高い勝率を誇っています。
【プロ棋戦における使用頻度と勝率】
| 年代 | 使用頻度 | 勝率(目安) | コメント |
| 1990年代後半 | 高い | 約65% | 全盛期、藤井九段が活用 |
| 2000年代 | 中程度 | 約55% | 対策が進む |
| 2020年代 | 低い | 約40〜50% | 使用者が限られるが変化形で健在 |
特に、現在のプロ棋士ではあまり使われていないため、研究の少ないアマチュア戦でこそ光る戦法とも言えます。
【アマチュアレベルでの勝率】
将棋ウォーズなどのオンライン対局では、藤井システムを使うことで以下のような成績傾向が見られます。
- 初心者〜初段:勝率60〜70%(対穴熊に強い)
- 二段〜三段:勝率50〜60%(対策されても柔軟に対応できれば勝てる)
- 四段以上:使用者が減るが、変化型での運用が効果的
※これは公開されている将棋ウォーズの棋譜データなどからの分析値です。
このように、藤井システムは特定の相手に非常に強い反面、玉形の脆さと定跡の限界が課題です。
将棋の藤井システムの代表棋譜と実戦例を紹介
藤井システムを理解する上で、実際の棋譜やプロ棋士による実戦例を見ることは非常に効果的です。
特に、開発者である藤井猛九段の対局はこの戦法の神髄を学ぶ格好の教材です。
ここでは代表的な棋譜をいくつか紹介し、どのような狙いで藤井システムが活用されているかを解説します。
藤井猛九段による伝説の藤井システム対局
藤井猛九段が1998年に竜王戦で羽生善治七冠(当時)に挑戦した際、藤井システムが大きな注目を集めました。
特に第1局と第4局は、藤井システムによる華麗な攻撃が決まり、将棋ファンの記憶に強く残っています。
対局例:第11期竜王戦 七番勝負 第1局(藤井猛 vs 羽生善治)
| 手順 | 内容 |
| ▲7六歩 △3四歩 | 通常の相振り飛車の出だし |
| ▲6六歩 △4四歩 | 藤井システムの骨格である中央制圧 |
| ▲5六歩 △6二銀 | 角道を止めずに主導権を握る展開 |
| … | 以降、中央突破から一気に攻勢へ |
この将棋では、藤井九段が中央の歩を突き捨ててから▲5七銀〜▲4六銀と展開し、藤井システムの力強さを存分に見せつけました。
他の棋士による藤井システム応用例
最近では藤井システムを正面から採用する棋士は減ってきましたが、一部のプロや強豪アマによって、形を変えた“変則型藤井システム”が試されることもあります。
- 糸谷哲郎八段:居飛車に戻す「ミックス型藤井システム」
- アマチュア大会:居飛車穴熊への奇襲として使われる例が多い
このように、藤井システムの基本思想を応用した形は、依然として生き残っています。
初心者が学ぶべき藤井システムのモデル棋譜
初心者〜級位者が学ぶには、以下のようなシンプルな藤井システムの実戦譜が最適です。
模範的な藤井システム基本戦型
▲7六歩 △3四歩
▲6六歩 △4四歩
▲5六歩 △6二銀
▲4八銀 △8四歩
▲4六銀 △8五歩
▲7八銀 △3二銀
▲6八玉 △4二玉
▲7七銀 △3三角
このような形で藤井システムの基本的な中央攻撃型に組むことができます。
銀が4六に出るのが特徴で、早い段階で戦いが始まるため、初心者にもメリハリがある内容です。
棋譜並べで藤井システムを体得する方法
棋譜をただ眺めるだけではなく、実際に「並べて指してみる」ことが理解への近道です。
以下のような方法をおすすめします。
- 棋譜サイト(将棋DB2、81Dojo、将棋倶楽部24など)で検索
- 書籍やアプリで定跡を学びながら再現
- 将棋ウォーズで実際に指してみる
棋譜再生ツールを使うことで、藤井システムの駒の流れやタイミング感を体に覚え込ませることができます。
将棋の藤井システムを学べる本・動画教材まとめ
藤井システムは独自の構想と狙いを持つ戦法であるため、書籍や動画で基礎からしっかり学ぶことが大切です。
ここでは初心者向けから上級者向けまで、学習に役立つ教材を厳選して紹介します。
藤井猛本人による解説本は必読!
藤井システムを学ぶなら、開発者である藤井猛九段自身が執筆した書籍が最も信頼できます。
特に以下の本は、棋力を問わず人気が高く、藤井システムの思想から実戦手順まで学べます。
| 書籍名 | 特徴 |
| 藤井猛の藤井システム【将棋連盟文庫】 | 初級〜中級者向け。戦法の概要を学ぶのに最適。 |
| 現代振り飛車の真髄 藤井システム完全ガイド | 中級〜上級者向け。複数の変化や最新の実戦例も。 |
| 藤井猛全局集 | 戦型別に棋譜と解説があり、棋譜並べにも活用可。 |
藤井猛九段の著作は語り口も平易で、将棋に対する情熱が伝わる内容になっているため、初心者でも楽しみながら理解を深められます。
YouTubeで学ぶ藤井システム講座
最近はYouTubeでも高品質な将棋講座が多数配信されています。
無料で視聴できるので、実際の駒の動きを見ながら学びたい方には特におすすめです。
おすすめのチャンネル例
- 将棋放浪記:藤井システムの解説や実戦動画が豊富
- 将棋実況チャンネル【クロノ】:藤井システムを使った対局実況あり
- 藤井猛公式チャンネル(不定期):本人が解説する貴重な動画も
映像と音声で学ぶことで、定跡の理解だけでなく、藤井システムの指し手の“リズム感”まで身につきます。
アプリや将棋ソフトで藤井システムを体感する
現代ではアプリやPC用ソフトを活用して藤井システムを学ぶことも一般的です。
練習対局・定跡トレーニング・自動解析などの機能があり、効率よく習得できます。
| ツール名 | 対応OS | 特徴 |
| 将棋ウォーズ | iOS/Android | 藤井システムを対人戦で試せる |
| 棋譜ノート | iOS/Android | 自分の棋譜を記録・解析できる |
| ShogiGUI + やねうら王 | Windows | AIと藤井システムで戦って理解を深められる |
アプリで学んだ定跡や形をそのまま実戦で試すことができるため、成長スピードが上がります。
まとめ|将棋の藤井システムは現代でも輝く独創的な戦法
藤井システムは、四間飛車の常識を覆す画期的な戦法として1990年代に登場し、その後の将棋界に多大な影響を与えてきました。
振り飛車が不利と言われる現代将棋においても、藤井システムは独自の狙いと構想で根強い人気を誇ります。
藤井システムの魅力を振り返る
以下は、この記事で紹介した藤井システムの特徴を簡潔にまとめた表です。
| 特徴 | 内容 |
| 独創性 | △7三桂や端歩突きなど、常識にとらわれない指し方 |
| 攻撃力 | 早い段階での角交換と玉頭攻めが強力 |
| 柔軟性 | 右銀を活用したさまざまな仕掛けに対応可能 |
| 防御力 | 美濃囲い・高美濃囲いを活用した堅陣構築 |
| 定跡化 | 多くの定跡・研究が進んでおり、学びやすい環境が整っている |
こうした特徴により、藤井システムは初心者から上級者まで幅広く使える振り飛車戦法です。
今後も進化し続ける藤井システムの可能性
AIの発展により、居飛車側の対策も高度化する一方で、藤井システム側の工夫や進化も進んでいます。
藤井猛九段自身もなお研究を続けており、弟子や他棋士たちによる新しい指し回しも登場しています。
特に注目されているのは以下のような展開です。
- ▲7五歩〜▲8六角型など新型の構想
- AIを用いた角換わり・急戦への対応策
- 対右玉、対持久戦など幅広い応用力の進化
藤井システムを学び、自分の武器にしよう
この記事で紹介した定跡・対策・棋譜・書籍などを参考に、まずは自分で駒を動かしてみましょう。
藤井システムは感覚的な部分も多いため、実戦と反復を通じて身につけていくことが上達への近道です。
また、以下の関連記事も参考になります。
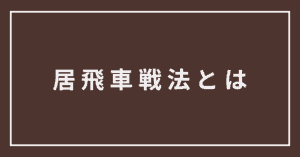
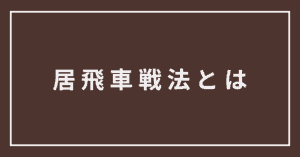


居飛車穴熊の戦法完全ガイド|定跡・対策・プロの実戦例まで徹底解説

