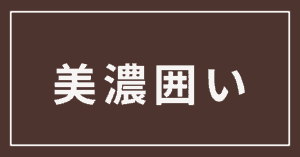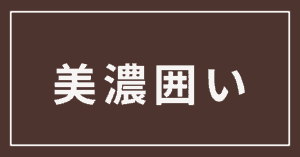将棋の囲いの中でも、堅くて柔軟な構えとして知られるのが「銀冠(ぎんかんむり)」です。
美濃囲いをさらに発展させたこの囲いは、特に振り飛車党の中盤以降の戦いで多く活用されています。
見た目も特徴的で、金銀が高く積み上がった形が“冠”のように見えることからこの名前がつきました。
銀冠囲いは、対急戦や持久戦どちらにも対応できるバランスの取れた囲いですが、組み方には少し注意が必要です。
また、崩されやすいポイントや、戦型によっては不向きなこともあるため、正しい理解が必要です。
この記事では、銀冠囲いの基本から発展形、崩し方や有効な戦法、プロ棋士の活用例などを丁寧に解説します。
初心者でも理解できるように、図解や実戦例にも触れながら紹介していきますので、これから銀冠を取り入れたい方はぜひ最後までご覧ください。


◆アプリダウンロード数4,000万突破!


将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、
【 ABEMA
プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。
>> 将棋見るならABEMA
銀冠囲いとは?|美濃囲いの発展形として誕生


銀冠囲いは、美濃囲いをベースに金銀をさらに高く積み上げた構えです。
防御力を強化しながらも攻撃にも転じやすく、特に振り飛車戦法との相性が良い囲いとして知られています。
銀冠の特徴と由来|「冠」のような形が名前の由来
銀冠囲いは、▲7八銀・▲6八金・▲5八金と金銀が縦に並び、まるで将棋盤上に「冠(かんむり)」をかぶせたように見える独特の形が特徴です。
この見た目から「銀冠」という名前が付きました。
他の囲いと比べてもその見た目はかなり個性的で、一目でわかるほど金銀の密集度が高い形です。
構築するにはやや手数がかかりますが、その分しっかりとした堅さを誇り、攻めに転じるタイミングも取りやすいのが魅力です。
美濃囲いとの違いと発展性
銀冠囲いは、美濃囲いを土台にしていますが、大きな違いは「銀の位置と高さ」です。
美濃囲いでは▲7七銀や▲6八金がバランスよく配置されているのに対し、銀冠では銀を一段高く▲7八に配置し、その下を金で支える構造になります。
このように一段高く構えることで、敵の攻めに対する耐久力が増し、特に左辺や中央からの攻撃に強くなります。
また、角を使った反撃のルートも自然にできるため、攻守の切り替えがスムーズになります。
なぜ振り飛車党に好まれるのか?
銀冠囲いは、特に振り飛車を採用する棋士に好まれています。
その理由は、美濃囲いからの自然な移行ができ、かつ端攻めや中央突破などに強くなるためです。
振り飛車は、どうしても玉の位置が偏るため、攻めを受け止めるための強固な守りが必要です。
また、持久戦になった際に角を使った反撃や金銀の押し上げが有効になり、カウンター気味の攻撃にも対応しやすい構えとなっています。
そのため、藤井システムなどの対抗策が研究される中で、より現代的な囲いとして評価が見直されています。
銀冠囲いの基本的な組み方と手順
銀冠囲いをしっかりと理解するには、基本形の構築手順を知ることが重要です。
特に美濃囲いからの自然な発展形として使われることが多く、無理のない手順で組み上げるのがポイントです。
銀冠囲いの基本形と組み上げ手順
銀冠囲いの基本形は、以下のような手順で構築されます(※先手側を想定):
| 手順 | 内容 |
| ▲7六歩 | 振り飛車の構え(四間飛車など)を想定 |
| ▲6六歩 | 銀を6七へ進出させるため |
| ▲7七銀 | 美濃囲いへの準備 |
| ▲6八金右 | 金を囲いに加える |
| ▲7八金 | 玉の守りを固める |
| ▲5八金左 | 銀冠の縦のラインを完成させる |
| ▲7八銀 | 銀を7七からさらに一段上げる |
| ▲6八金直 | 金を銀の下に配置することで「冠」状に |
このように、美濃囲いから始まり、銀を1段上げて「銀冠」に発展させる構えです。
組み上げに8〜10手程度かかるため、相手の攻め筋を見ながら柔軟に移行することが求められます。
振り飛車に対して有効な構えの理由
銀冠囲いが振り飛車に強い理由は、その「縦に強い構造」にあります。
特に、振り飛車側からの端攻めや左辺からの攻撃に対して、金銀が密集していることで耐久性が高まり、玉が非常に安全になるのです。
さらに、美濃囲いでは弱点とされる角筋(例えば5五角など)にも比較的強く、持久戦になったときに玉が早く逃げやすいという利点もあります。
したがって、現代将棋のような緻密な中終盤戦にも耐えられる構えとして見直されています。
実戦での構築例|先手・後手での形の違い
実戦では、先手・後手どちらでも銀冠囲いを構築することができますが、細かい形に違いがあります。
たとえば、後手番での銀冠では、玉の位置が△3二→△4一→△3二(または△2一)と少し変則的な位置になるため、相手の攻め方に応じてフレキシブルに構える必要があります。
また、先手番では比較的スムーズに銀冠を完成できますが、そのぶん相手の急戦への警戒も必要です。
特に角交換系の将棋になると、銀冠の弱点(横からの攻めや上部からの圧力)を突かれることもあるため、バランスのとれた攻めと受けを意識した指し回しが求められます。
銀冠囲いのメリットとデメリット
銀冠囲いは美濃囲いの発展型として人気が高く、持久戦に強い構えです。
ただし、万能ではなく、他の囲いと比較したうえでの特徴を理解することが重要です。
堅さ・柔軟性・攻守のバランスを評価
銀冠囲いの最大のメリットは、「バランスの良さ」です。
堅さと柔軟性の両方を備え、攻守に対応できる囲いとして評価されています。
【銀冠の特徴】
| 項目 | 評価内容 |
| 堅さ | 美濃囲いよりも一段階堅く、上からの攻めにも強い |
| 柔軟性 | 玉が逃げやすく、形を変化させやすい |
| 攻撃力 | 守りの形を残したまま攻めに転じやすい |
| 構築スピード | 美濃囲いよりは時間がかかる(8~10手) |
特に「美濃囲い→銀冠→銀冠穴熊」と発展させることで、状況に応じて防御力を強化することも可能です。
これにより、持久戦に強い構えとして愛用される理由となっています。
他の囲い(穴熊・矢倉・美濃)との比較
他の囲いと比較した場合の銀冠の特徴を表で整理してみましょう。
銀冠は美濃囲いの弱点である「縦からの攻め」に強く、穴熊ほどではないにせよ堅さもあり、スムーズに攻撃体勢に移れるバランス型。
持久戦では穴熊にやや劣る部分はありますが、終盤の玉の逃げやすさでは一歩リードしています。
銀冠囲いが向いている棋風とは?
銀冠囲いが向いているのは、以下のような棋風の方です。
- じっくり構えて戦うのが好きな人
→ 美濃囲いよりさらに固めたい人に最適 - 振り飛車を使うプレイヤー
→ 特に四間飛車や三間飛車と相性が良く、自然な流れで組みやすい - 終盤力に自信がある人
→ 玉の逃げ道が広く、終盤の粘りを活かしやすい
また、プロの対局でも銀冠はしばしば登場しており、研究も進んでいます。
組むのが多少遅くとも、その分リターンが大きい構えであるため、中級者以上の方にとっては、非常に心強い武器となるでしょう。
銀冠囲いへの対策と崩し方
銀冠囲いは堅さと柔軟性を兼ね備えた優れた構えですが、当然ながら弱点も存在します。
ここでは、銀冠を相手にした場合の攻め筋や崩し方を解説します。
効果的な攻め筋|端攻めや中央突破の狙い
銀冠囲いに対する基本的な攻め方は、「端攻め」と「中央突破」が有効とされています。
【1. 端攻め】
銀冠は玉が右側に寄っているため、1筋や9筋の端攻めが有効です。
特に1筋(先手番の場合)を歩で伸ばし、香車や桂馬と連動して攻めるのが定番の手筋です。
- 端歩を突き捨ててから香交換を狙う
- 桂馬で攻め筋を加える
- と金作りで玉の逃げ道を制限する
【2. 中央突破】
もうひとつの有効な手段は中央突破です。
特に銀冠の銀が左に上がっている場合、中央が手薄になりやすい傾向があります。ここを突けば、バランスが崩れて一気に崩壊する可能性も。
- 飛車や角を中央に効かせる
- 相手の囲いを分断するように攻める
- 歩交換で開戦し、馬を作るチャンスを狙う
バランス型ゆえに“どこも弱点がない”ように見えますが、「バランスの良さ=弱点がない」ではなく、「すべてが中間」という特徴であることを意識しましょう。
よくある形と崩し方の手順例
以下に、実際によく使われる崩しの手順を例示します。
【よくある崩しの流れ(端攻め)】
▲1六歩 △1四歩
▲1五歩 △同歩
▲同香 △1三歩
▲1八香 △1四香
▲同香 △同歩
▲1五歩…
この流れで端を削っていき、と金を作って玉に迫る展開に持ち込めます。
香車や角のサポートがあれば、さらに破壊力が増します。
【中央から崩す例】
▲5六歩 △同歩
▲同銀 △6四歩
▲5五銀 △5四歩
▲6六銀(退却)→▲4六銀(転回)…
中央の歩交換から銀を進出させて、敵陣にプレッシャーをかける形です。
飛車の成り込みや角交換に備えた布陣も大切です。
実戦での注意点と対策方法
銀冠を崩すにはタイミングと形の理解が重要です。
以下のような点に注意しましょう。
| 注意点 | 解説 |
| 焦って攻めない | 銀冠は粘り強いため、じっくり準備が必要 |
| カウンターに注意 | バランス型ゆえに、無理攻めすると逆襲される |
| 駒の連携が鍵 | 1枚では崩れにくいため、複数の駒を連動させる |
特に、角の使い方が勝敗を分けます。うまく馬を作れる形や、敵玉の“斜め”からのプレッシャーを意識すると崩しやすくなります。
銀冠囲いは初心者にもおすすめ?
「銀冠囲いは初心者にもおすすめ?」 のセクションを執筆します。
銀冠囲いはプロの実戦でも多く採用されており、その堅さと柔軟性が評価されています。
しかし、初心者にとってはどうなのか?
ここでは初心者が使う際のポイントや、他の囲いとの比較を交えて解説します。
初心者が使う際のポイントと注意点
銀冠囲いは堅さだけでなく、組む際の手順も比較的シンプルなため、初心者にも十分おすすめできます。
ただし、いくつかの注意点もあります。
【ポイント】
- 矢倉から自然に発展できる構えのため、初心者でも違和感なく組める。
- 囲いのまま守るだけでなく、攻撃への転用がしやすい構造を持っている。
- 玉が深く囲われるため、**「終盤まで安心して指せる」**という安心感がある。
【注意点】
- 銀の位置取りを誤ると弱点になりやすいため、正しい配置を理解する必要がある。
- 玉の位置が端に寄るため、端攻めに弱くなりやすい点を意識する。
- バランス型とはいえ、中途半端な攻めは禁物。守りと攻めのメリハリが必要。
初心者が使うなら、「囲いの完成までの手順をきっちり覚える」ことが最初の一歩になります。
組みやすさと学習難易度を他囲いと比較
銀冠は、矢倉や美濃囲いなど他の囲いと比較して“発展性のある囲い”です。
以下の表に、よく使われる囲いとの比較をまとめました。
| 囲い名 | 組みやすさ | 守備力 | 攻撃との両立 | 学習難易度 |
| 美濃囲い | ◎ | ○ | ○ | 低め |
| 矢倉囲い | △ | ◎ | △ | 高め |
| 穴熊囲い | △ | ◎◎ | △ | 高め |
| 銀冠囲い | ○ | ◎ | ◎ | 中程度 |
銀冠は「美濃→銀冠」という流れで組めるため、美濃囲いを卒業したい初心者に最適な囲いです。
また、急戦に対応しやすい点も評価されています。
覚えておきたい基本パターンと応用形
銀冠囲いは以下のようなパターンが代表的です。
どれも数手の工夫で形になるため、実戦で覚えておくと便利です。
【基本形】
▲7八玉 → ▲6八銀 → ▲7九金 → ▲6九金 → ▲5八金(または6七金)
▲7八玉 → ▲8八玉 → ▲9八香 → ▲8八銀 → ▲7八金
このような手順で、玉を安全地帯に寄せ、金銀で囲い込むことができます。
【応用形】
- 美濃囲いからの発展:△6二玉 → △7二銀 → △8一玉 → △7一金 → △6一金 → △6二金…
- 相振り飛車や相居飛車でも流用可能:構えだけでなく、対振り飛車戦にも強い。
形を覚えるだけでなく、「なぜこの形になるのか」という意味も理解しておくと、応用力が身につきます。
銀冠囲いを学べるおすすめの本・動画
銀冠囲いは、その堅さと柔軟性から多くのプロ棋士や中級者にも支持されており、学習教材も豊富です。
ここでは、初心者から中級者までにおすすめできる書籍や動画、プロ実戦例を紹介します。
入門書や定跡本で学ぶならこれ!
まずは書籍から。囲いの特徴や構築方法、実戦例を体系的に学ぶなら本がおすすめです。
【初心者向け】
• 『将棋・囲いの基本』(池田書店)
各種囲いの組み方や強み・弱みを図解付きで丁寧に解説。銀冠囲いも分かりやすく紹介されています。
• 『囲いの破り方・守り方』(浅川書房)
囲いの守備だけでなく、崩し方にも触れているため、両面から理解を深められます。
【中級者向け】
• 『将棋囲い辞典』(マイナビ出版)
矢倉・美濃・穴熊などとともに、銀冠も掲載。囲いの歴史や進化も学べます。
• 『最新戦法マガジン』シリーズ
特集号では、プロによる銀冠の活用例や評価が掲載されていることも。
囲いの学習は、定跡を丸暗記するよりも“意味を理解して覚える”ことが上達への近道です。
YouTubeで学べる銀冠囲い解説動画
今では、YouTubeでも無料で質の高い囲い講座が数多く公開されています。
特に銀冠囲いは、動画で見て理解するのが効果的です。
【おすすめチャンネル】
• 将棋放浪記(プロ棋士藤森哲也五段)
振り飛車相手に銀冠を組む流れを実戦形式で解説してくれます。
• 元奨励会員アユムの将棋実況
囲いを実戦でどう使うかがわかりやすい。銀冠の使用率も高め。
• 将棋講座・NHK将棋トーナメント公式
プロ棋士による解説付きで、銀冠の堅さや形の美しさが学べる。
また、「銀冠 囲い 組み方」「銀冠 相手 崩し方」などで検索すれば、ピンポイントの動画も見つかります。
プロの実戦例をチェックして理解を深めよう
銀冠囲いは現代将棋でも使用されており、プロ棋士の実戦例を通じてその有効性を確認することができます。
【銀冠を使用する代表的なプロ棋士】
• 久保利明九段:対振り飛車戦での銀冠活用が多い。バランス感覚に優れた指し回し。
• 木村一基九段:守りの固さを活かしつつ、銀冠からのカウンターを狙うスタイル。
• 稲葉陽八段:現代将棋における銀冠の可能性を見せた棋譜多数。
プロの棋譜は将棋連盟公式サイトや「将棋DB2」などで簡単に検索できます。「囲い名+プロ名」で探すのもおすすめです。
銀冠囲いまとめ|万能な囲いか?その真価とは
銀冠囲いはその堅実さと柔軟な対応力から、現代将棋でも一定の評価を保ち続けています。
ここでは、その本質的な魅力と、今後の指し方の参考となる視点を整理していきましょう。
あらゆる戦法に対応できる柔軟な囲い
銀冠囲いは、相手の戦法に合わせて形を変化させられるのが最大の魅力です。
特に振り飛車に対しては美濃囲いの強化版として機能し、攻めに転じる際も、バランスを崩さずに展開できるのが強みです。
- 中盤以降、玉の移動や金銀の再配置で形を変えられる
- 相手の端攻めや角筋を警戒しながら、持久戦にも対応
- 穴熊よりも崩されにくく、矢倉よりも組みやすい
このように、“万能型”の囲いとして多くの戦型に対応可能な点が、多くの中級者以上に好まれる理由の一つです。
囲いの変遷から見る銀冠の立ち位置
将棋界では、囲いの進化もプレースタイルの変化と連動しています。
銀冠囲いは、以下のような背景で評価されてきました。
| 時代 | 主流の囲い | 銀冠の位置付け |
| 昭和中期 | 矢倉・美濃 | 変則的な構えとして扱われていた |
| 平成初期 | 穴熊全盛 | 穴熊の代替案として再評価 |
| 現代(令和) | 角交換・ミレニアムなど柔軟戦法が台頭 | 柔軟に変化できる囲いとして注目 |
このように、時代に応じて再評価される囲いとして、銀冠は独自の存在感を保っています。
あなたに合った囲いを選ぶ参考に!
将棋は個々の棋風によって、合う囲いや戦法が変わります。
銀冠囲いが向いているのは、次のような人です。
- 相手の出方を見ながら柔軟に戦いたい人
- 固く守りつつ、カウンター攻撃で勝負を決めたい人
- 美濃囲いや矢倉に慣れ、次のステップに進みたい人
一方で、「ガッチリとした守りを固めたい」という人には穴熊、「厚みで圧力をかけたい」という人には矢倉が向いているかもしれません。
まずは銀冠囲いを実戦で試してみて、自分の感覚に合うかどうかを体感することが大切です。
将棋の矢倉囲い完全ガイド|組み方・戦法・攻め方・崩し方まで徹底解説
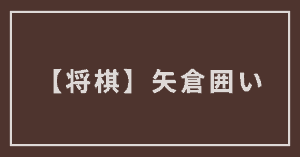
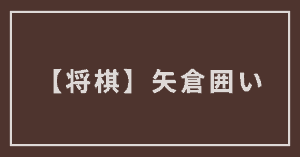
将棋の美濃囲いとは?種類・作り方・崩し方・銀冠との違いまで完全ガイド