将棋の戦法にはさまざまな種類がありますが、なかでも「石田流(いしだりゅう)」は、三間飛車を代表する攻撃的な振り飛車戦法として、多くの将棋ファンから支持を集めています。特に速攻性に優れ、相手が駒組みに時間をかけている間に主導権を握れることから、アマチュアからプロまで幅広く指されています。
一方で、石田流は「受けが弱い」「後手番では組みにくい」といった弱点もあり、相手の対策によっては難しい展開を強いられることも。この記事では、そんな石田流について「基本構え」「定跡」「対策」「プロの名局」など、初心者〜中級者にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
石田流をこれから覚えたい方、使っているけどもっと深く知りたい方、対策したい居飛車党の方にも必見の内容です。


◆アプリダウンロード数4,000万突破!


将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、
【 ABEMA
プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。
>> 将棋見るならABEMA
石田流とは?|将棋の代表的な三間飛車戦法
石田流は、振り飛車の中でも三間飛車(飛車を7筋に構える戦法)の発展形として知られる攻撃型戦法です。序盤から飛車を活用し、早い段階で相手陣に圧力をかけていく構想が特徴です。
石田流の基本構えと特徴とは?
石田流の基本形は、▲7六歩〜▲7八飛〜▲6六歩〜▲6八銀〜▲7七桂などと進行し、飛車を7筋に置いたまま、桂馬・角・銀を連携させて中央から右辺にかけての厚みを作ります。囲いは舟囲いや美濃囲いに似た形を用いながら、バランスの取れた攻めと守りを狙います。
攻撃の主軸は7筋からの攻め。▲7五歩と突き捨てて飛車の展開を図り、角のラインや桂馬の跳ねによって相手陣を一気に崩すことを狙います。特に相手が持久戦を志向している場合に有効な速攻が魅力です。
三間飛車との関係|なぜ石田流が強いのか
石田流は三間飛車の中でも、特に「本組」と呼ばれる完成形を目指す戦法です。通常の三間飛車よりも飛車・角・桂・銀の連携が強く、攻撃力が段違いに高いのが特徴です。
また、定跡が豊富に研究されており、AIによる最新の検討でも一定の評価を得ているため、理論武装しやすいのも魅力。後手でも活用できる工夫が進んでいるため、幅広いレベルの将棋ファンにとって心強い武器となります。
居飛車との対抗形で活きる石田流の力
居飛車の主な布陣である矢倉・急戦・右四間飛車などに対して、石田流は独特の攻め筋を持っています。特に相手が右側から攻めてくる場合、飛車が左側(7筋)に構えていることで自然とバランスが取れるのが強みです。
また、端攻めや中央突破など、多彩な攻撃パターンを備えているため、相手の囲いや陣形によって臨機応変に作戦を変更できる柔軟性もあります。実戦での勝率を上げたい方にとって、有力な選択肢の一つと言えるでしょう。
石田流の主な指し方と定跡の流れ
石田流は速攻型の振り飛車戦法でありながらも、複数の指し方・定跡パターンが存在します。ここでは、代表的な指し方と流れをわかりやすく紹介します。
石田流本組の基本定跡と流れ
石田流の「本組」とは、7筋に飛車を構えたまま左銀や角、桂馬、金を適切な位置に展開し、理想的な形に組む定跡のことです。以下は基本的な手順です(▲先手):
- ▲7六歩
- △3四歩
- ▲7八飛
- △8四歩
- ▲6六歩
- △8五歩
- ▲6八銀
- △3二金
- ▲7七桂
この形で石田流の土台が完成します。さらに▲7五歩と仕掛けていくと、攻めに転じることができます。
本組の特徴は、攻撃陣形が自然に形成されることです。特に▲7七桂の跳ねと▲6六歩の連携で角道と桂の利きを活かした攻めが非常に強力です。囲いは「簡易舟囲い」や「高美濃囲い」などが採用されることが多いです。
早石田・急戦石田・居飛車急戦への対応
石田流にはさまざまなバリエーションがあります。その中でもよく知られているのが「早石田」です。これは角道を開けずに▲7六歩→▲7八飛と進める形で、相手が3手目▲2六歩などの居飛車志向で来た場合に特に効果的です。
また、早石田は相手の不備をついて一気に仕掛ける速攻戦法としても知られており、序盤で主導権を握るのに非常に適しています。ただし、正しく対応されるとやや形が不安定になりやすい面もあるため注意が必要です。
居飛車急戦(▲6四角型など)に対しては、角交換や飛車の横利き、桂馬の跳ねを活かしてうまく反撃を狙うのがポイントです。
石田流を活かした攻め筋と中盤戦術
石田流の攻め筋は、7筋からの突破が基本ですが、それだけではありません。以下のような多彩な展開が可能です:
- ▲7五歩〜▲7四歩と突進し飛車を活かす
- ▲5五角の打ち込みで相手陣を分断
- ▲4六銀〜▲5五銀と中央に銀を繰り出す
- ▲2六飛と転換して端攻めを狙う
特に中盤以降の銀・桂・角の連携が鍵であり、局面によっては金も戦場に投入し、一気に勝負を決める力を持っています。攻撃に厚みがあるため、じっくり組んで一気に仕掛ける戦術がハマれば非常に強力です。
石田流のメリットとデメリット|採用すべきか?
石田流は魅力的な戦法である一方で、明確な長所と短所が存在します。ここでは採用前に知っておくべきポイントを整理し、あなたの棋風に合うかどうかを判断する材料をお伝えします。
石田流のメリット|攻撃力と柔軟性の高さ
石田流の最大の魅力は「速攻性」と「柔軟な攻め筋」にあります。以下のような利点があります:
- 飛車先を早期に制圧しやすい:7筋からの圧力で主導権を握れる
- 角・銀・桂の連携が強力:自然な流れで攻撃陣形が完成
- 囲いが柔軟に変化可能:舟囲いや高美濃囲いなど、相手の戦型に合わせた構築ができる
- 相手のミスを突きやすい:特に早石田は隙をつけばすぐ勝勢に持ち込める
石田流のデメリット|後手番・対策の進化
特にアマチュアでは石田流の速攻にうまく対応できないことも多く、短期決戦での勝率が高くなる傾向があります。
一方で、石田流には注意すべき欠点も存在します。
- 先手番向けの戦法:後手で使うには一手損になりやすく、工夫が必要
- 居飛車急戦に弱い場面もある:特に角道を止められた場合や▲6四角のような奇襲に脆い
- 形が決まっているぶん対策されやすい:石田流を知っている相手には封じ込められやすい
- 玉が薄くなりやすい:囲いが簡略化されるため、反撃を受けると脆い
このように、「対石田流」対策が進んでいる現代将棋では、相手に研究されているとやや不利になるケースもあります。
こんな人におすすめ!石田流が合う棋風とは
石田流は以下のようなプレースタイルの方に特におすすめです:
| 棋風 | おすすめ度 | 理由 |
| 攻め好きな人 | ★★★★★ | 序盤から主導権を握れるため、攻撃派に最適 |
| 形を覚えるのが得意な人 | ★★★★☆ | 基本形を覚えれば幅広く応用可能 |
| 短期決戦を好む人 | ★★★★☆ | 早石田などで一気に決着をつけやすい |
| 柔軟な指し回しが苦手な人 | ★★☆☆☆ | 相手に対応されると苦しくなる局面も多い |
逆に、「じっくり組み立てる戦法が好き」「囲いを厚くして守りを固めたい」タイプの方には、やや不向きかもしれません。
石田流のプロ棋士による実戦例と解説
石田流はアマチュアに限らず、プロ棋士の間でも実戦で採用されることがあります。ここでは代表的なプロ棋士や対局例を紹介し、どのように石田流が活かされているのかを見ていきます。
プロ棋士が採用した注目の石田流対局
石田流はかつて「アマチュア向け」と見なされていたこともありますが、近年ではプロの実戦でもたびたび登場しています。特に注目されたのは以下のような棋士です:
- 藤井聡太竜王(vs広瀬章人八段など):居飛車党でありながら石田流模様に進んだ対局もあり、その柔軟な構想力が話題に。
- 久保利明九段:振り飛車党の代表格。石田流をはじめ、三間飛車全般に精通し、巧みな捌きで魅せる将棋が多い。
- 村田顕弘六段:石田流を積極的に実戦投入し、「研究型石田流」ともいえる現代的アプローチを見せている。
プロの対局では、石田流を主導権を握るための「仕掛けの起点」として用い、単なる奇襲ではなく本格的な構想戦術の一つとして位置付けられています。
序盤~中盤の攻防|どこで主導権を握るか?
プロの対局では、石田流を使ったからといって単純な攻め合いにはなりません。むしろ、序盤での駆け引きと陣形の構築にこそ、真価が表れます。
たとえば、以下のような展開が典型です:
- 先手が7六歩→7五歩→7四歩と進出し、角を引いて石田型に構築
- 後手が6四歩型や角交換拒否で対応してくる中、5筋や中央への展開も視野に
- 玉の囲いは舟囲いや高美濃囲いに移行しつつ、飛車先をめぐる攻防へ突入
このように、「飛車の位置だけでなく、銀や桂の連携」「囲いの柔軟性」も大きく影響します。
プロの実戦では、このあたりの調整が非常に巧妙です。
プロ実戦から学ぶ石田流のコツ
以下のようなポイントは、プロの実戦からぜひ取り入れたいテクニックです:
- 相手の囲いによって作戦を変える:美濃囲いなら右銀速攻、矢倉なら角筋を絡めた攻め
- 7筋にこだわらず5筋・4筋も活用:石田流だからといって一直線ではなく、多角的に攻める
- 端攻めとの連携:7筋からの攻めと同時に端歩を突き合い、相手の囲いを揺さぶる
- 角を活用する構想:5四角や6五角など、攻防両面に睨みを利かせる位置に置くと有効
また、将棋ウォーズや将棋倶楽部24などでも、上位者の石田流採用局が閲覧できます。自分の棋譜と見比べながら研究するのも効果的です。
石田流の対策と崩し方|有効な受け方とは?
石田流は攻撃的な構えである一方で、対応を誤ると一気に主導権を握られてしまいます。ここでは、居飛車党が石田流にどう立ち向かうべきか、対策と崩し方について解説します。
石田流に有効な作戦と構え方
石田流に対する基本戦略としては、以下のような構えが効果的です。
- 舟囲いからの速攻:石田流が構築される前に、5筋や6筋から速攻を仕掛ける
- 角交換を拒否した陣形:相手の角道を止めたまま飛車先を突かせず、バランスよく構える
- 右銀速攻・左美濃急戦:先手石田に対しては、6四銀〜7三銀型から右サイドを固めるのが有効
石田流は基本的に7筋から攻める戦法ですが、逆にいえばそこに戦力が集中しているということ。
守りながら反対側(左辺)にカウンターを狙う構想も有力です。
崩し方の基本は「中央突破と端攻めの併用」
石田流は一見堅そうに見える陣形でも、囲いが軽いことが多く、急所を突かれると脆さが出やすいのも事実です。特に狙うべきは以下の2点。
| 崩しのポイント | 解説 |
| 中央突破 | 飛車先が重くなりがちな石田流では、中央が手薄になりやすい。銀や角を使って4~5筋から突破を狙う。 |
| 端攻め | 玉が左に寄っていれば端攻めが急所。1筋~2筋を突いて桂や香を活用する。 |
また、石田流は美濃囲いや簡易な舟囲いを採用していることが多く、持久戦より速攻に弱い傾向があります。そのため、「囲い合いを避けて素早く攻める」戦術が有効です。
注意したい石田流のカウンターとその対処法
石田流は構えが完成すれば攻撃力は非常に高く、うかつに動くと反撃を受けてしまいます。以下のような点には特に注意が必要です。
- 飛車の横利きを使った反撃:7筋を突いてきた際、6筋・8筋から飛車の利きを活用されることがある
- 角の転換(8六角、6五角)による攻守両面の働き
- 桂馬や香車を活用した端攻めの逆襲
対応策としては、相手の駒組みを見ながら早めにバランスを崩すことが重要です。
たとえば角道を止めたまま組む「角道閉鎖型」や、6四歩型で飛車の働きを抑制する布陣なども有効です。
石田流は初心者にもおすすめ?|導入と学び方
石田流は魅力的な攻撃型戦法として、多くの将棋ファンに支持されています。ここでは、初心者が石田流を学ぶ際のポイントや注意点を解説します。
初心者が石田流を使う際のポイント
石田流は「速攻」「角の活用」「飛車の位置取り」といった要素を学べるため、攻めの感覚を養いたい初心者には非常におすすめの戦法です。
ただし、以下の点に注意する必要があります。
- 正確な組み上げが求められる:早石田を狙う場合は、相手の対応により形を調整しなければならず、柔軟性が求められます。
- 守りが手薄になりがち:石田流は左側の囲いが軽くなりやすいため、攻め急がず、玉の安全も確保する意識が大切です。
最初は「後手番での3三角型」など、やや守備的な形から始めるのもよいでしょう。
石田流の組みやすさと学習難易度
石田流は、構えそのものはシンプルですが、相手によってベストな形が変わるため、「決まった形にする」のが難しい場合もあります。
| 評価軸 | 内容 |
| 組みやすさ | △(相手の対応に左右される) |
| 攻撃力 | ◎(破壊力が高い) |
| 守備力 | △(囲いが軽くなりやすい) |
| 学習のしやすさ | ◯(YouTubeや書籍が豊富) |
定跡が整備されている戦法のため、しっかり学習すれば十分に戦える構えです。
初心者はまず、「基本形(▲7六歩→▲7五歩→▲7八飛型)」から入り、相手の角道や飛車先の突き方によって形を柔軟に変える練習をしましょう。
覚えておきたい石田流の基本パターンと応用形
石田流にはいくつかの代表的な指し方と、それを応用した戦型があります。基本を押さえることで、幅広い局面に対応できるようになります。
- 基本形(早石田):▲7六歩 → ▲7五歩 → ▲7八飛 → ▲6六歩 → ▲6七銀 → ▲6八玉
- 応用形(石田流本組):基本形から▲5六歩 → ▲5七銀 → ▲4八玉 → ▲3八金 と中央から左に玉を移動する
- ▲7八飛型のままの早仕掛け:囲いを簡略化して攻めを優先
応用形に進むことで、相手の出方に合わせた柔軟な構えが可能になります。定跡本やYouTubeで複数のパターンを覚えておくと、実戦でも対応しやすくなります。
石田流を学べるおすすめの本・動画・定跡解説
石田流は昔ながらの戦法でありながら、現代でも研究が進む魅力的な構えです。ここでは、石田流を深く理解し、実戦で活かすための学習リソースをご紹介します。
初心者向けから上級者まで対応|おすすめ定跡本3選
将棋の学習では、体系的に知識を得られる書籍が最も安定した学習手段です。石田流に特化した定跡書は多数ありますが、特に評価の高いものを紹介します。
| 書籍名 | 著者 | 特徴 |
| 石田流道場(1〜3巻) | 戸辺誠 | 実戦的な解説で人気。変化手順も豊富に掲載。 |
| 石田流を指しこなす本(1・2) | 藤井猛 | 元祖藤井システムの使い手が解説。構想力が身につく。 |
| ひと目の石田流 | 所司和晴 | 初心者にもわかりやすく要点をまとめた一冊。 |
特に戸辺誠九段のシリーズは、最新の実戦でも通用する構想が多く取り上げられており、レベルを問わずおすすめです。
YouTubeで学べる石田流講座・実況解説
最近はYouTubeを活用して学ぶ人も増えています。無料で視聴でき、実戦譜も豊富に取り上げられているため、視覚的に覚えたい人に最適です。
おすすめのチャンネル:
- 戸辺チャンネル(戸辺誠九段):石田流を愛用しており、わかりやすい解説が人気。
- 将棋放浪記:対局実況型で、リアルな指し回しや勝負の流れを体感できる。
- 将棋講座チャンネル(NHK杯関連):プロによる実戦対局での石田流が観られる。
これらの動画を繰り返し見ることで、定跡や構想を自然に覚えることができるでしょう。
石田流のプロ実戦例で実力アップ
プロの棋譜を研究するのも、石田流を深く理解する方法の一つです。以下は石田流を多用するプロ棋士とその代表局です。
- 戸辺誠九段 vs 中村太地七段(NHK杯)
→ 鮮やかな石田流の速攻が決まった一局。 - 藤井猛九段 vs 羽生善治九段(王座戦)
→ 石田流本組からの創造的な構想が見どころ。 - 山本博志四段 vs 佐々木大地七段(新人王戦)
→ 若手らしい鋭い石田流の応酬が光る実戦。
これらの棋譜は将棋DB2や将棋連盟ライブ中継などで確認可能です。実戦から学ぶことで、タイミングの重要性や指し手の意図が理解しやすくなります。
まとめ|石田流は攻めを学ぶうえで最適な戦法
石田流は、古くから存在する伝統的な振り飛車戦法でありながら、今なお多くの棋士に支持されている攻撃型の囲いと構想を備えた戦法です。特に三間飛車と組み合わせた柔軟な布陣や、角交換からの速攻筋など、現代将棋でも十分通用する武器となります。
以下に石田流の特徴をまとめます。
序盤から主導権を握れるアグレッシブな構え
石田流は序盤から積極的に仕掛ける構想が可能であり、攻撃的な将棋を指したい人にぴったりの戦法です。特に▲7五歩〜▲7六飛と進める構えから、素早く相手にプレッシャーを与える展開が得意です。
また、相手の出方によって柔軟にプランを変えることも可能で、相手のミスを咎める鋭さが魅力となります。
定跡と実戦例を学べば勝率アップも期待できる
石田流は決して一発狙いの奇襲戦法ではなく、正しい手順や定跡を覚えれば長く使える戦法です。本記事で紹介したような定跡書やYouTube、プロ棋士の実戦譜を通じて学ぶことで、より深く石田流を理解し、自信を持って実戦に臨むことができるでしょう。
石田流は将棋の「攻め」を鍛えたい人に最適
特に将棋初心者〜中級者にとって、一貫した攻め筋や局面の作り方を学ぶには、石田流は最高の教材とも言えます。最初は手順を覚えるだけでも十分戦えるため、ぜひ気軽にチャレンジしてみてください。
また、相手の対応によっては矢倉・美濃・穴熊などの囲いとの組み合わせも可能で、幅広い戦型に発展する可能性も持ち合わせています。
将棋の三間飛車とはどんな戦法?石田流との違い・組み方・対策まで徹底解説
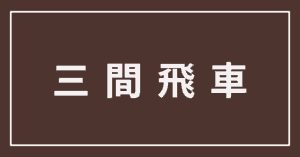
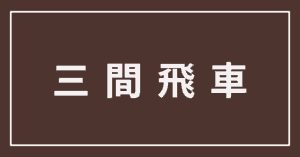
将棋の中飛車・ゴキゲン中飛車を徹底解説|最新定跡・対策・評価の真相とは?



