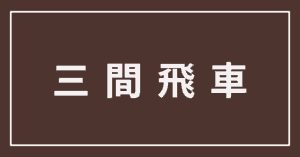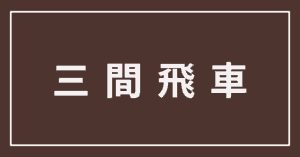将棋の戦法の中でも、独特な駒組みと主導権を握りやすい攻め筋で人気を集めている「中飛車」。
その中でも特に有名なのが「ゴキゲン中飛車」です。
しかし最近では「終わった戦法」「うざい」といったネガティブな声も聞こえてきます。
一方で、プロ棋士による最新研究やアプリ上での採用例も増えており、依然として注目の戦法でもあります。
本記事では、中飛車やゴキゲン中飛車の特徴・由来・定跡・メリット・対策方法から、なぜ「ゴキゲン」と呼ばれるのか、そして「終わった」と言われる真意まで、最新の研究と実践データをもとに徹底解説します。
中飛車に興味がある初心者から、対策を学びたい中級者まで役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
将棋の戦法一覧|初心者向けから最強戦法・奇襲型まで完全解説!


◆アプリダウンロード数4,000万突破!


将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、
【 ABEMA
プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。
>> 将棋見るならABEMA
将棋の中飛車とは?基本と戦法の特徴を解説
中飛車とは、飛車を中央(5筋)に構える振り飛車戦法の一つです。
振り飛車の中でもバランスが良く、攻守において万能型の戦法として多くの指し手に好まれています。
中飛車の基本構造と狙い
中飛車の最大の特徴は、序盤で飛車を5筋に振ることで中央を制圧し、主導権を握ろうとする構想にあります。
以下は中飛車の代表的な形です。
| 手順例(先手) | 内容 |
| ▲7六歩 | 角道を開ける |
| △3四歩 | 後手の定跡 |
| ▲2六歩 | 飛車先の歩を突く |
| △8四歩 | 角道を開けずに様子を見る |
| ▲5八飛 | 中飛車に構える! |
飛車が中央にいることで、中央突破や速攻、玉頭攻めなど、様々なプランに移行しやすくなります。
振り飛車の中でも中飛車が人気な理由
振り飛車は角道を止める「角交換拒否型」が主流ですが、中飛車は角道を開けたまま戦える点が特徴です。
そのため、序盤から角交換を含む展開にも強く、対居飛車・対振り飛車の両方に対応しやすい万能さが評価されています。
中飛車が人気な主な理由
- 中央の主導権を握れる
- 柔軟な囲い(美濃囲い・左美濃など)に発展可能
- 攻撃のパターンが豊富(中央突破、玉頭攻めなど)
- 棋力差が出にくい安定した構造
また、スマホアプリ「将棋ウォーズ」などでも勝率が高く、多くのアマチュアが採用しています。
中飛車の代表的な変化とバリエーション
中飛車には大きく分けて以下のようなバリエーションがあります。
| バリエーション | 特徴 |
| ゴキゲン中飛車 | 角道を開けたまま速攻を狙う最新形 |
| 旧型中飛車 | 角道を止めて守備重視の構え |
| 超速中飛車 | 早い段階で攻撃を仕掛ける |
| 中飛車左穴熊 | 玉を左に囲って耐久力重視 |
中飛車はこのように、状況や相手の構えに応じて自由自在に変化できる点も大きな魅力です。
将棋のゴキゲン中飛車とは?なぜ「ゴキゲン」と呼ばれるのか
中飛車の中でも特に有名なバリエーションが「ゴキゲン中飛車」です。
プロ・アマ問わず愛用されている戦法で、現在の振り飛車の代表格ともいえます。
この見出しでは、ゴキゲン中飛車の由来・特徴・基本構造・注目ポイントについて詳しく解説していきます。
ゴキゲン中飛車の名前の由来
まず気になるのが「ゴキゲン」という独特な名前の由来です。
これはプロ棋士・近藤正和六段が開発した戦法で、将棋中継中に「近藤先生がゴキゲンですね!」という実況から命名されたという説が有力です。
ゴキゲン中飛車の基本構造と定跡
つまり、正式名称というよりは、愛称として広まった呼び名ということです。
軽やかでポジティブな響きが戦法のイメージとも一致し、広く浸透しました。
ゴキゲン中飛車の最大の特徴は、角道を開けたまま中飛車に構えることにあります。
従来の中飛車は角道を止めてから飛車を振るのが主流でしたが、この戦法はそれを覆す革新的なアイデアでした。
ゴキゲン中飛車の代表的な序盤構成(先手)
| 手順 | 指し手 | 解説 |
| 1手目 | ▲7六歩 | 角道を開ける |
| 2手目 | △3四歩 | 後手の角道対応 |
| 3手目 | ▲2六歩 | 飛車先を突く |
| 4手目 | △8四歩 | 角交換も視野 |
| 5手目 | ▲5八飛 | ここで中飛車に構える |
このようにして、角道を開けたまま5筋に飛車を構えることで、角交換にも対応しやすく、主導権を握りやすい形になります。
なぜゴキゲン中飛車は人気なのか?メリットまとめ
ゴキゲン中飛車は、以下のようなメリットによってアマチュアにも広く支持されています。
ゴキゲン中飛車の主なメリット
- 角交換に強い:角道を開けたままなので、早い段階で角交換されても困らない構造。
- 中央制圧力が高い:飛車が中央に位置しており、5筋の攻防で優位に立てる。
- 囲いの自由度が高い:美濃囲い、左美濃、銀冠など多彩な囲いに対応。
- 攻守のバランスが良い:中央攻め・玉頭攻め・相振りすべてに柔軟。
ゴキゲン中飛車の基本戦略フロー
- 角道を開けて中飛車に構える
- 相手の対応を見ながら美濃囲いへ
- 相手の角交換に備えて金銀を柔軟に配置
- 中央突破・玉頭攻め・左からの攻めを使い分ける
「終わった」と言われる理由と現状
一部の将棋ファンや記事では「ゴキゲン中飛車は終わった」と表現されることもあります。
これは、居飛車側からの対策が確立されてきたことが背景です。
特に以下のような戦法が、ゴキゲン中飛車対策として有効とされています。
- 超速▲3七銀戦法
- 急戦左銀
- 銀対抗型
これらの戦法により、先手ゴキゲン中飛車の勝率がやや低下した局面が見られました。
しかし、これは「研究が進んだ結果」であり、戦法そのものの価値が失われたわけではありません。
実際には以下のような調整がなされており、新型のゴキゲン中飛車も登場しています。
- ▲6六銀型の新構想
- 端歩位取り型のアレンジ
- 棋書での最新定跡のアップデート
プロ棋士も採用!ゴキゲン中飛車の現在地
ゴキゲン中飛車はプロ棋士でも採用例があります。
代表的な使い手としては、以下のような棋士が挙げられます。
| 棋士名 | 特徴 |
| 近藤正和六段 | 開発者。ゴキゲンの名付け親 |
| 戸辺誠七段 | 明るい振り飛車の代表格。解説書も出版 |
| 菅井竜也八段 | 超攻撃的な振り飛車党で知られる |
| 渡辺明九段 | 過去に研究対局で使用した実例あり |
これらの棋士の影響により、ゴキゲン中飛車は今もアマチュアを中心に人気があり、「終わったどころか進化し続けている戦法」とも言えるでしょう。
将棋の中飛車はうざい?対策されやすいって本当?
中飛車に対して「うざい」「やりにくい」と感じる声は、将棋ファンの間でもよく見かけます。
これは主に居飛車党や初心者の視点から語られる感情であり、そこには中飛車独自の「戦いにくさ」が関係しています。
この章では、中飛車が「うざい」と言われる理由と、実際の対策法についてわかりやすく解説していきます。
なぜ中飛車は「うざい」と感じられるのか
中飛車がうざがられる理由は、大きく以下の3点に分けられます。
【中飛車がうざいと感じる理由】
| 理由 | 解説 |
| 中央を制圧してくる | 初心者は中央攻めに弱く、早く潰されることが多い |
| 定跡が複雑で対策しづらい | 特にゴキゲン中飛車など角道を開けたままの構えは、事前対策が必要 |
| 美濃囲いが硬くて崩れない | 守りが堅いため、簡単に突破できないと感じる |
つまり、攻めも守りもバランスが良いのが中飛車の強さであり、「うざい」と感じる本質です。
中飛車に対する基本的な対策の考え方
中飛車に対しては、序盤から積極的に主導権を握る姿勢が大切です。
以下に、よく使われる代表的な対策を紹介します。
【中飛車への代表的な対策戦法】
| 戦法名 | 特徴 |
| 超速▲3七銀 | 早めに銀を中央に繰り出し、飛車先を逆襲する構え |
| 急戦左銀 | 銀を左から中央に送り込み、飛車の利きを制限 |
| 舟囲い急戦 | 美濃囲いより早く戦える簡易囲いで先攻を狙う |
| 居飛車穴熊 | 玉を固めてカウンターを狙う |
特に「超速▲3七銀」は、プロ間でもゴキゲン中飛車対策として知られており、勝率も高い有力な作戦です。
初心者におすすめの中飛車対策手順
中飛車を相手にする初心者の方には、以下のような簡単な考え方を持つことが有効です。
【中飛車対策3ステップ】
- 飛車先の歩(2筋)を早めに突く
→ 中央に構える飛車のバランスを崩す - 角道を止めずに急戦構えにする
→ 相手の角交換に付き合わない - 美濃囲いにこだわらず舟囲いや銀冠を選ぶ
→ 守りより攻めを優先
こうしたシンプルな方針でも、相手のやりたい形を崩すことが中飛車対策の基本となります。
実際の勝率と評価値から見た中飛車の現状
プロの将棋やAIの研究によると、中飛車の勝率は以下のような傾向が見られます。
【プロ公式戦での中飛車の勝率データ(例)】
| 戦法 | 勝率(先手) | 勝率(後手) |
| ゴキゲン中飛車 | 約52% | 約48% |
| ノーマル中飛車 | 約50% | 約46% |
※出典:将棋DB2(2024年時点のプロ棋士データ)
このように、先手で使う中飛車はある程度勝率が安定しており、「うざい」と感じるのも納得できます。
しかし、勝率は五分前後であり、対策を知っていれば十分に戦える戦法とも言えるのです。
それでも中飛車が苦手ならどうする?
どうしても中飛車が苦手、という方には、以下のような工夫もおすすめです。
【中飛車対策のためにできること】
- 棋譜並べでプロの対局を見る
→ ゴキゲン中飛車 vs 居飛車急戦など - YouTubeなどで戦法解説動画を視聴
→ わかりやすく噛み砕いて解説されている - 将棋アプリで中飛車対策を練習
→ 将棋ウォーズ・ぴよ将棋などで練習モードを活用 - 中飛車に対して自分が使いやすい構えを覚える
→ 例えば「角交換型急戦」など
知識と経験を積むことで、「うざい」と感じる中飛車もやがて「読める・崩せる」相手に変わっていきます。
ゴキゲン中飛車はなぜ終わったと言われるのか?最新定跡も紹介
将棋ファンの間では「ゴキゲン中飛車はもう終わった」との声を耳にすることがあります。
しかし、実際には今でも多くのプロやアマチュアが採用している人気戦法です。
このセクションでは、なぜ「終わった」と言われるようになったのか、その背景や現状、そして最新定跡についても詳しく解説していきます。
「終わった」と言われる理由とは?
ゴキゲン中飛車が「終わった」と言われる理由は、主に以下の3点にあります。
【ゴキゲン中飛車が終わったとされる理由】
| 理由 | 詳細解説 |
| プロの採用率が減少 | 特にタイトル戦やA級棋士の間では使用例が減った |
| 対策が広まった | 超速▲3七銀や左銀急戦が定着し、有効な対策が多数出てきた |
| AI時代の影響 | AIによる序盤研究で「不利」と評価される変化が増えた |
こうした背景から、一部では「過去の戦法」「すでに読まれている」といった評価がついてしまっているのです。
実際の採用例は減っているのか?
では本当にプロ棋戦での採用は減っているのでしょうか?
以下のデータをご覧ください。
【プロ棋士によるゴキゲン中飛車採用例】
| 年度 | 採用回数 | 採用棋士例 |
| 2015年 | 約150局 | 久保利明、菅井竜也、戸辺誠など |
| 2020年 | 約90局 | 糸谷哲郎、藤井猛など |
| 2024年 | 約50局 | 一部若手棋士が使用、主流からは外れる傾向 |
確かにピーク時よりは減少していますが、それでも一定数の採用があり、決して「完全に終わった」とは言えない状況です。
ゴキゲン中飛車の最新定跡とは?
現在でも研究は続いており、最新の定跡では角交換型の変化や後手番での工夫などが注目されています。
【最新定跡のポイント】
- 角道オープン型 vs 超速銀
→ 中央の戦いを意識し、早めに玉を囲う形 - △4二銀〜△5三銀〜△6四歩型
→ 柔軟な構えから先手の急戦を受ける - △3三角保留型
→ 相手の出方を見て角を引くタイミングを調整
また、最近ではAIによって評価が見直される変化もあり、細かな工夫で対抗する動きが再び注目されているのです。
藤井聡太やトップ棋士は使っている?
藤井聡太竜王・名人は基本的に居飛車党ですが、若手時代にはゴキゲン中飛車を指していた時期もあります。
現在でも、以下のようなトップ棋士たちがゴキゲン中飛車を採用することがあります。
【最近ゴキゲン中飛車を採用した例】
| 棋士 | 採用例 | 備考 |
| 糸谷哲郎 | 2023年王座戦予選 | ▲超速銀に対し柔軟に対応 |
| 菅井竜也 | 2022年竜王戦 | 対▲居飛車穴熊戦で使用 |
| 藤井猛 | YouTubeやイベントで研究継続中 | 実戦でも指す |
このように、現代でも通用する戦法として認識されていることは間違いありません。
「終わった」は誤解?再評価される可能性も
AI時代により「評価値が悪い」と言われがちなゴキゲン中飛車ですが、評価値と実戦の勝率は一致しないことも多々あります。
実際、以下のような再評価も進んでいます。
【ゴキゲン中飛車が再評価される理由】
- 実戦向きの構えでアマチュアにも使いやすい
- 美濃囲いとの相性が良く、初心者にも安定
- 定跡型を崩せば「知らない変化」に持ち込みやすい
こうした特徴から、特に早指しの将棋やアマチュア同士の対局では依然として強力な武器なのです。
ゴキゲン中飛車は本当に終わったのか?【結論】
結論としては、「終わったわけではないが、主流ではなくなった」という表現が最も正確でしょう。
【まとめ】
- プロ間では使用率は減ったが、一定の支持は残る
- 定跡が研究され尽くした分、工夫の余地が必要
- AI時代でも実戦で使える戦法として生き続けている
初心者やアマチュアにとっては、今なおゴキゲン中飛車は有力な武器の一つであることに変わりありません。
将棋の中飛車の攻め方と覚えることまとめ【初心者向け】
将棋の「中飛車」は、攻め重視の戦法として多くのファンを持ちます。
特に、戦法の目的や組み方がシンプルなため、初心者にも取り組みやすいという大きなメリットがあります。
この章では、中飛車の基本的な攻め方や、初心者が覚えておくべきポイントを、図表も交えてわかりやすく解説していきます。
中飛車の攻め方の基本パターン
中飛車はその名のとおり、飛車を5筋(中央)に展開する戦法です。
ここから「中央突破」や「左翼展開」を狙うのが王道の攻め筋です。
【基本の攻め方の流れ】
- 飛車を5筋に配置(△5四飛)
- 美濃囲いなどで玉を安全に囲う
- 銀や角を展開して5筋~6筋の突破を狙う
- 相手の急戦に注意しながら機を見て仕掛け
初心者がよく陥るミスは、囲いが不完全なまま攻めてしまうことです。
「囲ってから攻める」が鉄則です。
仕掛けのタイミングと形の目安
中飛車で仕掛けるタイミングは、飛車の後ろに銀・角が揃ってサポートできる形が理想です。
【仕掛けの目安となる形】
| 図形 | 解説 |
| 飛車が5筋に、左銀が5三(or 4四)に配置 | 中央突破しやすい基本形 |
| 角が7四に出て飛車を支援 | 角交換後の攻めが強力 |
| △6四歩突きが済んでいる | 左銀と連携しやすくなる |
こうした形が整っている場合、▲5五歩や▲5四歩の仕掛けを検討するタイミングです。
覚えるべき基本定跡3選【初心者向け】
初心者がまず覚えるべき中飛車の定跡を3つ紹介します。
これらはアマチュアの対局で非常によく登場する形です。
【中飛車の定跡一覧】
| 定跡名 | 概要 | 対応戦型 |
| ゴキゲン中飛車 | 角道を開ける積極的中飛車 | 超速▲3七銀など急戦型 |
| ノーマル中飛車 | 角道を閉じてじっくり組む | 急戦や持久戦どちらも対応 |
| 石田流転換型 | ▲5八飛→▲7六飛と展開 | 対居飛車・振り飛車両方に有効 |
特に最初は「ノーマル中飛車」から入り、形を覚えると他の変化にもスムーズに対応できます。
対振り飛車における中飛車の扱い方
相手も振り飛車(四間飛車・三間飛車など)を選んできた場合、中飛車同士の「相振り飛車」となります。
このときは、相手の飛車の位置を見ながら柔軟に対応することが重要です。
【相振り飛車での中飛車のコツ】
- 飛車を真ん中(5筋)に据えてバランスよく構える
- 美濃囲い同士の競り合いになることが多い
- 銀の使い方で攻めの形が決まる(△5三銀~△4四銀など)
中飛車は相振りでも中央支配力が高いため、角の働きや飛車の回転を意識すると有利に立てます。
初心者がやりがちなミスとその対策
最後に、中飛車初心者が陥りやすい失敗と、その対策方法を紹介します。
【初心者のミスと対策】
| ミス | 原因 | 対策方法 |
| 玉を囲う前に攻める | 美濃囲い未完成のまま仕掛け | まず囲いを完成させてから |
| 飛車が孤立する | 銀や角の展開が遅い | 銀→角→飛車の順に攻め準備 |
| 相手の急戦に対応できない | 定跡を知らない | 超速▲3七銀などの対策を学ぶ |
このように、攻め急ぎや構え不足が最大のリスクです。定跡を学ぶことでそれらを防げます。
中飛車の攻め方・覚えることまとめ
最後に、本セクションの内容をまとめておきます。
【中飛車の基本ポイントまとめ】
- 中央から攻めるため、囲いと攻めの形をしっかり整える
- 銀・角の展開でタイミングを見て仕掛け
- 美濃囲いとの相性が抜群で初心者にもおすすめ
- 定跡を理解することで急戦や相振りにも対応可能
中飛車は形を覚えればすぐに実戦投入できる実践的な戦法です。特にアマチュアや早指しの実戦ではその威力を発揮します。
将棋の中飛車を学べる本・動画・棋譜・棋書まとめ
中飛車を使いこなすには、実戦経験とともに、信頼できる教材を通じた学習が欠かせません。
このセクションでは、「本・動画・棋譜・アプリ」などさまざまな手段で中飛車を学ぶ方法をまとめて紹介します。
中飛車・ゴキゲン中飛車の定跡本おすすめ3選
まずは体系的に学ぶなら、やはり定跡書が最適です。
以下に初心者〜中級者におすすめできる中飛車関連の将棋本を紹介します。
【おすすめの中飛車本3選】
| 書籍名 | 著者 | 特徴 | 対象レベル |
| ゴキゲン中飛車戦法 | 藤井猛 | ゴキゲン中飛車の創始者による解説。思想が学べる | 初〜中級者 |
| 最新戦法マル秘定跡ファイル | 週刊将棋編集部 | 中飛車を含めた最新定跡を解説 | 中級者向け |
| 羽生善治の定跡講座 中飛車編 | 羽生善治 | 対中飛車の対策にも対応。両視点から学べる | 初級者 |
特に藤井猛九段の著作は、中飛車の思想と戦略が体系的に学べるため、最初の一冊に最適です。
プロの棋譜を使った学習法
次におすすめしたいのは、実際のプロ棋士が使った中飛車の棋譜を並べて学ぶ方法です。
AI解析も加えれば、効率的な実力向上が期待できます。
【棋譜学習のステップ】
- 中飛車党の棋士(藤井猛、佐藤天彦など)の対局を探す
- 序盤の型、飛車・銀・角の動かし方を観察
- 定跡に沿った進行か?独自手順か?をチェック
- 詰みまで並べて終盤力も同時に磨く
棋譜は「将棋DB2」「将棋ウォーズの棋譜再生機能」「ABEMA将棋チャンネル」などでも簡単に閲覧可能です。
YouTubeやアプリで学べる無料講座も紹介
動画で学びたい方には、YouTubeやスマホアプリも強い味方になります。
【おすすめYouTubeチャンネル】
- 将棋放浪記(藤森哲也五段):中飛車講座も豊富
- 元奨励会員アゲアゲ将棋実況:アマトップクラスの対局・中飛車解説あり
- 日本将棋連盟公式:プロによる中飛車講座や解説動画が随時公開
【スマホアプリ】
| アプリ名 | 特徴 |
| 将棋ウォーズ | 中飛車の対局を自分でも指せて記録も残る |
| 将棋クエスト | 中飛車党のユーザーも多く、定跡学習に使える |
| 将棋アプリ 将皇(しょうおう) | 定跡や詰将棋が学べる無料アプリ |
書籍+動画+実戦を組み合わせれば、中飛車の理解が飛躍的に深まります。
の将棋中飛車の歴史と有名棋士たちの採用例
中飛車は長い歴史を持ち、時代ごとに形を変えながら発展してきました。
この章では、中飛車の起源や進化、そして有名棋士たちの採用例を通じて、その魅力と影響力を掘り下げていきます。
中飛車の起源と進化|古典から現代へ
中飛車の起源は江戸時代にまで遡るとされており、当時の指し方は現代のような体系的な定跡は確立していませんでした。
【中飛車の歴史的な流れ】
| 時代 | 概要 |
| 江戸時代 | 自由な発想で指される「遊びの戦法」として認知されていた |
| 昭和 | 大山康晴・升田幸三などが対振り飛車用に実戦採用 |
| 平成 | 藤井猛が「ゴキゲン中飛車」を開発し、プロ間で大流行 |
| 令和 | AI研究を背景に再評価。最新定跡と組み合わせた新戦法が誕生 |
特に藤井猛九段の登場以降、「中飛車=攻撃的な戦法」というイメージが強くなり、定跡の刷新も進みました。
藤井猛・佐藤天彦など使用棋士の実例
プロ棋士の間でも中飛車を好んで用いる棋士は少なくありません。
以下に代表的な棋士と特徴をまとめます。
【中飛車党の代表棋士】
| 棋士名 | 採用形 | 特徴 |
| 藤井猛九段 | ゴキゲン中飛車 | 定跡革命。「藤井システム」考案者でもあり攻撃的 |
| 佐藤天彦九段 | ノーマル中飛車・角交換型 | 研究型。柔軟な構想力で中飛車を現代風にアレンジ |
| 永瀬拓矢九段 | 対抗形の選択肢として | AIを活用した準備力。中飛車を状況に応じて採用 |
中飛車は序盤から主導権を握る戦法であるため、「自分から攻めたいタイプの棋士」に好まれる傾向があります。
中飛車が将棋界に与えた影響とは?
中飛車は将棋界に多大な影響を与えた戦法の一つです。
藤井システムの登場以降、戦法全体のバランスに変化をもたらしました。
【将棋界への影響まとめ】
- 定跡革命の引き金に:藤井猛のゴキゲン中飛車が従来の定跡を破壊
- 振り飛車復権の象徴:一時期「不利」とされた振り飛車の価値が見直された
- プロ vs アマの戦型にも変化:アマでも扱いやすく、上級者との対局でも通用する戦法に
また、「ゴキゲン中飛車」は今も進化を続けており、AIを使った最新研究が積極的に行われています。
まとめ|将棋の中飛車・ゴキゲン中飛車を使いこなすコツ
将棋の中飛車やゴキゲン中飛車は、攻めの主導権を握りやすく、形も比較的覚えやすいため、初心者から上級者まで幅広く人気があります。
この章では、中飛車戦法を実戦で活かすためのコツをわかりやすく解説します。
初級者が覚えるべき型と攻防のバランス
中飛車を覚えたての方にとって、最初に意識すべきなのは「陣形のバランス」です。
飛車を3筋に振るだけでなく、囲いと攻め筋を連動させる感覚が重要になります。
初心者が意識すべき基本ポイント
- 美濃囲いを優先的に組む(バランス型)
- ▲5七銀→▲6六銀(銀の連携で攻める形)
- 無理攻めせず、玉の安全を確認してから攻撃
| 囲い | 特徴 |
| 美濃囲い | 振り飛車の基本囲い。バランスよく攻守に優れる |
| 高美濃囲い | 美濃より強固だが、攻撃に転じにくくなる点も |
「攻める前に囲う」が中飛車成功の鍵です。
対策・定跡・最新研究までチェックしよう
現代将棋では、研究と準備が勝率に直結します。
中飛車にもさまざまな定跡と対策が存在するため、敵の狙いを知っておくことが重要です。
チェックしておきたい項目
- 相手が居飛車党の場合の急戦策
- 左銀を活用した「銀対抗型」
- 角交換型中飛車の研究
また、最新のAI研究を取り入れた藤井猛の研究動画や、将棋ウォーズ・将棋倶楽部24の実戦データも有効です。
自分の将棋スタイルに合った型を見つけよう
中飛車といっても、人によって合う型・合わない型があります。
ゴキゲン中飛車のように積極的に攻めるタイプが合う人もいれば、角交換型中飛車のようにバランス重視が向く人もいます。
スタイル別おすすめ型
| スタイル | おすすめ中飛車戦法 |
| 攻撃型 | ゴキゲン中飛車、藤井システム |
| 守備型 | 角交換型中飛車+高美濃囲い |
| バランス型 | ノーマル中飛車+舟囲い |
まずは実戦でいろいろ試し、自分にとって「勝ちやすい型」を見つけるのが上達の近道です。
まとめ
- 中飛車は初心者でも扱いやすく、囲いと攻撃のバランスが重要
- ゴキゲン中飛車はプロでも愛用される現代的な戦法
- 棋譜やYouTubeなどで最新研究を学ぶことが勝率アップにつながる
- 自分のスタイルに合った中飛車を見つけて、安定した戦績を目指そう


将棋の三間飛車とはどんな戦法?石田流との違い・組み方・対策まで徹底解説