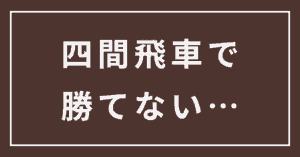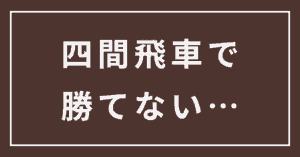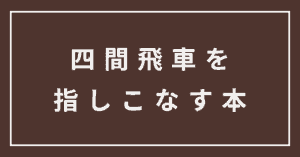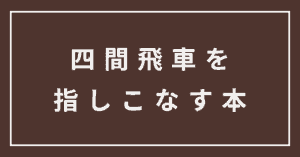四間飛車は安定した守りと柔軟な攻めを両立できる優秀な戦法ですが、「棒銀」に弱いという弱点があることでも知られています。
特に美濃囲いを完成する前に飛車先を突破されてしまうと、対処が難しく、あっという間に形勢が傾いてしまうことも。
そこで本記事では、「四間飛車 棒銀対策」をテーマに、相手の攻め筋の狙いから具体的な受け方、実戦で使える応用テクニック、さらに学習に役立つ書籍や動画までを体系的に解説します。
これを読めば、棒銀におびえることなく自信を持って四間飛車を指しこなせるようになります。
将棋の戦法一覧|初心者向けから最強戦法・奇襲型まで完全解説!


◆アプリダウンロード数4,000万突破!


将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、
【 ABEMA
プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。
>> 将棋見るならABEMA
四間飛車に対する棒銀とは?|どんな攻め筋かを把握しよう
四間飛車を指す上でよく遭遇するのが「棒銀」での攻めです。
まずはこの戦法の基本的な意図と、なぜ四間飛車にとって脅威となるのかを理解しておきましょう。
棒銀とは?基本の攻め筋を理解しよう
棒銀(ぼうぎん)は、飛車の前を空けて銀を真っ直ぐ前進させるシンプルな攻めの形です。
特に居飛車で採用されやすく、飛車と銀を縦に並べて一直線に突進するスタイルが特徴です。
▶ 棒銀の基本構成
| 駒の配置 | 目的 |
| 飛車が2筋(先手)または8筋(後手) | 飛車先から突破を図る |
| 銀を3七→4六→4五→4四へ進める | 障害を排除し突破口を開く |
| 歩や角でサポートする | 攻めの連携を保つ |
このように、飛車先の歩を交換し、銀で橋頭堡(きょうとうほ)を築いて突破してくるのが棒銀の基本戦術です。
なぜ棒銀は四間飛車に有効なのか?
棒銀は四間飛車の構造上の弱点を的確に突いてきます。
特に玉が右に寄って囲いを構築している間、左側(飛車のいない側)が手薄になりやすいため、そこを狙われやすいのです。
▶ 棒銀が有効な理由
- 美濃囲いの完成前に仕掛けられると受けが間に合わない
- 四間飛車の飛車が左側を守りづらい
- 銀をうまくさばかれると反撃の手が難しくなる
そのため、棒銀は「形が整う前に仕掛けたい」四間飛車対策として非常に理にかなった戦法といえます。
よくある失敗例|こう受けると崩される
棒銀に対して受け方を間違えると、形勢が一気に悪化します。
以下は、特に四間飛車側がやってしまいがちなNG対応です。
失敗例1:美濃囲いに夢中で棒銀を放置
→ 囲いの完成ばかり意識して相手の銀の前進を許すと、飛車先を突破されてしまいます。
失敗例2:角交換にすぐ応じる
→ 無理な角交換をすると、打ち込みの隙を与え、自陣が混乱します。
失敗例3:飛車を動かさず静観
→ 攻め筋を変える準備をせずに静観すると、突破を許して防戦一方になります。
こうした例からもわかるように、棒銀を甘く見ると一気に主導権を握られてしまいます。
【ポイントまとめ】
棒銀は攻め筋が単純で覚えやすい反面、四間飛車にとっては非常に危険な戦法です。
特に囲いが未完成の段階での仕掛けには細心の注意が必要です。
四間飛車での棒銀対策|有効な受け方と手順
棒銀の攻めに対して、四間飛車側も定跡的な受け方や応用手筋を知っておく必要があります。
ここでは主に四間飛車側が取れる代表的な受けの構えと狙いを解説していきます。
6五歩の早突きで角交換を仕掛ける
四間飛車対棒銀戦で多く使われる代表的な対策の一つが「6五歩」の早突きです。
これは相手が棒銀で攻めてくる前に、角交換をこちらから仕掛けて主導権を握る狙いがあります。
▶ 6五歩の仕組みと狙い
| タイミング | 意図 |
| 相手が3四歩〜4四銀と棒銀に組む前 | 自分から角交換を仕掛ける |
| 6五歩と突くことで角道を開く | 相手が対応を迫られる |
| 角を交換し、5四角打ちなどの反撃が可能に | 銀を前進させづらくする |
これにより、棒銀の銀を進める余裕を奪い、相手の攻めのリズムを崩せる可能性が高まります。
▶ 注意点
・角交換後の打ち込みには細心の注意を払いましょう。
・玉が中央寄り(居玉や簡易囲い)だと打ち込みに弱くなります。
角を引いて飛車先を軽くする構え
棒銀は飛車先の突破が要です。
逆に言えば、こちらが「飛車先を軽く」しておけば、攻めが不発に終わる可能性も高くなります。
そこで有効なのが、角を引く構えです。
▶ 具体的な手順
- 四間飛車の角を7七から6八に引く
- 角の利きで飛車先の守りを強化
- 同時に、5九銀や6八銀で角打ちのスペースを消す
| 駒の位置 | 意図 |
| 角を6八に引く | 飛車先を守る/打ち込みを防ぐ |
| 飛車を6八→6七にスライド | 攻めのスペースを制限 |
このように、角を下げて守備に使うと棒銀は簡単には崩せません。
飛車を回して相手の攻め筋を分断する
棒銀は縦一直線の攻めです。つまり、銀の前進ルート(2筋や8筋)を妨害できれば、機能しにくくなります。
そこで、途中で飛車を振り直して相手の攻め筋にプレッシャーをかけるのも一つの対策です。
▶ 振り直しの例:四間→三間→右四間
| 手順 | 解説 |
| 7六歩〜7七銀で右四間に組む | 右側でプレッシャーを与える |
| 相手の銀進出を誘導し、カウンター狙い | 角の利きも生かせる |
| 攻めと守りの両立が可能になる | 四間の柔軟性を活用する |
この手法は特に、相手が早仕掛け棒銀を狙っているときに有効です。
囲いをしっかり整えてから受ける構え
急戦棒銀に焦って受けに回るのではなく、まずは玉を囲ってしっかり守るというのも重要な考え方です。
四間飛車では「美濃囲い」が基本となりますが、状況によっては「高美濃」や「銀冠」に発展させることで耐久力が増します。
▶ 美濃囲い→高美濃・銀冠の進化例
| 囲い | 特徴 | 耐久度 |
| 美濃囲い | 初期の安定形 | ★★★☆☆ |
| 高美濃囲い | 上部に強い | ★★★★☆ |
| 銀冠 | 端攻め・棒銀に強い | ★★★★★ |
しっかりとした囲いがあることで、多少攻められても冷静に反撃する余裕が生まれます。
【ポイントまとめ】
- 「6五歩」などの角交換で主導権を握るのは有効な戦術。
- 飛車先を軽くする・角を引くことで受けやすくなる。
- 飛車の振り直しで相手の攻め筋を崩す柔軟性も大事。
- 囲いを高美濃や銀冠に進化させて耐久力を上げよう。
実戦に役立つ棒銀対策の応用テクニック
基本の対策を身につけたら、さらに実戦的な応用テクニックを習得することで、勝率が大きく向上します。
ここでは棒銀に対する具体的な受けの工夫やタイミングについて詳しく見ていきましょう。
先手と後手で変わる受けのコツ
先手と後手では序盤の主導権の取り方が異なります。
そのため、同じ四間飛車であっても棒銀への受け方に違いが出てきます。
▶ 先手四間飛車の場合(△が棒銀)
| 対応方法 | 理由 |
| △4四銀型を見たら▲6五歩を検討 | 相手の銀が動く前に主導権を握れる |
| 角交換後の5四角や7四歩の反撃 | 手厚いカウンターが狙える |
| 美濃囲いを早めに構築 | 攻められても耐えられる体制を作る |
▶ 後手四間飛車の場合(▲が棒銀)
| 対応方法 | 理由 |
| 早めの6五歩で角交換誘導 | 主導権を放棄しない戦い方 |
| 銀を5三・6二に備えて待機 | 急戦を受け止めやすくなる |
| 高美濃への早い移行で守備固め | 角の打ち込み対策も兼ねる |
このように、先手後手によって受け方を変える柔軟性が必要です。
棒銀を逆手に取って反撃するタイミング
棒銀は飛車と銀を縦に並べるため、攻めが単調になりやすく、読みやすいという弱点もあります。
これを逆手に取って反撃のタイミングを見極めましょう。
▶ 反撃タイミングの目安
- 相手の飛車先交換を受けずに保留している場合
- 相手の銀が2五や8五など前進した直後
- 飛車先突破を狙っているが、囲いが未完成の時
上記のようなタイミングでこちらが角交換→飛車先カウンター→飛車成りなどを狙えば、逆に相手が受けに回らざるを得ない展開になります。
▶ 有効な反撃手筋
| 手筋 | 解説 |
| 飛車を中央に展開 | 攻め筋を変えて混乱を誘う |
| 桂馬を使った両取り | 棒銀は横に弱いため有効 |
| 飛車成りによる先攻 | 先にと金を作ることで優位に |
攻めを受けるだけでなく、「攻めさせて反撃する」姿勢が大切です。
定跡崩しに強くなる!研究例と実例紹介
定跡通りに受けていても、相手が研究してきた変化球にはまってしまうこともあります。
そこで重要なのが、研究例を知っておくことと実戦譜を学ぶことです。
▶ 定跡崩しの例(四間飛車側)
| 変化 | 内容 | 有効な対応 |
| ▲3五歩早仕掛け | 角交換拒否から速攻 | △6四歩で角道を確保し反撃 |
| 銀が2四→3五→4六 | 棒銀を途中から変更 | 囲い完成まで無理に応じない |
| ▲5五角打ち | 振り飛車側の隙を狙う | 飛車位置を調整し角をいなす |
こうした変化にも対応するために、プロの実戦譜や有段者のネット将棋を見て学ぶのが効果的です。
▶ 学びのポイント
- 棒銀対策の定跡をベースに、自分なりの工夫を加える
- 1つの対策に頼らず、複数の引き出しを持つ
- 「失敗した実戦」こそ、成長のヒントになる
【チェックリスト】実戦での棒銀対策まとめ
以下は実戦で棒銀に直面した際、意識しておきたいポイントのチェックリストです。
| チェック項目 | 確認済み? |
| 囲いが完成しているか? | □ |
| 角の利きで飛車先を守れているか? | □ |
| 相手の銀が前に出た瞬間を狙えているか? | □ |
| 飛車を振り直す手を検討したか? | □ |
| 6五歩など角交換を狙えるか? | □ |
すべてにチェックが入るような将棋を目指すことで、棒銀に強くなれます。
次のセクションでは、おすすめの書籍や動画など、四間飛車の棒銀対策を学べる教材を紹介していきます。
継続的に学びたい方はぜひ参考にしてください。
四間飛車で棒銀対策を学べる本・動画まとめ
棒銀対策をより深く理解し実戦で活かすには、良質な教材に触れることが近道です。
ここでは、書籍・YouTube・プロの実戦譜など、信頼できる学習コンテンツを紹介します。
初心者におすすめの定跡書・入門書
棒銀対策の基本から学びたい方にとって、定跡書や入門書は非常に心強い味方です。
以下に初心者でもわかりやすく、かつ四間飛車視点で学べる書籍を紹介します。
▶ おすすめ書籍一覧(四間飛車 vs 棒銀対応)
| 書籍名 | 著者 | 特徴 |
| 四間飛車を指しこなす本(1〜3巻) | 藤井猛 | 棒銀対策に多くのページを割いている名著。変化も網羅。 |
| 四間飛車破り【急戦編】 | 所司和晴 | 相手が棒銀で攻めてくる際の対応が中心。四間側の視点で読める。 |
| 四間飛車の急所 | 藤井猛 | 1手ごとの意味が丁寧に解説されており、受け方の勉強になる。 |
これらの書籍は【電子書籍版】もあるため、スマホやタブレットでも手軽に学べます。
▶ 書籍選びのポイント
- 「定跡本」よりも「講座形式」のものがおすすめ(初心者向け)
- 筋の解説だけでなく「なぜその手が有効なのか」が書かれているか確認
- 棒銀に限らず、四間飛車全体の考え方も学べる本を選ぶと応用が効く
初心者が1冊選ぶなら、やはり定番の「四間飛車を指しこなす本」シリーズがおすすめです。
YouTubeのおすすめ講座・解説動画
最近では、動画で学べる将棋講座が数多く登場しており、棒銀対策も無料で学べる時代です。
以下は特に四間飛車vs棒銀に特化した良質な解説動画です。
▶ おすすめYouTubeチャンネルと講座
| チャンネル名 | 解説者 | 特徴 |
| 元奨励会員アゲアゲ将棋実況 | アゲアゲさん | 実戦形式で四間vs棒銀を実況解説。初心者に人気。 |
| 将棋放浪記 | プロ棋士藤森哲也五段 | 丁寧な口調で解説。棒銀の崩し方・受け方が明快。 |
| 渡辺明チャンネル(公式) | 渡辺明九段 | プロの視点での受けや対応がわかる。四間飛車寄りの動画も多数。 |
▶ 動画学習のメリット
- 手順と盤面が同時に見られるため、理解が速い
- 再生速度を変えられるので復習がしやすい
- 実戦形式の動画は「どの場面でどんな選択肢があるか」を学べる
特に「将棋放浪記」のような実践解説は、指しながら学ぶ実践型プレイヤーに最適です。
プロの実戦譜から学ぶ受けの技術
プロ棋士の実戦譜には、棒銀への高度な対応手順が詰まっています。
ここでは、四間飛車で棒銀に勝った有名な実戦例を紹介します。
▶ 学ぶべき実戦譜(四間飛車で棒銀を撃退)
| 棋戦 | 対局者(先手 vs 後手) | ポイント |
| 棋王戦(2022年) | 藤井猛 vs 谷川浩司 | 棒銀に対し6五歩から角交換→反撃が炸裂 |
| NHK杯(2021年) | 佐藤康光 vs 菅井竜也 | 菅井四間飛車が受けて→飛車振り直しで主導権奪取 |
| 王座戦(2023年) | 近藤誠也 vs 久保利明 | 久保流・高美濃囲い+6四歩のタイミングが秀逸 |
これらは将棋DBやYouTubeで棋譜並べが可能です。観戦時は「どのような構えで、どう受けたか」を意識しましょう。
▶ 実戦譜の学び方のコツ
- 序盤〜中盤に注目し、「棒銀にどう備えたか」をチェック
- 受ける手と反撃のタイミングをセットで覚える
- 同じような形を複数並べて比較するとパターンが見える
実戦譜を10局並べるだけでも、受けのセンスは確実に上がります。
このように、書籍・動画・実戦譜の3方向から学ぶことで、棒銀対策の理解が格段に深まります。
次のセクションでは、これまでの内容をまとめて整理し、さらに他の記事との連携も提案します。
まとめ|棒銀対策で四間飛車をさらに強くしよう
ここまで、四間飛車に対する棒銀の基本から具体的な対策、教材まで幅広く解説してきました。
最後におさらいとして、重要なポイントを振り返りましょう。
棒銀に強くなると四間飛車はさらに使いやすくなる
四間飛車の天敵とも言える「棒銀」に対応できるようになると、四間飛車は非常に安定感のある戦法になります。
なぜなら、棒銀は四間飛車側が最も警戒すべき急戦の代表格だからです。
棒銀に対応できると得られるメリット
- 四間飛車に自信を持って指せるようになる
- 他の急戦(▲4五歩早仕掛けなど)にも応用が効く
- 囲いの整備や受けの基本感覚が自然に身につく
特にアマチュア間の対局では、棒銀を仕掛けてくる相手は多いため、対策しておくことは勝率アップに直結します。
受けの経験値を積むことが上達への近道
棒銀対策のような「受けの構え方」は、定跡暗記だけでは対応しきれない場合もあります。局面ごとの応用力や判断力が問われるため、実戦経験を積むことが非常に重要です。
受けを鍛えるためのおすすめ方法
- 実戦対局(将棋ウォーズや81dojoなど)で四間飛車を使い続ける
- 棋譜並べで受けのバリエーションを蓄積する
- 自分の失敗局面を振り返って「次はどう指すか」を考える習慣を持つ
こうした取り組みは、**棒銀対策だけでなく将棋全体の「守りの力」**を養うことにもつながります。
他の対策記事・囲い記事もあわせてチェック!
棒銀対策は四間飛車の一部分に過ぎません。他にもさまざまな急戦や戦法に対応できるよう、以下の記事もあわせて学習することをおすすめします。
▶ 関連おすすめ記事一覧
| テーマ | 記事タイトル |
| 急戦対策 | 四間飛車 4五歩早仕掛け対策【完全ガイド】 |
| 囲い研究 | 美濃囲いの崩し方と強化法【基本から応用まで】 |
| 定跡理解 | 四間飛車 定跡まとめ|先手後手別おすすめ形 |
| 戦法比較 | 三間飛車 vs 四間飛車|違いと使い分けを解説 |
| 応用テク | 四間飛車で攻める!仕掛けのタイミングと読み筋 |
また、棒銀側から見た戦い方を知ることも、受けの理解を深める大きな助けになります。
■ 今後のステップとして
- 書籍や動画で棒銀の攻め筋を「受けの視点」で復習
- 実戦での反復練習を通じて自分の型を固める
- 他の急戦・囲いにも対応できるよう学びを広げる
四間飛車は「守りが固く、柔軟に対応できる戦法」です。
棒銀という代表的な急戦をしっかり受け切れるようになれば、あとは自分の土俵でじっくり戦うことができます。
今後も当サイトでは、四間飛車や振り飛車を中心に「勝つための具体的な定跡・対策」を丁寧に解説していきますので、ぜひブックマークや他記事もご活用ください!