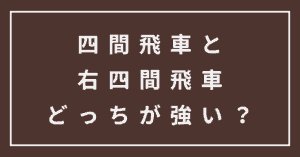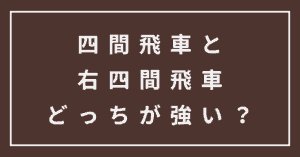四間飛車を指しているのに、なかなか勝てない。そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。振り飛車の代表格とも言える四間飛車は、守りが堅く、攻めのバランスも取れている魅力的な戦法ですが、実は「勝てない」「通用しない」と感じている将棋ファンも少なくありません。
本記事では、なぜ四間飛車で勝てないのかという根本的な疑問に対し、よくある敗因パターンや対策、そして勝率を上げるための改善方法を丁寧に解説していきます。さらに、居飛車穴熊や急戦型など、特定の戦法に対する弱点にも踏み込み、実戦的な対処法を紹介。
四間飛車を諦めたくない方も、これから見直したいと考えている方も、この記事を読むことで、自信を持って再び盤上に向かえるようになるはずです。
将棋の戦法一覧|初心者向けから最強戦法・奇襲型まで完全解説!


◆アプリダウンロード数4,000万突破!


将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、
【 ABEMA
プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。
>> 将棋見るならABEMA
四間飛車で勝てないと感じる理由とは?
四間飛車は初心者にも人気の高い戦法ですが、勝てないと感じる局面にはいくつか共通点があります。まずは「なぜ勝てないのか」を正しく理解することが、上達への第一歩です。
定跡を知らずに指している
四間飛車は柔軟で自由度が高い戦法ですが、基礎となる定跡を知らずに指すと、相手の急戦や穴熊に対応できずに不利を招きがちです。特に居飛車党の相手は、四間飛車対策に習熟している場合が多く、定跡を知らずに我流で指していると、あっという間に劣勢になることも。
たとえば、▲7六歩 △3四歩 ▲6六歩 △8四歩 のように進行する中で、四間飛車に構えた後の銀の運用(=銀の繰り出し方)や、美濃囲いの組み方、端歩の受け方などを理解していないと、相手の攻撃にうまく対応できません。
定跡とは“相手も知っている前提の道”。その道の途中で手を間違えれば、すぐに不利になります。
受けの感覚が足りない
四間飛車は受けてから反撃するタイプの戦法です。したがって、終始攻めに回ることが得意なプレイヤーには向かない場合があります。序盤で受け損なったり、受けるべきところで無理に攻めたりすると、形勢が一気に悪化します。
特に居飛車穴熊相手の場合、攻めあぐねている間に自玉が堅さで劣ってしまい、反撃されて逆転されることがよくあります。
そのため、勝つためには「受けながら手を作る」「相手の急所を見極める」技術が必要です。単に攻めることに夢中になりすぎないようにしましょう。
序盤の組み方にムダがある
四間飛車は、美濃囲いを完成させてから攻撃態勢に入るのが基本ですが、この囲いの構築にムダな手があると損になります。たとえば、金銀の位置や玉の移動順、飛車先の歩の突き方など、わずかな手順の違いが後の展開に大きく影響します。
また、「銀冠」に発展させるのか、「高美濃」で止めて攻めに転じるのか、といった戦術的な判断も必要です。組み方が遅れたり、不自然な形になっていると、相手に先攻を許す原因になります。
手順の美しさは結果の勝敗に直結します。
対急戦への理解不足
四間飛車を指していると、相手が「急戦策」で崩しにくることがよくあります。たとえば、棒銀や舟囲いからの早仕掛け、右四間飛車などが代表的な急戦です。
これらの攻めに対して、正確な受け方を知らないと、序盤で一気に潰されるリスクがあります。四間飛車で勝てないと悩む多くの人が、**この「急戦対策不足」**に陥っています。
各急戦への基本的な対策を覚え、相手の動きに応じて最適な受けを選べるようになることで、勝率は大きく上がります。
相手の囲いによる相性差を理解していない
将棋には「戦法同士の相性」が存在します。たとえば、四間飛車は「居飛車穴熊」に対してやや不利だと言われています。これは守備力の差に加えて、攻撃のスピードや持久戦の強さに違いがあるためです。
このような戦型の相性を知らずに、苦手な相手にも四間飛車を続けてしまうことで、勝てない印象が強くなってしまうことがあります。
一時的に他の戦法に切り替えてみるのも、将棋を学ぶ上で有効です。
四間飛車が通用しないと言われる理由と誤解
「四間飛車はもう古い」「今の将棋では通用しない」といった声を耳にすることがありますが、それは本当なのでしょうか?ここではその根拠と、実際の実力者がどう評価しているかを見ていきましょう。
プロ棋界では使用率が低下している
実際、近年のプロ棋士の公式戦では、四間飛車の使用頻度は減少傾向にあります。AIの発達によって最善手が厳密に解析される中、四間飛車は居飛車側の対策が豊富になり、優位性を保ちづらくなったためです。
特に、居飛車穴熊や急戦策に対する対応が難しく、わずかな不備でリードを許してしまうため、リスクが高い戦法と見なされがちです。そのため、角交換型振り飛車(例:角交換四間飛車)や中飛車、三間飛車などに切り替えるプロ棋士も少なくありません。
ただし、これは“勝てない”のではなく、“リスク管理が難しい”という評価である点は重要です。
アマチュアレベルでは依然として有効
一方で、アマチュア将棋においては四間飛車は非常に有効な戦法です。理由は以下の通りです:
- 美濃囲いが堅くて覚えやすい
- 相手の急戦に対する受けを学べば、安定した戦いができる
- 攻守のバランスが良く、基本の習得に適している
特に10級〜初段程度のプレイヤーであれば、四間飛車の基本形をマスターするだけで安定した成績を出せることもあります。プロ棋士レベルの精密な対応力が求められるわけではないため、アマチュアにはむしろおすすめできる戦法といえるでしょう。
「通用しない」は思い込みか、定跡不足
「四間飛車が通用しない」と感じている人の多くは、定跡や受けの基本を知らずに指しているケースが多いです。たとえば、相手の右四間飛車に対しての構え、居飛車穴熊への攻め筋などを理解していないと、「勝てない=戦法が悪い」と感じてしまいがちです。
しかしこれは、どの戦法でも同じことであり、理解が浅い段階での敗戦を戦法のせいにしているに過ぎない場合が少なくありません。
四間飛車にも明確な勝ちパターンや優位に立つ構想があるため、それを理解すれば「通用する戦法」に変わります。
AI研究により新たな形も生まれている
AI研究が進んだことで、これまでにはなかった四間飛車の新しい構想も出てきています。たとえば、角交換型の四間飛車や、石田流とのハイブリッド、居飛車側の角筋を活かした柔軟な構えなど、旧来の四間飛車とは違う進化型も生まれています。
「四間飛車は時代遅れ」と言われる一方で、その中で変化しながら生き残る新しい四間飛車もあるのです。
こうした最新の知見を取り入れることで、あなたの四間飛車も格段に強化されるはずです。
四間飛車で勝つためのコツと実戦でのポイント
四間飛車はただ飛車を振るだけでは勝てません。定跡の理解と実戦での応用が不可欠です。ここでは、四間飛車で安定して勝てるようになるためのコツと、対局中に意識すべきポイントを解説します。
美濃囲いをしっかり完成させる
まず基本となるのが美濃囲いの完成です。四間飛車では、飛車を4筋に振ったあと、自陣をしっかりと囲って守る構えが重要になります。特に以下の形を目指すのが基本です:
▲6八玉 → ▲7八玉 → ▲7七銀 → ▲6八銀
▲5八金右 → ▲6八金 → ▲7八金
この構えにより、横からの攻撃にも強く、玉の逃げ道も確保しやすい形ができます。囲いが未完成のまま攻めると簡単に反撃を食らうため、まずはしっかり守りましょう。
急戦対策を覚えておくと勝率が上がる
居飛車側が急戦で攻めてくる場合、対策を知っているかどうかが明暗を分けます。代表的な急戦として以下のような戦法があります:
• 棒銀
• 右四間飛車
• 4五歩早仕掛け
これらに対する基本の受け方を知っておけば、序盤で不利にならずに済みます。たとえば右四間飛車に対しては、玉を早く囲い、銀を5七に上げてカウンターを狙うのが有効です。
急戦対策に特化した本やYouTube講座もあるので、自分の負けパターンを分析して重点的に学習しましょう。
角交換を恐れずに柔軟に対応する
相手によっては、序盤から角交換をしてプレッシャーをかけてくる場合もあります。ここで慌てずに、振り飛車側が持ち駒の角をどう使うかを冷静に考えることが重要です。
たとえば、相手の囲いが甘いと見たら、敵陣に打ち込む角打ちで一気に勝負を決めるチャンスもあります。角交換型四間飛車などの応用戦法を学ぶと、さらに戦略の幅が広がります。
持久戦になったときの攻め方を知っておく
相手が穴熊などの持久戦志向の場合、こちらも無理攻めを避けてじっくり組み立てる必要があります。このとき重要なのが、端攻めや銀冠などへの囲いの変化です。
攻めの基本としては以下の順がよく使われます:
1. 銀を中央から前進(5五銀型)
2. 飛車先を突いて交換
3. 角や金で攻めを連携
こうした持久戦における理想的な形を知っておくだけで、終盤の粘り強さが変わります。
四間飛車で勝てないときの改善方法と練習法
四間飛車を使ってもなかなか勝てない…という方には、いくつかの「改善ポイント」があります。単に手順を覚えるだけではなく、負け方の傾向を分析し、効果的な練習法を取り入れることが上達の近道です。
負けパターンを分析して対策を立てる
まずやるべきことは、自分の対局を振り返ることです。どの場面で形勢を損ねたのか、どんな攻めを受けて崩れたのかを振り返れば、自ずと克服すべきポイントが見えてきます。
たとえば以下のような敗因が多い場合:
- 美濃囲いが不完全なうちに攻め込まれる
- 急戦への対応が分からず混乱する
- 中盤以降の指し手に迷いが多い
→それぞれに対応した定跡学習・詰将棋・指し直しが有効です。負けを活かして成長する意識を持つだけで、学習の質は大きく変わります。
四間飛車の基本定跡を体系的に覚える
勝てない人の多くが、「四間飛車の定跡を断片的にしか覚えていない」状態です。体系的に学べば、序盤から自信を持って指せるようになります。
基本となる学習順:
- 美濃囲いの完成形とその変化形(銀冠・高美濃など)
- 棒銀・右四間など急戦型への対処
- 持久戦型での攻め筋(5筋攻めや端攻め)
これらを覚えることで、どのような展開にも対応しやすくなります。
📘おすすめ書籍:「四間飛車の急所」シリーズは体系的に学べる良書として有名です。
対局数を増やして経験値を積む
**知識だけでは勝てません。実戦経験が不可欠です。**将棋ウォーズや将棋クエスト、81道場などのオンライン対局サービスを活用しましょう。
ただし「数打てば当たる」ではなく、1局ごとに反省点をメモする・再現するなど、フィードバックを必ず取り入れるのがポイントです。
また、自分より少し強い相手と対局することで、無理攻めや形の崩れを実感し、改善しやすくなります。
プロ棋士の四間飛車を観戦して真似する
プロ棋士の対局には四間飛車の真髄が詰まっています。藤井聡太竜王も過去に四間飛車を採用しており、深い理解と準備のもとで指していることが分かります。
YouTubeや将棋連盟ライブ中継などを使い、四間飛車党の棋士の将棋を**並べてみる(棋譜再現)**のもおすすめです。
ポイント
- 銀の動かし方(早めに中央へ?守りに使う?)
- 角の活用タイミング
- 相手の囲いに合わせた攻めの柔軟性
など、プロの構想をそのまま自分の将棋に落とし込むだけで、勝率は確実に向上します。
まとめ|四間飛車は奥深く、工夫次第で必ず勝てる戦法
ありがとうございます。では続けて、記事の最終セクション【H2:まとめ|四間飛車は奥深く、工夫次第で必ず勝てる戦法】を執筆します。
四間飛車は一見シンプルに見えるものの、実は非常に奥深く、指す人の個性や工夫が生きる戦法です。勝てないと感じている方も、適切な学習と練習を続ければ、必ず成果が現れてきます。
以下のポイントを振り返りながら、四間飛車での上達を目指しましょう。
定跡理解と経験の積み重ねがカギ
四間飛車で勝つためには、基本定跡の理解と実戦での経験が何より大切です。序盤の型を覚えた上で、対急戦・持久戦・端攻めなどの対応力を養っていくと、自然と自信がついてきます。
序盤でリードされても、中盤以降に逆転できるのが振り飛車の強みでもあります。
自分に合ったスタイルを見つけよう
四間飛車には、柔らかく受ける指し方から積極的に反撃を狙うスタイルまで、幅広い指し方があります。
- 手堅く勝ちたい → 美濃囲い+カウンター重視型
- 攻めを楽しみたい → 急戦拒否型+銀冠で中央制圧
- プロ棋士の真似をしたい → 藤井システム・角交換型の研究
自分の性格や得意な展開に合わせて、四間飛車を“自分の型”にしていくことで、将棋の面白さがぐっと深まります。
四間飛車を学ぶ楽しさを忘れずに
「勝てないからやめよう」ではなく、「なぜ勝てないかを知る」ことが、四間飛車上達の第一歩です。
最近ではYouTube、電子書籍、アプリなど、学習環境も豊富です。ミシュラン級とも言える優良教材も多数あり、初心者から中級者まで学びやすい時代です。
四間飛車は「使いこなすほどに強くなる」戦法です。今は勝てなくても、続けることで必ず棋力向上につながります。諦めずに一歩ずつ、自分だけの四間飛車を育てていきましょう!
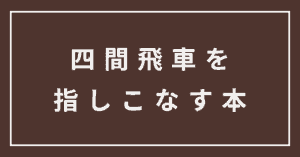
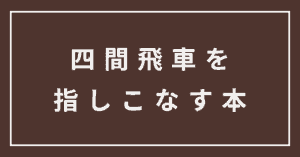
将棋の四間飛車と右四間飛車はどっちが強い?違いと特徴を徹底比較