「将棋を始めてみたいけど、何から覚えればいいの?」「ルールが難しそうで自信がない…」
そんなふうに感じている初心者の方も多いのではないでしょうか。
将棋は、日本で長く親しまれてきた伝統的なボードゲームでありながら、近年では藤井聡太竜王の活躍や将棋アプリの普及などにより、若い世代にも広く注目されています。しかし、いざ始めようと思っても「駒の動き方が覚えられない」「どう指していいかわからない」といった悩みが最初のハードルになることもあるでしょう。
この記事では、初心者の方でも安心して将棋を始められるように、「ルール」「駒の動き」「基本の戦法」から「練習方法」「おすすめ書籍・アプリ」まで、わかりやすく丁寧に解説します。この記事を読めば、今日からあなたも自信をもって将棋を指し始められるはずです。
◆アプリダウンロード数4,000万突破!


将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、
【 ABEMA
プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。
>> 将棋見るならABEMA
将棋とは何か?初心者が知っておくべき基礎知識
将棋は、二人で盤上に並べた駒を使い、相手の「王将(玉将)」を詰ませることで勝敗を決める、日本の伝統的なボードゲームです。囲碁やチェスと並ぶ知的ゲームとして世界でも評価されており、戦略的思考力や先を読む力を鍛えるのに最適です。
将棋盤は縦9×横9の計81マスで構成されており、各プレイヤーは20枚の駒を使って対局を行います。特徴的なのは「取った駒を自分の駒として使える」というルールで、これが将棋を奥深くしているポイントです。
将棋にはさまざまな魅力があります。たとえば…
- 頭の体操になる
- 一手の重みが深く、やりこみ要素がある
- 子どもから大人まで楽しめる
- SNSやアプリで気軽に対局できる
- 世界的なプロ棋士・藤井聡太のようなスター選手が注目されている
初心者でも将棋を理解するのに特別な知識は必要ありません。基本ルールを一度覚えれば、誰でもすぐにプレイできます。特に近年はスマホアプリや動画など、学びやすい環境が整っているため、これから始める人にとって非常に恵まれた時代といえるでしょう。
将棋のルールと駒の動かし方
将棋を始めるにあたって、まず覚えておきたいのが「ルール」と「駒の動き」です。将棋には以下の8種類の駒があり、それぞれに独自の動き方があります。
将棋の駒とその役割
| 駒の名前 | 初期枚数 | 動きの特徴 |
| 王将(玉将) | 1枚 | 1マスずつ全方向に動く |
| 飛車 | 1枚 | 縦・横に何マスでも動ける |
| 角行 | 1枚 | 斜めに何マスでも動ける |
| 金将 | 2枚 | 前・横・後ろ斜めに1マス |
| 銀将 | 2枚 | 前3方向・後ろ斜めに1マス |
| 桂馬 | 2枚 | 前方2マス+左右1マスの跳び駒 |
| 香車 | 2枚 | 前に何マスでも動ける |
| 歩兵 | 9枚 | 前に1マス |
※駒は進める方向や枚数がそれぞれ異なるため、最初は手元に駒の説明シートを置きながらプレイすると理解が進みます。
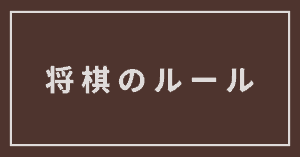
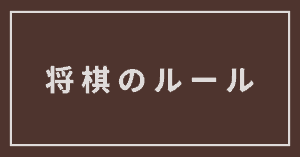
駒の成りとは?使い方と注意点
敵陣(相手から見て3段目)に駒が入ると「成る」ことができます。成ると駒の動きが強化され、攻撃力や守備力が向上します。
たとえば
- 歩 → と金(ほぼ金将の動き)
- 銀 → 成銀(金と同じ動き)
- 飛車 → 龍王(飛車+1マス斜め)
- 角行 → 龍馬(角+1マス縦横)
成るか成らないかは選択できますが、敵陣の奥深くに入り込んだ駒は、戻れない場合が多いので積極的に成るのがおすすめです。
将棋の駒の動かし方を完全解説|初心者でも図でわかる入門ガイド
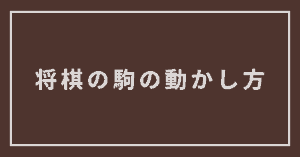
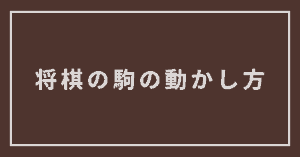
持ち駒ルールと打ち歩詰め
将棋の最大の特徴は「取った駒を自分の駒として使える」点です。これを「持ち駒」といい、自分の番で好きな場所に打つことができます(ただし以下のような制限あり):
- 歩は同じ列に2枚置けない(二歩禁止)
- 打ち歩詰めは禁止(歩で詰ますのは不可)
- 桂馬や香車は、打ってすぐ動けない場所には打てない
この持ち駒ルールが将棋における「逆転の要素」として非常に重要で、終盤戦の醍醐味を生み出しています。
実際に将棋を指してみよう!基本の流れと勝敗のつけ方
将棋は、駒を動かして相手の「王将(玉将)」を詰ませたほうが勝ち、というシンプルな勝利条件があります。ただ、初めて将棋を指す場合には「どこから始めて、どう進めるのか?」という流れが分かりにくいかもしれません。ここでは、実際に将棋を始めるための基本の進行手順と、勝敗がつくまでの流れをわかりやすく解説します。
将棋の初期配置と対局の始まり方
将棋盤は9×9マス。初期の駒の配置は、すべての駒がルールに従って自分側の3段に配置されています。
- 7最前列(段目):歩兵が1列に並ぶ(9枚)
- 8段目:左から2番目に角行、右から2番目に飛車
- 9段目):左から香・桂・銀・金・王・金・銀・桂・香
プレイヤーは交互に1手ずつ駒を動かしていきます。対局では、基本的に「先手・後手」に分かれて指しますが、ネット将棋では自動でランダムに決まる場合がほとんどです。
勝敗の決まり方と「詰み」の意味
将棋では、以下の条件で勝敗が決します:
- 相手の「玉(王)」を詰ませたら勝ち
- 相手が反則(例:二歩・打ち歩詰め)をしたら勝ち
- 連続王手による千日手や持将棋になった場合は引き分け
「詰み」とは、相手の王が次の手で必ず取られてしまう状態で、どこに逃げても助からない状況のこと。これが将棋のゴールです。
ちなみに、「詰み」ではなく「王手」の状態は、まだ勝ちではありません。相手が逃げる手を残している場合、王手は「ただの攻撃手段」です。
持ち時間と対局形式の違い
将棋にはいくつかの対局形式があります。
| 対局形式 | 特徴 |
| 持ち時間なし(秒読み) | 初心者向け。制限なしで考えられる |
| 10分+秒読み | アプリなどで主流の形式 |
| 1分将棋 | 一手に1分以内で指さなければならない |
| プロ棋戦形式 | 1時間〜数時間以上、戦略性重視の長時間戦 |
初心者はまず持ち時間なしで、ルールや駒の動きをゆっくり理解しながら指すのがおすすめです。
最初に覚えておきたい簡単な定跡(序盤の指し方)
序盤では、主に以下のような指し方が定番です。
- ▲7六歩(先手の歩を前に出す)
- △3四歩(後手の歩を出して角の道を開ける)
- ▲2六歩(飛車を活用する準備)
このように、自分の飛車や角を使いやすくする形を整えるのが序盤の目的です。「序盤=駒の開発」「中盤=戦い」「終盤=詰ませる準備」という流れを意識することが重要です。
初心者におすすめの戦法と囲い方
将棋には無数の戦法や囲い(玉の守り方)が存在しますが、初心者がいきなり全部を覚える必要はありません。まずは「自分に合ったシンプルな戦い方」と「安全に玉を守れる囲い方」を選ぶことで、勝率も楽しさも大きく向上します。
ここでは、初心者におすすめの戦法と囲い方を具体的に紹介します。
覚えておくべき基本の戦法2選|居飛車 vs 振り飛車
初心者がまず意識したいのは、自分が「居飛車党」か「振り飛車党」かを決めることです。
| 戦法 | 概要 | おすすめ度 |
| 居飛車 | 飛車を右側に置いて攻める正統派戦法。玉と飛車が近く守りやすい。 | ★★★★☆ |
| 振り飛車 | 飛車を左側に振って、玉と飛車を分離。自由度が高くバリエーション豊富。 | ★★★☆☆ |
初心者には居飛車のほうが動きがわかりやすく、基本を学ぶのに向いています。ただし、自由に指してみたい方には振り飛車も面白い選択です。
初心者向けの囲い3選|簡単・堅い・覚えやすい
囲いとは、自分の「玉将」を守るための陣形です。下記は特に初心者におすすめの囲いです。
- 舟囲い
最も基本的な囲い。駒の移動が少なく簡単に組める。 - 美濃囲い
振り飛車向けの堅い囲い。玉の逃げ道も確保しやすい。 - 矢倉囲い
居飛車向けの本格的な囲い。中〜上級者へのステップアップに。
※それぞれの囲いの詳細は、以下の記事で紹介しています。
▶ 美濃囲いとは?
▶ 舟囲いの組み方


棒銀戦法|攻撃を学ぶならまずコレ!
「棒銀(ぼうぎん)」は、銀をまっすぐ前に進めて攻撃する戦法です。
- 手順がシンプル
- 1枚の銀で相手陣形を崩せる可能性がある
- 相手の守備陣形(囲い)を突破しやすい
たとえば、序盤で ▲2六歩 → ▲2五歩 → ▲2四歩 → ▲3三角成 というような流れで相手陣を崩すのが基本的な棒銀の形です。
棒銀は、攻めの感覚をつかむためにも非常に良い教材になります。
囲いと戦法はセットで覚えよう
戦法と囲いはそれぞれ独立しているように見えて、実際には密接に関係しています。
| 戦法 | おすすめ囲い |
| 居飛車 | 矢倉囲い、舟囲い |
| 振り飛車 | 美濃囲い、高美濃、銀冠 |
自分の使いたい戦法を選び、それに対応した囲いをセットで覚えると、指しやすくなります。
将棋の戦法一覧|初心者向けから最強戦法・奇襲型まで完全解説!


将棋に役立つ無料アプリ・書籍・練習方法
将棋はただ指しているだけでは上達に時間がかかります。効果的に強くなるには、練習ツールや教材を活用することがとても重要です。
このセクションでは、初心者から中級者まで役立つ「アプリ」「書籍」「学習方法」をそれぞれ紹介します。
無料で始められる将棋アプリ3選【初心者向け】
スマホ1つで気軽に将棋が楽しめる時代。以下は、初心者に特におすすめの無料アプリです。
| アプリ名 | 特徴 | 対局形式 |
| 将棋ウォーズ | 全国のプレイヤーと1手30秒の早指し対局ができる | オンライン対局 |
| 将棋クエスト | ランキング形式で初心者も上達しやすい | オンライン対局 |
| あそんでまなべる将棋 | 駒の動かし方から丁寧に学べる学習特化型 | オフライン学習 |
どれも操作がわかりやすく、初心者でもすぐに使えます。「駒の動き」や「定跡の理解」に役立つモードも豊富に搭載されています。
初心者におすすめの将棋入門書2選
将棋の基本をしっかり学びたい方には書籍もおすすめです。紙の本やKindleで読める入門書の中から、厳選した2冊をご紹介します。
- 『1手ずつ解説!初心者から始める将棋入門』(著:羽生善治 監修)
→ 駒の動き・対局の流れ・基本戦法まで網羅した初心者向け定番。 - 『大人のための将棋ドリル 初級編』(著:戸辺誠)
→ 詰将棋や次の一手を通じて、実戦力を自然に身につけられる内容。
これらはAmazonや書店で手に入りやすく、独学でもかなりの実力がつきます。
効率的な学習方法|定跡より「実戦→復習」がカギ
初心者にありがちなのが、定跡や囲いの知識だけに偏ってしまい、実戦経験が少ないということ。将棋は覚えるだけでなく「実戦→復習」のサイクルが非常に重要です。
おすすめの学習手順
- アプリで1日1局対局(将棋ウォーズなど)
- 終局後に「なぜ負けたか」「どこで悪手を指したか」を確認
- 分からなかった局面をYouTubeや書籍で調べる
- 同じような局面で指し直してみる(再現対局)
このサイクルを繰り返すことで、知識が実戦力として身につきます。
まとめ|将棋のやり方・始め方を理解して一歩ずつ上達しよう
将棋はルールこそシンプルですが、奥深い思考ゲームです。初めての方が「どう始めればいいか」と迷っても当然。しかし、正しい順序とツールを使えば、誰でも楽しみながら上達できます。
本記事では以下のような流れで、将棋の始め方について解説しました。
- 将棋の基本ルール(駒の動き・勝敗条件)
- 必要な道具や無料アプリの紹介
- 初心者におすすめの練習方法
- 知っておきたい囲い(舟囲い・美濃囲いなど)や戦法
- 無料アプリ・書籍を活用した学び方
最初は「覚えることが多い」と感じるかもしれません。しかし、ひとつずつステップを踏みながら実戦経験を積むことで、自然と指せるようになっていきます。
将棋は年齢を問わず一生楽しめる趣味です。勝ち負けに一喜一憂するのも楽しみのひとつ。まずは簡単な対局から始めて、少しずつ「囲い」や「戦法」を覚えましょう。
将来的には「右玉」や「四間飛車」など、より高度な戦い方にも挑戦できるようになります。そのためにも、最初の一歩を踏み出すことが大切です。
将棋は「考える力」「粘り強さ」「先を読む力」を育ててくれるゲームです。
最初の一手が、あなたの新しい知的趣味への扉になります。
さあ、今日から将棋を始めてみませんか?

