将棋の戦法には「居飛車」と「振り飛車」という大きな分類がありますが、その中でも居飛車戦法は、安定した守備と多彩な攻め筋を両立する王道のスタイルです。
「将棋を始めたばかりでどの戦法を選べばいいか迷っている」「居飛車と振り飛車、どっちが強いの?」そんな悩みを抱える初心者から、さらなる実力アップを目指す中級者まで、この記事では居飛車戦法の基本から定跡、実戦のやり方、対策法までを徹底的に解説します。
また、キーワードとして挙げられた「棒銀」「定跡」「対策」「守り方」「受け方」などもすべてカバー。
具体的な戦法の選び方やプロ棋士の実例も交えて、実践的な知識が身につく内容になっています。
この記事を読めば、自分に合った居飛車戦法を見つけ、将棋で勝つための道筋が見えてくるはずです。
将棋の戦法一覧|初心者向けから最強戦法・奇襲型まで完全解説!


◆アプリダウンロード数4,000万突破!


将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、
【 ABEMA
プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。
>> 将棋見るならABEMA
将棋の居飛車戦法とは?基本と特徴
将棋における「居飛車戦法」とは、飛車を初期配置の右側(2筋)から動かさずに戦う戦法の総称です。
振り飛車が飛車を左翼へ移動して戦うのに対して、居飛車は飛車を居たままにして中央や右側から攻めを構築していきます。
このスタイルは将棋の基本形とも言えるもので、序盤から中盤にかけてのバランスが良く、多くのプロ棋士も採用する堅実な戦法です。
居飛車戦法の基本と指し方
居飛車戦法では、序盤から飛車先の歩(2四の歩)を突き、相手の出方を見ながら攻守のバランスを取ります。
基本の指し方は以下の通りです。
| 手順 | 指し手 | 解説 |
| 1手目 | ▲7六歩 | 角道を開ける基本の一手 |
| 2手目 | ▲2六歩 | 飛車先を突いて主導権を握る |
| 3手目 | ▲2五歩 | 早い段階での飛車先突破を狙う |
このように、飛車先の歩を積極的に突きながら角や銀の活用を考えていくのが居飛車の基本です。
飛車の利きを活かして中央を制圧し、角との連携で攻めを組み立てていくことが重要です。
居飛車の特徴と振り飛車との違い
居飛車の特徴は以下の3つにまとめられます。
- 中央〜右側から攻める構造
- 守備と攻撃のバランスが良い
- 定跡が豊富に整備されている
一方で振り飛車は、飛車を左に振ることで相手の攻めを受け流しながらカウンターを狙う構造です。
振り飛車は柔軟性がありますが、居飛車は「読みの正確さ」がより求められる戦法と言えるでしょう。
居飛車戦法を採用する理由と適性
居飛車を選ぶプレイヤーの多くは、戦局を自分でコントロールしたいタイプです。
相手の仕掛けに対して受ける形よりも、自分から主導権を握りたい人に向いています。
以下のような性格傾向と相性が良いとされます。
- 戦術より戦略を重視する
- 序盤から中盤の構造把握が得意
- 対局全体を計画的に進めたいタイプ
特に初心者にとっては、定跡が多く整っているため学習もしやすく、正しい型を身につけるにはうってつけの戦法です。
このように、居飛車戦法は攻守ともに優れたオールラウンダー型の戦法です。
次のセクションでは、実際にどのような種類の居飛車戦法が存在するのかを詳しく紹介していきます。
将棋の居飛車戦法の種類と選び方
居飛車戦法には数多くのバリエーションが存在し、それぞれに特徴や狙いがあります。
どの戦法を選ぶかは、プレイヤーの性格や好み、対局の状況に応じて異なります。
ここでは代表的な居飛車戦法とその選び方について解説します。
初心者におすすめの居飛車戦法
初心者が最初に習得すべき居飛車戦法は、以下のような基本的なものです。
| 戦法名 | 特徴 | 難易度 |
| 矢倉戦法 | 固い囲いと力強い攻め | 中 |
| 角換わり戦法 | 現代将棋の主流、角交換が前提 | 高 |
| 横歩取り | スピード感のある展開 | 高 |
| 棒銀戦法 | 銀を積極的に前に出す | 初〜中 |
特に「棒銀戦法」は、攻めの基本を学ぶうえで非常に有効です。
銀を飛車の前に進めて一直線に攻め込むため、攻撃感覚を養いやすくなります。
勉強の順番と戦法の絞り方
将棋の学習では「1つの戦法を深く掘ること」が上達の近道です。
以下の順番で居飛車を勉強していくと、理解が深まりやすくなります。
- 棒銀(攻めの基本)
- 矢倉(守備と構造理解)
- 角換わり(現代型の戦術理解)
- 横歩取り(スピード感のある将棋)
戦法を絞る際には、自分が攻め好きか受け好きかを判断軸にしましょう。
たとえば、ガンガン攻めたいタイプは「棒銀」、構えて反撃したいなら「矢倉」が合っています。
居飛車を使う将棋棋士たち
プロ棋界では、居飛車を主戦法とするトップ棋士も多数います。
以下はその一例です。
| 棋士名 | 代表戦法 | 特徴 |
| 藤井聡太 | 角換わり、矢倉 | 柔軟な構想力と読みの深さ |
| 渡辺明 | 矢倉、角換わり | 安定した序盤戦術と終盤力 |
| 羽生善治 | オールラウンダー | 相手に応じて柔軟に対応 |
彼らの棋譜を研究することは、居飛車戦法の理解を深めるうえで非常に有効です。
特に「角換わり」や「矢倉」などの実戦譜を繰り返し並べてみることで、手順の意図が掴めるようになります。
次のセクションでは、居飛車に対する対策や守り方、定跡の理解など、実践的な対応力を高める内容に進みます。
将棋の居飛車戦法への対策と受け方
居飛車戦法はバランス型であるがゆえに、多くのプレイヤーが採用します。
しかし、どんな戦法にも弱点はあるもの。ここでは、居飛車に対抗するための基本的な対策と、受け方のコツを紹介します。
居飛車に対する振り飛車の有効性
居飛車に対抗する代表的な戦法が「振り飛車」です。
特に四間飛車や中飛車は、居飛車の飛車先攻めを逆用し、左翼からの反撃を狙えます。
| 振り飛車戦法 | 有効な理由 |
| 四間飛車 | 相手の飛車先に飛車をぶつけて反撃できる |
| 中飛車 | 中央からの制圧で居飛車を崩せる |
| 向かい飛車 | 飛車の直線的な攻撃で主導権を握れる |
振り飛車は柔軟性が高く、相手の型に付き合わずに戦えるという点で、居飛車に対する実戦的な対策となります。
守り方と囲いでの工夫
居飛車戦法は攻めに特化する分、守りの準備がやや遅れがちになります。
これを突くには、素早い囲いと中央の厚みを意識した構えが重要です。
おすすめの囲い
| 囲い | 特徴 |
| 美濃囲い | 振り飛車党に人気。居飛車の右攻めを防ぐ |
| 金無双 | 守備力が高く居飛車の突破を阻止しやすい |
| 舟囲い | 早囲いに対応できる簡易な囲い |
相手が早めに飛車先を伸ばしてきた場合は、自分も囲いを急ぎ、角や銀の進出をブロックすることが効果的です。
居飛車にありがちなミスとその誘発
居飛車は定跡が豊富で強い戦法ですが、逆に「型に頼りすぎる」ミスも多い戦法です。
たとえば以下のような例がよく見られます。
- 飛車先の歩交換にこだわりすぎて囲いが遅れる
- 棒銀で攻め急ぎすぎて玉が薄くなる
- 相手のカウンターに無防備な陣形を作る
こうしたミスを誘発するには、「受けすぎないこと」が重要です。
あえて中央を固めて相手に攻めさせ、スキを突く構えをとると、居飛車側が過剰に動いてくる可能性が高まります。
次は、「居飛車戦法をどこまで極めるべきか」というテーマで、長所と短所、そして最強かどうかの評価をしていきます。
将棋の居飛車戦法の強みと弱点|最強の戦法なのか?
居飛車戦法は「最も標準的かつ普遍的」とされる将棋の戦法です。
では実際に、居飛車戦法は他の戦法と比べて「最強」と言えるのでしょうか?
ここでは、居飛車の長所と短所、そして実戦における評価を詳しく見ていきます。
居飛車戦法のメリット
居飛車戦法には、以下のようなメリットがあります。
- 安定した戦型を構築しやすい
- 攻守のバランスが取れている
- 定跡研究が進んでおり、情報が豊富
- 中盤〜終盤に持ち込んでからの逆転がしやすい
特に、将棋ウォーズのような早指しアプリでも、定跡を覚えていれば序盤でリードを取れるため、勝率が安定します。
また、相手の戦型に合わせて柔軟に戦法を変化させることも可能です。
居飛車戦法のデメリット
一方で、居飛車にはいくつかの弱点もあります。
- 定跡を知らないと一方的に潰される
- 相手に読み筋を知られやすい
- 中盤以降の捌きが難しい
- 戦いが激化するとミスが出やすい
たとえば、棒銀などのシンプルな攻め筋は、対策を知っている相手には通じづらく、逆に攻めが空振りになることもあります。
また、中央や2筋の戦いは難解になりやすく、少しのミスで劣勢になるリスクがあります。
居飛車戦法は最強か?評価と結論
結論から言えば、居飛車戦法は「最強」ではありませんが、「もっとも安定して強くなれる戦法」であることは間違いありません。
特定の状況や相手においては、振り飛車の方が優れている場合もありますが、以下のような点で居飛車は優秀です。
| 比較項目 | 居飛車 | 振り飛車 |
| 攻撃力 | ◎ | ◯ |
| 守備力 | ◎ | △ |
| 定跡の整備 | ◎ | ◯ |
| 柔軟性 | ◯ | ◎ |
| 初心者向け | ◎ | ◯ |
このように、居飛車は「堅実に勝ちたい人」「将棋を体系的に学びたい人」には最適の戦法です。勝率を上げたい初心者・中級者にとっては、まず居飛車をマスターすることが上達の近道となります。
次のセクションでは、居飛車戦法をより深く学ぶための書籍や動画、実戦例など、おすすめの学習リソースを紹介していきます。
続いて、学習リソースに関する最終セクションを執筆します。
将棋の居飛車戦法を学べる本・動画・実戦例まとめ
居飛車戦法は定跡や戦型の数が多く、自己流で進めると迷いやすくなります。
そのため、信頼できる学習リソースを使って段階的に理解を深めることが重要です。
ここでは、居飛車戦法を学ぶのに役立つ書籍や動画、実戦譜の活用方法を紹介します。
初心者におすすめの書籍3選
将棋初心者でも理解しやすい、居飛車戦法に特化した入門書籍を紹介します。
| 書籍タイトル | 著者 | 特徴 |
| 『居飛車入門 基本から学ぶ定跡』 | 中村太地 | 図解豊富で定跡の基本が学べる |
| 『棒銀戦法マスター』 | 勝又清和 | 居飛車戦法の入口「棒銀」の習得に最適 |
| 『矢倉戦法完全ガイド』 | 佐藤康光 | 中級者向けに矢倉の構造が深く理解できる |
特に「棒銀」と「矢倉」は初心者〜中級者への登竜門的な戦法なので、まずはこの2つを徹底的に学ぶと良いでしょう。
YouTubeで見られる丁寧な解説動画
近年は、将棋系YouTuberの台頭により、無料で高品質な解説動画が多数公開されています。
おすすめチャンネル
- 【将棋放浪記】:角換わりや矢倉の戦型解説が丁寧で初心者にもやさしい
- 【元奨励会員アゲアゲさん】:居飛車戦法を実戦形式で解説
- 【日本将棋連盟公式】:プロ棋士による定跡解説や講座動画が充実
YouTubeの強みは「棋譜の流れを実際に目で見て覚えられる点」です。
特に解説付きの動画であれば、感覚ではなく「理屈で理解」しやすくなります。
将棋ウォーズや将棋クエストでの実戦練習
習った戦法は実戦で試してこそ、身につきます。
オンライン将棋アプリである「将棋ウォーズ」や「将棋クエスト」では、気軽に対局しながら戦法の理解を深められます。
学習の流れ
- 書籍や動画で戦法を学ぶ
- アプリで10局〜20局ほど同じ戦法で実戦
- 勝ち負けよりも「型を守る」ことを意識
- 後で棋譜を振り返って反省と修正
特に将棋ウォーズでは「AIによる検討機能」が付いており、自分の指し手がどこで悪くなったかを確認できるため、短期間での上達が可能です。
まとめ:将棋の居飛車戦法を学ぶべき理由と実践ポイント
最後に、本記事で紹介した内容の要点を以下にまとめます。
まとめ
- 居飛車戦法は将棋の基本型であり、攻守のバランスに優れる。
- 棒銀・矢倉・角換わりなど複数の派生戦法があり、目的に応じて使い分けが可能。
- 居飛車に対する振り飛車は有効な対策であり、囲いの工夫や守り方が重要。
- 最強ではないが安定感と応用力が高く、初心者にもおすすめの戦法。
- 書籍・YouTube・将棋アプリを活用して段階的に学習し、実戦経験を積むのが成長の近道。
このように、居飛車戦法は「正統派の将棋を学ぶうえで欠かせない基本」です。
この記事をきっかけに、自分に合った戦法を見つけ、将棋の奥深さをさらに楽しんでください。
将棋の三間飛車とはどんな戦法?石田流との違い・組み方・対策まで徹底解説
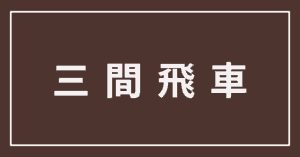
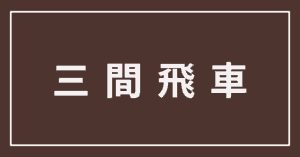
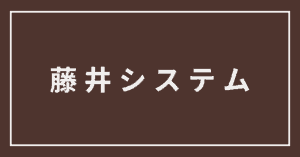
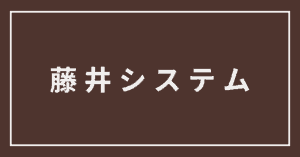
居飛車穴熊の戦法完全ガイド|定跡・対策・プロの実戦例まで徹底解説

