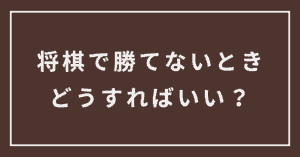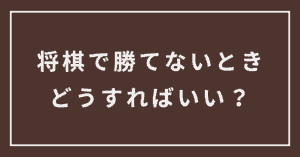将棋の世界には「タイトル戦」と呼ばれる8つの頂上決戦があります。
プロ棋士たちは日々の対局やリーグを勝ち抜き、このタイトル戦に挑むことを夢見て戦っています。
タイトルを獲得すれば名声・賞金・地位のすべてを手に入れることができるため、まさに将棋界の“頂上決戦”といえる存在です。
しかし、将棋ファンや初心者の中には「タイトル戦って何?」「どんな仕組みなの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、将棋の8大タイトルの特徴や違い、序列・賞金額・開催時期・挑戦制度などを、初心者でもわかるように詳しく解説します。
さらに、ABEMAでの視聴方法や観戦の楽しみ方についても紹介しますので、これから将棋を学びたい人にも最適な内容になっています。
\ 将棋観戦ができる唯一のVOD /
将棋のタイトル戦とは?8大タイトルの全体像
将棋界において「タイトル戦」とは、プロ棋士たちの頂点を決める公式な戦いのことを指します。
2025年現在、タイトル戦として認定されているのは以下の8つです。
そもそも将棋における「タイトル戦」とは?
日本将棋連盟が認定する「タイトル戦」は、棋戦の中でも最も権威のあるものとされています。
これらのタイトルは、それぞれ独立した主催者・形式・予選制度を持っており、年間を通じて開催されています。
各タイトル戦の勝者は「○○タイトル保持者」となり、複数のタイトルを同時に保持することも可能です。
2025年現在、藤井聡太七冠(竜王・名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖)(叡王のみ伊藤匠叡王が保持)という異次元の記録も生まれています。
タイトル戦は「格式・賞金・期間」がまったく異なる別々の棋戦。
8つすべて制覇することは「八冠制覇」と呼ばれます。
現在存在する8大タイトル戦一覧
以下が、現在の将棋タイトル戦の一覧です(2025年時点)
| 序列 | タイトル名 | 現在の保持者(2025) | 主催・協賛 |
| 1位 | 名人 | 藤井聡太 | 毎日新聞社、朝日新聞社 |
| 2位 | 竜王 | 藤井聡太 | 読売新聞社 |
| 3位 | 王位 | 藤井聡太 | 中日新聞社、他 |
| 4位 | 叡王 | 伊東匠 | 不二家 |
| 5位 | 王座 | 藤井聡太 | 日本経済新聞社 |
| 6位 | 棋王 | 藤井聡太 | 共同通信社 |
| 7位 | 王将 | 藤井聡太 | スポーツニッポン、毎日新聞社 |
| 8位 | 棋聖 | 藤井聡太 | 産経新聞社 |
※現在は藤井聡太棋士が七冠保持しており、1つは伊藤匠棋士が保持しています。
各タイトルの主催・後援・運営元まとめ
各タイトル戦は、新聞社や企業がスポンサーとなって開催されており、棋戦ごとに対局場・運営スタイル・持ち時間・番勝負の回数なども異なります。
例
- 竜王戦:読売新聞社主催。持ち時間8時間、7番勝負。
- 名人戦:毎日新聞と朝日新聞が共同主催。持ち時間9時間、7番勝負。
- 叡王戦:株式会社不二家が主催。比較的新しい棋戦で、形式の変遷が多い。
このように、将棋のタイトル戦はひとくくりにできない奥深さがあります。
次のセクションでは、その序列や賞金など、もう少し詳しく掘り下げていきましょう。
将棋タイトル戦の序列と賞金・格付けを比較
将棋の8大タイトル戦には、「序列」や「賞金額」といった“格付け”が存在します。
これはあくまで慣習的なものですが、将棋ファンや棋士にとっては非常に重要な指標です。
将棋界におけるタイトル序列とは?
将棋界では、タイトルの「重み」や「歴史の長さ」、「獲得したときの名誉」などを総合的に評価して、タイトルの“序列”が暗黙のうちに存在しています。
これは公式に決まっているものではありませんが、長年の伝統と実績に基づいて以下のように位置づけられています。
【タイトル戦の序列一覧(一般的な順)】
| 序列 | タイトル名 | 理由・特徴 |
| 1位 | 名人 | 将棋界で最も伝統と名誉があるタイトル。名人位は別格。 |
| 2位 | 竜王 | 賞金額が最も高く、格式も高い。7番勝負で争われる。 |
| 3位 | 王位 | 歴史が長く、対局数も多い。リーグ戦を勝ち抜く必要がある。 |
| 4位 | 叡王 | 新設タイトルながら注目度が高い。形式が頻繁に変わる。 |
| 5位 | 王座 | 毎年秋に行われる5番勝負。比較的短期決戦。 |
| 6位 | 棋王 | 持ち時間4時間と短く、スピード感のある対局が多い。 |
| 7位 | 王将 | 昔ながらの「東西対抗」の雰囲気がある伝統的タイトル。 |
| 8位 | 棋聖 | 5番勝負で行われ、夏の風物詩的存在。 |
このように、名人と竜王が“二大タイトル”として位置付けられ、特に名人位は「将棋界の王」としての象徴的な意味を持ちます。
賞金額・対局料の比較【2025年版】
タイトル戦の魅力の1つが「賞金・対局料」の高さです。
特に竜王戦は将棋界で最高額の賞金を誇ります。
【主要タイトル戦の賞金額(推定)】
| タイトル | 賞金額(推定) | 備考 |
| 竜王 | 約4,400万円 | 最も賞金額が高く、プロ憧れのタイトル |
| 名人 | 約2,500万円 | 歴史的価値が高い。名人の名は世襲に近い |
| 王位 | 約1,000万円 | リーグ戦勝ち抜き型でハードな戦いが特徴 |
| 王将 | 約800万円 | 東西代表決戦が残る伝統棋戦 |
| 棋王 | 約600万円 | 決着が早く、賞金も安定 |
| 王座 | 約500万円 | 短期決戦。賞金よりも名誉が重要視される |
| 叡王 | 約500万円 | 若手活躍の場として注目が高まっている |
| 棋聖 | 約300万円 | 夏開催の5番勝負。比較的軽めの賞金 |
[重要] これらの金額はあくまで主催者発表や過去の傾向に基づく推定であり、年によって変動します。
賞金だけを見ると竜王戦が圧倒的ですが、名人位の「名誉」や「格」はお金以上の重みがあります。
棋士にとって名人経験は引退後も永遠に称される勲章であり、プロの最終目標とされています。
対局形式の違いとタイトル戦日数の比較
タイトル戦にはそれぞれ異なる対局形式(持ち時間・番勝負数)があります。
棋士の得意なスタイルによって、活躍しやすいタイトルも変わります。
【主要タイトル戦の形式まとめ】
| タイトル | 番勝負 | 持ち時間 | 形式 |
| 名人 | 7番勝負 | 各9時間 | 2日制 |
| 竜王 | 7番勝負 | 各8時間 | 2日制 |
| 王位 | 7番勝負 | 各8時間 | 2日制 |
| 王将 | 7番勝負 | 各8時間 | 2日制 |
| 王座 | 5番勝負 | 各5時間 | 1日制 |
| 棋王 | 5番勝負 | 各4時間 | 1日制 |
| 棋聖 | 5番勝負 | 各4時間 | 1日制 |
| 叡王 | 5番勝負 | 各3時間 | 1日制(変動あり) |
2日制で行われる対局は、午前〜夕方にわたる長時間対局で、非常に集中力が求められます。
一方、1日制の棋戦はテンポが速く、若手やスピード型の棋士が活躍しやすい傾向にあります。
将棋タイトル戦の仕組みと開催形式の違い
将棋の8大タイトル戦は、それぞれに予選方式・挑戦者決定の方法・主催者・開催時期が異なります。
このセクションでは、各タイトル戦の「仕組みの違い」について詳しく解説します。
各タイトル戦の主催・時期・開催数を一覧で比較
将棋のタイトル戦は、新聞社や配信サービス、文化団体などが主催・共催しています。
棋戦によって開催時期や注目度、報道の扱い方にも違いが見られます。
| タイトル | 主催(または共催) | 開催時期(目安) | 特徴 |
| 竜王 | 読売新聞社 | 10月〜12月 | 棋界最高賞金の超注目タイトル |
| 名人 | 朝日新聞社・毎日新聞社 | 4月〜6月 | 歴史最長の伝統棋戦 |
| 王位 | 北國新聞社など | 7月〜9月 | 持ち時間8時間の7番勝負 |
| 王座 | 日本経済新聞社 | 9月〜10月 | 短期決戦・秋の風物詩的存在 |
| 棋王 | 共同通信社など | 2月〜3月 | スピード勝負が持ち味の棋戦 |
| 王将 | スポーツニッポン新聞社など | 1月〜3月 | 東西代表制の伝統を継ぐ一戦 |
| 棋聖 | 産経新聞社 | 6月〜7月 | 比較的短期間で決着する |
| 叡王 | ABEMA/ドワンゴ | 5月〜6月 | 新興メディア主催、ネット生中継多数 |
王道は「名人・竜王」ですが、近年では不二家主催の叡王戦も急速に注目度を上げています。
予選方式の違い|トーナメント・リーグ制・挑戦者決定戦
各タイトルには、「誰が挑戦者になれるか」を決めるための予選制度があります。
これも棋戦ごとに形式が大きく異なります。
- リーグ戦を導入している棋戦(名人・王位・王将)
予選を勝ち抜いた棋士がリーグ入り
リーグ内での総当たり戦を経て、最上位者が挑戦権獲得 - トーナメント方式の棋戦(竜王・王座・棋王・棋聖・叡王)
勝ち上がり制のトーナメント
竜王戦はさらに昇級・降級を含む複雑な「クラス分け」あり
【予選形式別タイトル戦】
| タイトル | 予選形式 | 挑戦者決定法 |
| 名人 | A級順位戦 | 1位が挑戦者 |
| 竜王 | トーナメント+決定三番勝負 | 決定戦勝者が挑戦者 |
| 王位 | 挑戦者決定リーグ戦 | 白組・紅組1位の決戦 |
| 王座 | トーナメント制 | 決勝勝者が挑戦者 |
| 棋王 | トーナメント制 | 決勝勝者が挑戦者 |
| 王将 | 挑戦者決定リーグ戦 | 最上位が挑戦者 |
| 棋聖 | トーナメント制 | 決勝勝者が挑戦者 |
| 叡王 | 本戦トーナメント | 決勝勝者が挑戦者 |
[参考] 名人戦のみは順位戦という独自のピラミッド構造の中で、年間を通して順位が争われます。
最上位「A級」の1位が挑戦権を得る仕組みで、非常に重みのある制度です。
ネット中継とABEMAの影響力
近年では、ABEMAを中心としたネット中継の影響で、若年層を中心に将棋の視聴者層が拡大しています。
特に以下のようなタイトル戦はABEMAで中継され、多くのファンに支持されています。
- 叡王戦(不二家主催)
- 王位戦・棋聖戦・王将戦など(共催・協賛多数)
ABEMAは「無料+高画質+多視点+解説あり」という強みを持ち、テレビ放送をしのぐ人気を誇っています。
\ 将棋観戦ができる唯一のVOD /
タイトル戦をもっと楽しみたい人に向けて、ABEMAプレミアムへの加入をおすすめする流れが自然です。
広告視聴なし&過去の対局も見放題。
将棋タイトル戦の記録と偉業|歴代最多・最年少記録をチェック
将棋のタイトル戦では、数々の偉大な記録や記憶に残る名勝負が生まれてきました。
ここでは、棋士たちの歴代記録・最年少記録・連覇記録などを、データとともにご紹介します。
歴代最多タイトル獲得数ランキング
歴代の棋士の中で、タイトル戦を最も多く制したのは誰なのか?以下の表でトップ5をご紹介します。
| 順位 | 棋士名 | 獲得タイトル数 | 主なタイトル |
| 1位 | 羽生善治九段 | 99期 | 名人・竜王・王位・王座など全制覇(永世七冠) |
| 2位 | 大山康晴十五世名人 | 80期 | 名人・王将・棋聖など |
| 3位 | 中原誠十六世名人 | 64期 | 名人・王座・棋王など |
| 4位 | 谷川浩司九段 | 27期 | 名人・棋王・王位など |
| 5位 | 森内俊之九段 | 12期 | 名人・竜王など |
羽生善治九段は全てのタイトルで永世称号を保持し、「将棋界のレジェンド」として不動の地位を築いています。
最年少タイトル獲得記録
近年、藤井聡太八冠の登場により、タイトル最年少記録も更新されました。
以下は将棋界の主な最年少記録トップ3です。
| 順位 | 棋士名 | 獲得タイトル | 年齢 |
| 1位 | 藤井聡太八冠 | 棋聖(初タイトル) | 17歳11ヶ月 |
| 2位 | 屋敷伸之九段 | 竜王 | 18歳6ヶ月 |
| 3位 | 加藤一二三九段 | 王位 | 19歳3ヶ月 |
藤井聡太八冠はその後、史上初の全冠制覇(八冠)を達成し、すべての最年少タイトルホルダー記録を塗り替えました。
連覇記録・連続防衛数ランキング
同じタイトルを連続で防衛する強さも将棋界で高く評価されます。以下は代表的な連覇記録です。
| タイトル | 棋士名 | 連覇数 | 備考 |
| 王座 | 羽生善治九段 | 19連覇 | タイトル戦最多連覇記録 |
| 棋王 | 渡辺明九段 | 9連覇 | 現代将棋界の鉄壁防衛王 |
| 名人 | 大山康晴十五世名人 | 13連覇 | 昭和の巨人、長期政権を築く |
| 王将 | 大山康晴十五世名人 | 10連覇 | 名人戦と並ぶ長期保持タイトル |
| 王位 | 中原誠十六世名人 | 9連覇 | 安定した棋風で防衛を重ねる |
注目ポイント:藤井聡太八冠もすでに複数のタイトルで「防衛戦の連勝街道」を歩み始めています。
今後は羽生九段の記録更新も現実味を帯びています。
次のセクションでは、将棋タイトル戦の賞金と対局料・副賞の相場について解説します。
金銭面でのスケール感や、タイトル戦の格式を感じられる内容です。
将棋タイトル戦の賞金・対局料・副賞のリアル
将棋のタイトル戦は棋士にとって名誉であると同時に、賞金・対局料という面でも非常に大きな価値を持っています。
このセクションでは、タイトルごとの賞金額や副賞の内容、金銭的な魅力について詳しく解説します。
各タイトルの賞金額ランキング
以下は、日本将棋連盟や各主催メディアが公開している情報をもとにした、タイトル戦ごとの賞金額の目安(2024年時点)です。
| 順位 | タイトル | 主催 | 賞金額(推定) |
| 1位 | 竜王 | 読売新聞社 | 約4,400万円 |
| 2位 | 名人 | 朝日新聞・毎日新聞 | 約2,000万円 |
| 3位 | 王位 | 北國新聞社 他 | 約1,000万円 |
| 4位 | 王将 | スポーツニッポン 他 | 約800万円 |
| 5位 | 棋王 | 共同通信社 | 約600万円 |
| 6位 | 王座 | 日本経済新聞社 | 約500万円 |
| 7位 | 棋聖 | 産経新聞社 | 約300万円 |
| 8位 | A級順位戦(名人挑戦者) | 将棋連盟 | 対局料ベースで約500万円 |
※あくまで公表や報道による目安であり、実際の対局料や賞金には変動があります。
竜王戦の4,400万円は、将棋界最高峰の金額であり、「棋士の夢」とされる理由でもあります。
対局料・旅費・副賞の詳細
賞金とは別に、タイトル戦に出場するだけで支払われる「対局料」や旅費、副賞も存在します。
- 対局料の例
名人戦第1局:両対局者に各50万円程度
タイトル戦全体では数百万円規模の対局料が支払われることも - 旅費・滞在費
対局地までの交通費・宿泊費は主催者が全額負担
高級旅館や料亭が会場になることが多く、格式の高い場所での対局が基本 - 副賞
地元特産品(蟹、牛肉、米など)
トロフィーや賞状
地方自治体からの記念品など
タイトル獲得で生まれる収入面のメリット
タイトルを獲得することは、単発の賞金以上にキャリア・収入面でも大きなプラスとなります。
- CMやメディア出演の増加
- 記念対局・イベント出演のオファー
- 企業や団体からの支援やスポンサー契約
- 連盟からの年俸アップ(将棋大賞や功労賞)
特に藤井聡太七冠のように、メディア露出が多い若手棋士は、将棋界外からの社会的な注目と広告価値も増大しています。
将棋タイトル戦の観戦方法|ABEMAや現地観戦の楽しみ方
将棋のタイトル戦は、観戦方法の多様化によって、より多くのファンが楽しめるようになっています。
特に「ABEMA(アベマ)」の登場は、将棋観戦の文化を大きく変えました。
このセクションでは、タイトル戦をリアルタイムで楽しむための方法を紹介します。
ABEMAでの無料&有料観戦|どこまで見られる?
ABEMAは、将棋界の中継において圧倒的な存在感を持つメディアです。
多くのタイトル戦を高画質・解説付きで生配信しており、将棋ファンにとっては欠かせない存在です。
ABEMA観戦の特徴
- 基本無料でリアルタイム観戦可能(全局ではない)
- 豊富な解説陣(棋士・女流棋士・タレント)
- 過去の対局や感想戦のアーカイブも充実(※プレミアム限定)
- 観戦中のコメント機能でファン同士の交流も活発
ABEMAプレミアム(有料プラン)の特典
| 特典 | 内容 |
| 対局の全編視聴 | 一部制限付き配信の続きを視聴可能 |
| アーカイブ視聴 | 過去の名対局をいつでも観られる |
| 広告なし視聴 | 中断されずに集中して楽しめる |
| 同時視聴機能 | 別デバイスで複数配信をチェック |
こんな方におすすめ
- 対局を最初から最後までじっくり観たい
- 棋譜解説を繰り返し勉強したい
- プロ棋士の感想戦までじっくり楽しみたい
ABEMAプレミアムに登録することで、将棋観戦の幅がグッと広がります。
\ 将棋観戦ができる唯一のVOD /
現地観戦の魅力とは?大盤解説会や記念撮影も
タイトル戦は全国各地の旅館や会場で行われることが多く、ファンが実際に足を運んで観戦することも可能です。
現地観戦の楽しみ方
- 大盤解説会:会場に棋士が登場し、リアルタイムで戦局をわかりやすく解説
- 記念写真コーナー:実際の盤面やタイトル戦のセットを背景に写真撮影が可能
- 指導対局・ファン交流イベント:棋士と直接話したり指導を受けたりできる企画もあり
観戦チケットや参加申し込みは、将棋連盟公式HPや主催新聞社の情報をチェックしましょう。
YouTube・ニコニコ・NHKなど他の観戦手段
ABEMA以外にも、さまざまなメディアで将棋タイトル戦の観戦が可能です。
| メディア | 内容 |
| YouTube | 一部の将棋チャンネルがダイジェストや解説動画を公開 |
| ニコニコ生放送 | コメント文化が人気。解説つきライブ配信あり |
| NHK | 日曜午前の「NHK杯将棋トーナメント」など、TVでの放送あり |
ただし「生中継」や「アーカイブの充実度」ではABEMAが圧倒的です。
本格的に将棋タイトル戦を楽しみたい方は、やはりABEMAプレミアムの登録がおすすめです。
\ 将棋観戦ができる唯一のVOD /
将棋タイトル戦を楽しむためのファンガイド|初心者〜中級者向け
将棋のタイトル戦は、ルールを知っているだけでも十分に楽しめますが、少し知識を深めるだけで感動の深さが格段に違ってきます。
ここでは、初心者から中級者がより楽しく観戦できるポイントを紹介します。
観戦時に注目すべき3つのポイント
将棋観戦をより深く味わうには、以下の3点に注目すると良いでしょう。
| 注目ポイント | 内容 |
| 戦型選択 | 序盤の戦法(角換わり、相掛かりなど)から選手の戦略がわかる |
| 時間の使い方 | 長考や即指しで対局者の心理が見えてくる |
| 感想戦の内容 | プロの思考プロセスがわかり、学びが深まる |
これらに意識を向けるだけでも、将棋の奥深さをより一層味わうことができます。
タイトルホルダーの個性と棋風を理解しよう
将棋は「人間ドラマ」でもあります。
棋士それぞれの個性や戦い方を知ることで、観戦の面白さが倍増します。
例えば
- 藤井聡太七冠:AI的な精密さと終盤の切れ味が特徴
- 渡辺明九段:鋭い読みと中盤力で魅せる現代将棋の申し子
- 永瀬拓矢九段:粘り強さと徹底した準備で知られる努力型
こうした背景を知った上で対局を見ると、1手の意味や流れの重みが変わって見えてきます。
ABEMA観戦と併用した学習のコツ
ABEMAで将棋を観るだけでなく、観戦と学習を組み合わせることで棋力アップにも繋がります。
おすすめの学習法
- 観戦後に感想戦をチェックしてプロの考え方を理解する
- 気になった局面はアプリや将棋ソフトで検証する
- 同じ戦型の過去対局をABEMAアーカイブで振り返る
ABEMAプレミアムなら、こうした活用が自由自在。
観るだけでなく、学ぶ・深めるためのツールとしても最適です。
\ 将棋観戦ができる唯一のVOD /
まとめ|将棋タイトル戦はABEMAで“観て、学んで、楽しむ”
最後に、将棋タイトル戦を楽しむためのポイントをまとめます。
将棋タイトル戦まとめ【チェックリスト】
| 項目 | 内容 |
| 観戦メディア | ABEMA、YouTube、NHKなど多様な手段あり |
| タイトル一覧 | 竜王、名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖、叡王 |
| 観戦のコツ | 棋風、戦型、時間の使い方に注目 |
| 学習法 | 感想戦やアーカイブの活用で理解が深まる |
ABEMAプレミアムは将棋ファンに最適な環境
将棋ファンが快適にタイトル戦を楽しむなら、ABEMAプレミアムは必須級のサービスです。
- 全局ライブ観戦が可能
- 解説・感想戦・アーカイブすべて対応
- 将棋以外のコンテンツも充実
今なら無料トライアルも実施中。まずは気軽に試してみてください!
\ 将棋観戦ができる唯一のVOD /
将棋観戦は“知るほど楽しくなる”世界
タイトル戦は、ただ勝ち負けを見るだけではもったいないコンテンツです。
棋士の個性、戦法、駆け引き、歴史など、あらゆる視点から楽しむことができます。
ぜひ、ABEMAを通じて、将棋の奥深さと感動を体験してみてください。
\ 将棋観戦ができる唯一のVOD /