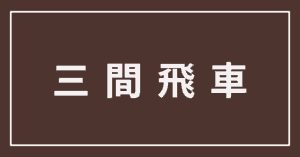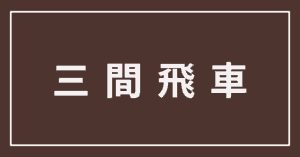将棋には定跡と呼ばれる膨大な知識体系が存在しますが、その一方で「奇襲戦法」と呼ばれる、相手の意表を突いて主導権を握る指し方も数多く存在します。その代表例のひとつが、三間飛車から派生した「トマホーク戦法」です。名前のインパクトと実戦的な破壊力から、一度は耳にしたことがある人も多いでしょう。
トマホーク戦法は、序盤から中央突破を仕掛けることで相手に早い段階でプレッシャーをかける戦術です。とりわけ居飛車党の研究不足を突ける点が魅力で、ネット将棋や早指し将棋では「相手が知らなければ刺さる」戦法として人気を集めています。一方で玉型が薄くなるリスクも抱えており、使いこなすにはバランス感覚が求められる戦法でもあります。
この記事では、トマホーク戦法の由来や定跡、強みと弱点、対策法、さらに実戦棋譜や学習教材までを徹底的に解説します。これから武器にしたい方はもちろん、受け方を学びたい方にも役立つ内容になっています。
将棋の戦法一覧|初心者向けから最強戦法・奇襲型まで完全解説!


◆アプリダウンロード数4,000万突破!


将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、
【 ABEMA
プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。
>> 将棋見るならABEMA
トマホーク戦法とは?基本の考え方と由来
トマホーク戦法は、振り飛車の中でも「三間飛車」から派生した奇襲戦法の一つです。序盤から中央突破を狙う大胆な戦い方で、攻撃力とインパクトのある名前からアマチュア将棋界で注目されてきました。ここではその由来や基本的な狙いについて解説します。
トマホーク戦法の名前の由来と歴史
トマホークという名前は、ネイティブアメリカンが用いた斧(Tomahawk)に由来しています。相手の守備陣を「斧で叩き割るように突破する」イメージから名付けられたといわれています。奇襲戦法らしく、1990年代後半から2000年代初頭にかけてインターネット将棋や早指し対局で広まったのが始まりです。プロ棋界での採用は少ないものの、アマチュアやアマ強豪の研究者が愛用してきた背景があります。
また、奇襲戦法を体系的に整理する中で、石田流や中飛車と並んで紹介されることも多く、奇襲系の戦法を扱った書籍や雑誌記事で名前を見かけるようになりました。
基本の狙いと中央突破のイメージ
トマホーク戦法の最大の特徴は、三間飛車から素早く中央を制圧し、△5五歩や△6五歩の突き出しで攻撃の起点を作る点です。具体的には、飛車を3筋に振った後、角を活用して中央を圧迫し、相手の飛車先交換や右銀の前進を妨害します。
基本的な狙いは以下の通りです:
- 中央突破:序盤から△5五歩を突いて中央の主導権を握る
- 角の活用:角を5四に展開し、相手陣を睨む
- 奇襲性:相手が知らないと正確に対処できず、そのまま押し切れる
特に居飛車党が石田流や三間飛車への通常の受けを準備している場合、予想外の中央突破で大きくバランスを崩すことができます。
他の振り飛車との違い
通常の三間飛車は飛車先の歩を交換してからじっくりと囲いを組みます。しかしトマホーク戦法では、あえて飛車先交換を後回しにし、中央に歩を突き出して「速攻」を仕掛けるのが大きな違いです。つまり、玉の安全性をある程度犠牲にしてでも、攻撃力に全振りする構想が特徴となります。
比較表にすると次のようになります。
| 戦法 | 狙い | 囲い | 特徴 |
| 三間飛車(通常) | 飛車先交換からの持久戦 | 美濃囲い | 安定感重視 |
| 石田流 | 飛車・角の連携で攻撃 | 美濃囲い | 攻守バランス型 |
| トマホーク | 中央突破で奇襲 | 簡易囲い | 攻撃特化・速攻型 |
このように、トマホークは「短期決戦型の三間飛車」として理解すると分かりやすいでしょう。
トマホーク戦法の基本手順と代表的な指し方
トマホーク戦法は、奇襲戦法ながら一定の体系があり、基本の手順を理解していれば再現性の高い攻めが可能です。ここでは、序盤からの組み方と代表的な進行例を見ていきましょう。
初手からの流れと三間飛車への展開
トマホークは三間飛車を基盤とするため、まずは振り飛車の形を作ります。典型的な進行は以下の通りです(先手の場合)。
- ▲7六歩 △3四歩
- ▲6六歩 △8四歩
- ▲7八飛
ここで飛車を3筋(▲7八飛 → ▲7六飛)に振り、三間飛車の構えを整えます。その後、角を5七に上げ、中央の歩を突き出す形がトマホークの基本。
進行例:
- ▲7六歩 → ▲6六歩 → ▲7八飛(振り飛車)
- ▲5七角 → ▲5五歩(中央突き出し)
これによって、通常の三間飛車よりも早く中央で戦いを仕掛けることができます。
中央突破を狙う基本の手順
トマホークの要は「△5五歩(▲5五歩)」の突き出しです。この一手によって、相手の銀の進出や飛車先交換を牽制します。
中央突破の流れをまとめると:
- 角を5七(または5三)に展開:中央をにらみ攻めの支点にする
- 5五歩を突く:相手の中央進出を阻止しつつ攻撃開始
- 飛車を3筋から中央にシフトする場合も:奇襲性を高める
相手が油断していると、この突破から一気に中央が崩壊し、短手数で勝負が決まることもあります。
代表的なトマホーク進行例
実際の対局でよく見られる進行例を簡単にまとめます。
例:先手トマホーク
- ▲7六歩 △3四歩
- ▲6六歩 △8四歩
- ▲7八飛 △8五歩
- ▲5六歩 △3二金
- ▲5七角 △5四歩
- ▲5五歩
ここで中央を制圧し、相手が受けを誤ると角の利きと飛車の連携で一気に崩せます。特に▲5五歩から角を5六に出るパターンは「トマホークの代名詞」といえる進行です。
囲いとの組み合わせ
奇襲戦法であるトマホークは、玉を堅く囲う前に仕掛けることが多いですが、最低限の囲いを作っておくと安心です。
よく組み合わせられる囲い:
- 片美濃囲い:素早く囲えるので奇襲に向く
- 簡易舟囲い:中央で勝負するため耐久力は不要
- 高美濃囲い(応用形):じっくり構えたい場合
ただし、囲いに時間をかけすぎるとトマホークの持ち味である「速攻性」が失われるため注意が必要です。
後手で使う場合の工夫
後手でトマホークを採用する場合、先手の居飛車が飛車先を伸ばす前に中央突破を仕掛けるのがポイントです。後手番でも、△5五歩や△6五歩の突き出しから速攻を狙うことで、相手に十分な準備をさせずに戦いを始められます。
- 後手なら△3四歩 → △5四歩 → △5五歩の流れが多い
- 飛車は△7二飛から△3二飛へ振るのが基本
このように、後手でも「中央突破」の狙いは変わりません。
トマホークの典型図
代表的な形を表にすると以下の通りです。
| 駒組みの段階 | 主な狙い |
| ▲7六歩〜▲7八飛 | 三間飛車に構える |
| ▲5七角〜▲5五歩 | 中央突破の準備 |
| ▲6六歩+角の展開 | 相手の銀や飛車先を牽制 |
この流れを理解すれば、誰でもトマホークの基本を習得することができます。
トマホーク戦法のメリットとデメリット
どんな戦法にも長所と短所があるように、トマホーク戦法も一方的に強いわけではありません。ここでは、実際の局面でどのような利点と欠点があるのかを整理してみましょう。
メリット|意表を突く奇襲で主導権を握れる
トマホークの最大の魅力は「相手が知らない局面に早く持ち込める」点です。定跡型に比べ、奇襲的な色が濃いため、特にアマチュア戦では勝率が上がりやすい傾向があります。
メリットを整理すると以下の通りです。
- 奇襲性が高い:研究が少ないため相手が戸惑いやすい
- 中央突破力が強い:▲5五歩(△5五歩)から一気に主導権を取れる
- 短手数で決着することも:相手が誤れば序盤で優勢に
- アマチュア間では有効性が高い:大会や早指しで特に効果的
特に早指し将棋やネット将棋では「意表性」が武器になり、知識よりも対応力が問われる場面で威力を発揮します。
デメリット|長期戦に弱く形が崩れやすい
一方でトマホークには構造的な弱点も存在します。中央に力を集中する関係で、囲いが不十分なまま仕掛けることが多く、持久戦には不向きです。
代表的なデメリットを挙げると:
- 囲いが薄い:玉の守りを軽視して攻めるため、反撃に弱い
- 研究されると脆い:プロや上級者は正確に対応できる
- 一度失敗すると立て直しにくい:奇襲性ゆえ、失敗すると形が崩壊
- 長期戦に不向き:持久戦では穴熊や矢倉に比べて耐久力不足
つまり「一撃で決められなかった場合」のリスクが非常に高いのです。
他の奇襲戦法との比較
トマホークはほかの奇襲戦法とどう違うのでしょうか?代表的な戦法と比較してみましょう。
| 戦法名 | 特徴 | メリット | デメリット |
| トマホーク | 中央突破を狙う三間飛車奇襲 | 意表性・中央制圧力 | 玉が薄い・持久戦に弱い |
| 筋違い角 | 初手から角を変則配置 | 相手が慣れていないと即効 | 研究されていると通用しにくい |
| 嬉野流 | 角道を止める独特の戦法 | 形が独特で読みづらい | 序盤からリスク大 |
| 鬼殺し | 端攻め狙いの極端な奇襲 | 短手数で決着することも | バレたら対策容易 |
このように、トマホークは奇襲の中でも「中央を支配する」という独自の性質を持っています。
向いている棋風とは?
トマホーク戦法が合うかどうかはプレイヤーの棋風に大きく左右されます。
向いている人の特徴は以下の通りです。
- 攻め将棋が好き:序盤から主導権を取りたい人
- 奇襲を好むタイプ:相手を混乱させてペースを握りたい人
- 短期決戦を狙う人:早指しやネット将棋で結果を出したい人
逆に「じっくり組んでから勝負したい」「安全第一で守りを固めたい」という人には不向きです。その場合は穴熊や矢倉などの堅陣を選ぶ方が向いています。
アマチュアでの勝率と実用性
実際にアマチュアの大会や将棋倶楽部24などのネット対局では、トマホークの採用率は一定数あります。特に級位者から初段前後の層では「勝ち筋をわかりやすく作れる」として人気です。
- 勝率は相手の知識量に依存:知らない相手には強烈に刺さる
- 研究者同士の対局では苦戦:中級以上になると対策が整っている
- 練習効果が高い:中央突破の感覚を学べるため、他の戦法にも応用可能
つまり「勝つためだけ」ではなく、学習用としても一定の価値がある戦法といえます。
トマホーク戦法への対策と崩し方
奇襲戦法であるトマホークは、不意を突かれると一気にペースを握られてしまいます。ここでは、相手がトマホークを仕掛けてきた場合にどう受け、どのように崩していくのかを整理してみましょう。
効果的な受け方|玉を堅く囲ってカウンターを狙う
トマホークは中央突破を狙う戦法のため、玉を固めて相手の攻めを受け切るのが基本的な対策です。美濃囲いや高美濃、場合によっては銀冠を選び、中央への突破を耐えながら反撃の準備を整えます。
対策の基本ポイント
- 早めに玉を囲う(美濃、高美濃、銀冠など)
- 相手の5筋歩の突き出しに注意し、角交換を避ける
- 受けの駒を中央に集中させて突破を防ぐ
このように中央の弱点をケアしておけば、相手の攻めは自然と切れやすくなります。
端攻めを絡めて揺さぶる
トマホークは中央に駒を集める関係上、端に弱点を抱えることが多いです。特に端歩の突き伸ばしは、相手に対応を迫る有効な手段です。
- 端歩を伸ばしておく:相手が中央に集中している間に端を制圧
- 桂馬を跳ねるタイミング:▲8五桂(△2五桂)などで圧力をかける
- 端攻め+中央受け:中央を受けつつ端から崩すと効果的
中央を狙ってきた相手に対し、端からの突破を合わせることで攻めのバランスを崩すことができます。
角交換から主導権を握る
トマホークは角道を通す形が多いため、角交換が起きやすい戦型です。ここで受け側が冷静に角を手持ちにしてしまえば、守りながら攻めの幅も広がります。
- 角交換に持ち込むメリット
- 中央突破を狙う相手に牽制できる
- 自陣に打ち込まれにくい形を作れる
- 攻めと守りの両方に使える
例えば「角打ちからのカウンター」を意識することで、相手の奇襲性を和らげることが可能です。
棒銀や居飛車急戦型での対処法
トマホークに対しては、奇襲に対してさらにスピード勝負を仕掛けるのも有効です。
- 棒銀でプレッシャーをかける:相手が中央に構えている間に飛車先突破を狙う
- 居飛車急戦で攻め合う:手数勝負に持ち込めば、玉の薄さが響く
- 右四間飛車も候補:相手が中央突破を狙う間に、端・飛車先を攻める
このように「攻め合いに持ち込む」ことが有効で、守るだけでなく能動的に仕掛ける選択肢も持っておくと勝率が上がります。
対策を怠るとどうなる?実戦での失敗例
トマホークに対策せず受け流してしまうと、簡単に中央を突破されてしまいます。例えば以下のようなケースです。
- 玉が薄いまま開戦 → 相手の5筋突破で一気に寄せられる
- 端歩を放置 → 端と中央の両方から攻められて崩壊
- 角交換に消極的 → 相手に角を使われて主導権を奪われる
こうした失敗は「知っていれば防げる」ことが多いため、定跡を理解しておくことが大切です。
トマホーク対策のまとめ表
| 対策方法 | メリット | デメリット |
| 玉を堅く囲う | 攻めを受け切りやすい | 囲いが完成するまでに攻め込まれる可能性 |
| 端攻めを絡める | 中央偏重の弱点を突ける | 端攻めに時間がかかると逆に中央突破される |
| 角交換を仕掛ける | 主導権を奪いやすい | 角打ちの隙を与えるリスク |
| 急戦を仕掛ける | 相手に対応を迫れる | 攻め合いで技術差が出やすい |
このように、複数の選択肢を知っておけば相手の出方に応じて柔軟に対応できます。
トマホーク戦法は初心者にもおすすめ?
トマホーク戦法は奇襲型であるため、「初心者でも使えるのか?」という疑問を持つ方が多いです。ここでは、習得のしやすさや注意点を踏まえ、初心者にとっての実用性を考えてみましょう。
初心者が使う際のポイントと注意点
初心者がトマホークを選ぶ場合、最も大切なのは「玉の安全度を意識すること」です。攻めに偏りすぎると、あっという間に反撃を受けてしまうため、駒組みの途中でも玉を寄せる意識を忘れてはいけません。
初心者が意識すべきチェックリスト:
• 玉を一手でも二手でも囲う(美濃囲い・金無双など)
• 角交換後の角打ちに注意する
• 攻めが止まったら守りに切り替える勇気を持つ
• 定跡を完璧に知らなくても狙い筋を把握する
これらを押さえることで「ただの無謀な突撃」ではなく、実戦的な奇襲として機能します。
組みやすさと学習難易度を他囲いと比較
トマホークは他の戦法に比べ、組み上げ手順がシンプルである点が初心者に向いています。序盤から飛車を三間に配置し、中央の歩を突き出すだけで形になるため、「定跡の暗記が少なく済む」という利点があります。
以下は主な囲い・戦法との比較です。
戦法 学習のしやすさ 定跡量 強さ 初心者向け度
トマホーク 簡単 少なめ 中級まで有効 ◎
美濃囲い+四間飛車 中 普通 安定 ○
矢倉 やや難しい 多い 高い △
穴熊 囲いは簡単だが中盤難解 多い 最強クラス △
この比較からもわかるように、「勝ちやすさ」と「学びやすさ」を両立したい初心者にとって、トマホークは最初の一歩として優秀です。
覚えておきたい基本パターンと応用形
トマホークは単発の奇襲戦法ではなく、発展型や応用形も存在します。基本の狙い筋を覚えれば、それを発展させることで勝率を伸ばせます。
• 基本パターン:三間飛車から5筋歩を突き、中央突破を狙う
• 応用形:角交換から持ち駒を使って再攻撃
• 発展形:急戦気味に攻める形、持久戦寄りに調整する形
また、応用的に「美濃囲い」や「高美濃」と組み合わせることで、奇襲の枠を超えてバランスの取れた戦法に変化させることも可能です。
初心者が練習するときのおすすめ手順
初心者がトマホークを効率よく学ぶためには、手順を「分岐点ごとに整理する」ことが有効です。
例えば:
1. ▲7六歩 △3四歩 ▲2六歩 △4四歩 ▲2五歩 △3三角 ▲4八銀 △4二飛
2. ▲6六歩 △6二玉 ▲6八玉 △7二玉 ▲7八玉
この流れで三間飛車+中央歩の突き出しが形になります。
さらに練習のステップとしては:
• まずは定跡本の図解を見ながら並べる
• 次にネット将棋で10局試して感触をつかむ
• 失敗した局面を記録して復習する
このサイクルを繰り返すことで、短期間でも上達が見込めます。
初心者にとってのメリットとリスク
最後に、初心者がトマホークを選ぶメリットとリスクをまとめます。
メリット
• 奇襲性で相手を翻弄できる
• シンプルな手順で実戦投入しやすい
• 中央突破の感覚が鍛えられる
リスク
• 守りが手薄になりやすい
• 対策を知っている相手には通用しづらい
• 攻めが止まると一気に不利になる
初心者にとっては「使いやすいけれどもリスクも高い」戦法です。そのため「勝ち負けよりも経験値を得る」つもりで取り組むのが良いでしょう。
トマホーク戦法を学べるおすすめの本・動画
実戦でトマホークを使いこなすためには、書籍や動画を活用して体系的に学ぶのが近道です。ここでは初心者から中級者まで役立つ教材を紹介します。
入門書や定跡本で学ぶならこれ!
トマホークは奇襲戦法であるため、大型の定跡書に細かく解説されていることは多くありません。しかし近年では、奇襲戦法をまとめた書籍や実戦譜集に取り上げられるケースが増えています。
おすすめできる書籍ジャンル:
- 奇襲戦法総合本:鬼殺しや筋違い角と並んでトマホークが紹介されている
- 三間飛車関連書籍:三間飛車の章にトマホーク型の解説がある場合が多い
- 実戦譜集:アマチュア大会やネット将棋での採用例をまとめたもの
例として「奇襲大全」「三間飛車戦法入門」などは参考になりやすく、基本の指し方を学ぶ助けとなります。
YouTubeで学べるトマホーク解説動画
近年ではプロ棋士やアマ強豪がYouTubeで戦法解説を行っており、トマホークも題材にされています。動画は盤面を見ながら学べるため、書籍よりも直感的に理解しやすい点が魅力です。
代表的なコンテンツ:
- 戦法解説チャンネル:「奇襲特集」や「三間飛車の応用編」で取り上げられる
- アマチュア実戦配信:実際の対局を振り返りながらトマホークの勝ち筋を解説
- プロ棋士の研究配信:公式チャンネルで取り上げられるケースもある
動画学習のメリットは「短時間で狙い筋が理解できる」ことです。実戦前に数本見るだけでも大きな効果があります。
プロの実戦例をチェックして理解を深めよう
トマホークはプロ公式戦で頻繁に出る戦法ではありませんが、研究家タイプの棋士が実験的に採用する例があります。また、アマ大会の棋譜には豊富な事例があり、実戦的な応用を学ぶのに役立ちます。
棋譜学習の方法:
- 将棋ウォーズや将棋倶楽部24の対局データからトマホーク採用局を検索
- プロ棋士の研究将棋や解説棋譜を参考にする
- 盤面を並べて「どのタイミングで仕掛けるか」を確認する
ポイントは「失敗局面を含めて学ぶこと」です。成功例だけでなく、相手に正しく対策された場合の棋譜も見ることで、リスクを実感しやすくなります。
教材選びのコツと活用法
教材を選ぶ際は、自分の棋力や学習スタイルに合ったものを選ぶことが大切です。
- 初心者 → YouTubeや入門書で基本の流れを学ぶ
- 中級者 → 実戦譜集や研究記事で応用パターンを習得
- 上級者 → 自分で棋譜を分析し、オリジナルの形を構築
さらに、学んだ内容をそのまま実戦で試す「アウトプット型学習」が重要です。1局ごとにテーマを決めて指すと、習熟度が高まります。
本と動画を組み合わせた学習プラン例
効率よくトマホークを身につけるには、本と動画を組み合わせた学習が効果的です。
学習プラン例:
- 1週目:YouTubeで基本の流れを理解
- 2週目:入門書で狙い筋や変化を整理
- 3週目:実戦で試し、棋譜を保存
- 4週目:棋譜を振り返りつつ再度動画を確認
このサイクルを繰り返せば、短期間でトマホークを実戦投入できるレベルに到達します。
まとめ|トマホーク戦法は現代将棋でどう活かせるか
ここまでトマホーク戦法の基本からメリット・デメリット、対策方法や学習法まで幅広く解説してきました。最後に、現代将棋におけるトマホークの位置づけと、活用のポイントを整理してみましょう。
奇襲としての使いどころと効果的な運用
トマホークは「意表を突く戦法」として強みを発揮します。プロ公式戦では採用例が少ないものの、アマチュア戦やネット将棋では依然として効果的です。
特に有効なのは以下の場面です。
- 短時間制の対局(早指し・ネット将棋)
- 相手が居飛車党で定跡重視のタイプ
- 研究勝負ではなく経験勝負を仕掛けたいとき
意表を突くことが最大の武器であり、「相手が知らない局面に誘導する」ことが勝率を高める鍵となります。
対策を知った上で使えば大きな武器に
トマホークを効果的に使うためには、自分自身が「トマホークを対策されたとき」にどうするかを理解しておく必要があります。
- 受け切られたらどうするか:玉を固め直して持久戦に移行
- 角交換された場合:手持ちの角を生かして反撃準備
- 端攻めされた場合:早めに端歩を受けるか、逆襲に転じる
このように、対策を理解したうえでトマホークを指せば、「奇襲失敗=即負け」にならず、安定して運用できます。
実戦と復習で筋違い角の精度を上げよう
戦法を自分のものにする最短ルートは「実戦+復習」の繰り返しです。トマホークも例外ではなく、実際に指してみて初めて強さと弱さを体感できます。
練習の流れ:
- 定跡書や動画で基本手順を学ぶ
- 実戦で積極的に試す(10局程度を目安)
- 負けた局面を棋譜で確認し、原因を整理
- 改善点を意識して再挑戦
このサイクルを繰り返すことで、自然と「いつ仕掛ければよいか」「どの形が危険か」が見えてきます。
トマホークが将棋上達に与える効果
トマホークを学ぶこと自体が、単なる奇襲戦法の習得にとどまらず、将棋の理解を広げる効果があります。
- 中央突破の感覚を身につけられる
- 攻めと守りのバランスを考える習慣がつく
- 対策を学ぶ過程で他戦法の理解も深まる
つまり、トマホークは「上達の教材」としての役割も果たすのです。
H3:これからトマホークを試す方へ
最後に、トマホークをこれから指してみたい方へのアドバイスをまとめます。
- 最初は勝ち負けよりも形を作る練習を重視
- 対策されることも想定して柔軟に切り替える
- 実戦+復習を繰り返し、狙い筋を体に染み込ませる
この姿勢で取り組めば、トマホークは「ただの奇襲」ではなく、自分の強力な武器に変わっていきます。
まとめると、トマホーク戦法は奇襲性に優れ、特にアマチュア戦で威力を発揮する戦法です。正しく学び、対策を知った上で指せば、勝率アップだけでなく将棋力全体の向上にもつながるでしょう。
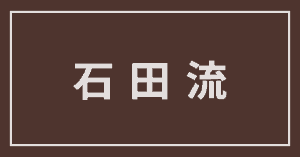
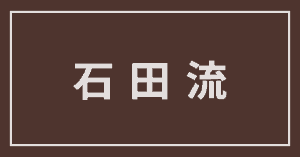
将棋の三間飛車とはどんな戦法?石田流との違い・組み方・対策まで徹底解説