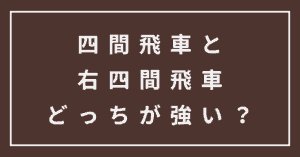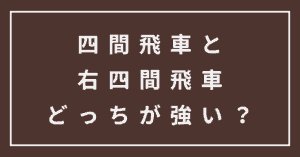将棋の中でも一風変わった戦法として知られる「筋違い角」。
序盤から相手の意表を突き、奇襲を仕掛けるこの戦法は、一部のアマチュアや研究好きな上級者たちの間で根強い人気を誇ります。
序盤で角を交換し、盤上の定跡から逸脱することで、相手に自由な展開を許さず主導権を握れるのが最大の魅力。
しかし一方で、少しでも対応を誤れば一気に形勢が悪くなる“諸刃の剣”でもあります。
この記事では、「筋違い角」の意味や由来から、定跡や指し方、対策法、さらには学習方法や教材まで幅広く解説します。
初心者でも理解しやすいように図やリストも交えながら丁寧に紹介していくので、これから筋違い角を使ってみたい方や、相手に使われて困った経験がある方も、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
将棋の戦法一覧|初心者向けから最強戦法・奇襲型まで完全解説!


◆アプリダウンロード数4,000万突破!


将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、
【 ABEMA
プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。
>> 将棋見るならABEMA
将棋の筋違い角とは?奇襲戦法としての基本と由来
筋違い角(すじちがいかく)は、序盤から角を通常とは異なる筋(列)に打ち込み、相手の陣形を崩しにいく奇襲型の戦法です。
定跡にとらわれない攻撃が可能で、アマチュア間では「奇襲の王様」として知られることもあります。
以下ではその意味・歴史・特徴を3つのポイントに分けて紹介していきます。
筋違い角の意味と起源・歴史
筋違い角とは、序盤早々に角交換を行い、敵陣近くに角を打ち込む戦法です。
通常、角は斜め方向のラインを制圧する駒ですが、交換後に角を「相手の銀や金を直射する位置」に打つことで、序盤から大駒の力で局面を揺さぶるのが特徴です。
【筋違い角の語源】
- 「筋違い」とは、本来あるべき筋(列)とは異なる位置に打たれることを意味します。
- 「角」は将棋で唯一斜めに動く大駒であり、配置によって戦局に大きな影響を与えます。
【歴史】
- 古くは江戸時代の将棋指南書『将棋無双』にも登場。
- 近代ではアマチュアの研究者やユニークなプロ棋士によって注目され、現代将棋においても奇襲の一つとして一定の人気を維持しています。
初心者にもわかる筋違い角の特徴
初心者にとっては筋違い角は「定跡を覚えなくても勝てる」戦法のひとつとして知られていますが、それは正確な理解がある場合に限ります。
| 特徴 | 解説 |
| 意表を突く | 角交換→打ち込みにより、相手に定跡通りの進行をさせない |
| 手順がシンプル | 基本は数手で角交換→筋違いに打つのみ(例:▲7六歩→▲2六歩→▲2五角) |
| リスクも高い | 相手に正確に対処されると、早々に形勢が悪くなる可能性もある |
また、戦型の縛りが少ないため、振り飛車・居飛車どちらでも応用が利くのもメリットです。
ただし、角を打った後の展開を把握しておかないと、“角だけ浮いた状態”になって持て余すという失敗も多く見られます。
奇襲戦法として注目される理由とは?
筋違い角が注目され続ける理由は、「研究が進みにくい」「初見殺しになりやすい」という性質があるからです。
奇襲戦法としてのメリット
- 相手の“定跡頼り”を崩せる
- 自分の得意展開に誘導しやすい
- 短時間の持ち時間でも使いやすい
さらに、ネット将棋やアマチュア大会などでは持ち時間が短く、研究よりも反射的な対応力が求められる環境が多いため、こうした奇襲は非常に効果的です。
ただし、以下のような点にも注意が必要です。
- プロや上級者には対策が練られている
- 一手のミスが命取りになる
- 中終盤での構想力が求められる
将棋の筋違い角の定跡と基本的な指し方
筋違い角は定跡型の将棋とは一線を画す「奇襲戦法」として知られていますが、実は一定の型や指し方のパターンが存在します。
このセクションでは、序盤の手順や展開例をわかりやすく解説し、実際に筋違い角を使う上で押さえておきたいポイントを整理していきます。
初手からの指し方・代表的な進行例
筋違い角は、角交換を早めに仕掛け、すぐに相手陣へ角を打ち込むのが基本的な流れです。
たとえば先手の基本形は次のような進行になります。
【先手の筋違い角 基本形】
- ▲7六歩
- △3四歩
- ▲2六歩
- △8四歩
- ▲2五角(筋違い角)
![図解イメージ(棋譜)]
ここで、▲2五角が筋違い角。
まだ角交換をしていませんが、早い段階で角を▲8四の地点などに打ち込みたいという意図が表れています。
ここから先手が▲同角成→▲7七桂と進めば、角を捌いたうえで主導権を握れる形へと発展します。
角交換から始まる展開と注意点
筋違い角は「角を交換してから奇襲をしかける」タイプが主流です。
その代表的な流れを確認しましょう。
【角交換型の筋違い角】
- ▲7六歩
- △3四歩
- ▲6八銀
- △8四歩
- ▲2六歩
- △8五歩
- ▲7七角
- △8六歩
- ▲同歩
- △同飛
- ▲同角
- △同角
- ▲同銀
- △同飛
ここで角交換が成立。
この後、▲6五角など筋違いに角を打ち込み、相手陣に圧力をかけていきます。
【注意点】
- 交換前に無理に角を打ち込むと、自陣の守りが崩れやすい
- 相手が棒銀や急戦で来ると対応が難しいため、周囲の駒組みも重要
角をただ交換するだけでは形勢が良くなるわけではなく、その後の「打ち込み位置」「囲い」「飛車の展開」が勝敗を分けます。
筋違い角に持ち込みやすい形とは?
筋違い角は、すべての戦型で採用できるわけではありません。
下記のような構えを相手が取っている場合に、比較的成功しやすくなります。
| 相手の構え | 筋違い角の成功率 | 備考 |
| 居飛車で矢倉模様 | 高い | 駒組みに時間がかかるので奇襲が刺さりやすい |
| ノーマル四間飛車 | やや高い | 美濃囲いに行く途中を狙える |
| ゴキゲン中飛車 | やや低い | 中央制圧が早いため、角が活かしにくい |
| 急戦型の早石田など | 低い | 先に攻められるので対応が難しい |
特に、相手が矢倉を目指すようなじっくり型の場合は、「角打ち→囲い崩し→飛車先突破」の流れに乗りやすく、奇襲が決まりやすいです。
将棋の筋違い角のメリット・デメリット
筋違い角は奇襲戦法として一部の将棋ファンから人気を集めていますが、当然ながら一長一短の戦法でもあります。
この章では、筋違い角の長所と短所を具体的に解説し、どのような場面で効果を発揮するのか、逆にどのような場面で使いにくいのかを整理します。
メリット|意表を突くことで主導権を握れる
筋違い角の最大の魅力は、相手の意表を突けることです。
序盤から大胆に角を筋違いに打つという発想は、通常の定跡書にはあまり載っていないため、多くの将棋指しが戸惑います。
主なメリットは以下のとおりです。
| メリット | 内容 |
| 相手の定跡を外せる | ゴキゲン中飛車や角換わりなど、事前準備された形を崩せる |
| 攻撃の主導権を握れる | 角の利きを活かして相手陣を早期に攻められる |
| 一手損を逆手に取れる | 相手の囲いの途中で揺さぶることで、守備を崩しやすい |
| 終盤力で勝負しやすい | 序盤に仕掛けて駒をさばき、終盤の実力勝負へ |
特にアマチュア間では、序盤の研究量が不足しがちなため、奇襲がうまく決まるケースが多いです。
デメリット|後手に回ると形が崩れやすい
筋違い角は攻撃的な戦法である反面、守備が疎かになりやすいという欠点も抱えています。
主なデメリットは以下のとおりです。
| デメリット | 内容 |
| 自陣が薄くなりやすい | 角を交換しすぎると守りの要がなくなる |
| 対応を誤ると即悪形に | 相手が冷静に対応した場合、筋違い角の角が働かない形になる |
| 終盤で手数不足になりやすい | 駒損や無理攻めが残ると押し切れない |
| プロレベルではほぼ使われない | 高段者には読まれやすく、リスクが大きい |
つまり、「筋違い角はハイリスク・ハイリターン型の戦法」と言えます。
形を崩すことなく主導権を取り続けられるかが、運用のカギです。
アマチュア間での有効性・勝率は?
筋違い角は、アマチュア将棋界では一定の支持を得ている戦法です。
特にネット将棋や道場での対局では、「定跡を知らない相手」に刺さることが多く、初級〜中級者帯での勝率が高いことがわかっています。
以下のような傾向があります。
- 10秒将棋や3切れなど持ち時間が短い戦型では強い
- 相手が囲いを作っている途中を狙うと大駒交換→一気に攻め落とせる
- ただし、駒組みに慎重な相手や囲いを優先するタイプには通じにくい
勝率は使用者の棋力にも左右されますが、「相手の囲い構築を乱す」という奇襲の本質を理解し、無理に攻めすぎない慎重さを加えることで、安定して使える戦法になります。
次は「筋違い角への対策|どう受けるべきか?」について詳しく解説していきます。
将棋の筋違い角への対策|どう受けるべきか?
筋違い角は奇襲戦法の一種であり、不意を突かれると混乱しやすい戦法です。
しかし、適切な対策を知っていれば、落ち着いて受けることが可能です。
このセクションでは、筋違い角への有効な対処法や注意点について、プロ・アマの視点から具体的に解説していきます。
プロ・アマでの代表的な対策パターン
筋違い角を受ける際に重要なのは、「慌てないこと」です。
相手は意表を突いてくる戦法を選んでいるため、ペースを乱さずに自分の形を整えることが大切です。
よく使われる対策例
| 対策法 | 特徴 |
| 早めに囲いを作る | 美濃囲いや舟囲いなどで自陣を固める |
| 銀や桂で角筋を防ぐ | 駒の効きを使って角の働きを限定する |
| 角を打たせた後に囲いを崩さない | 手損を避けて囲いを維持しつつ反撃 |
| 穴熊に組む | 奇襲の継続的な攻撃を無力化できる |
プロ棋士の間では、相手の狙いを受け流す構えが基本です。
過度に反応せず、「気づいたら相手の角が働かなくなっていた」という展開を目指すのが理想です。
棒銀や居飛車急戦型での対処法
筋違い角に対しては、棒銀戦法や急戦居飛車型などの積極的な対抗策も有効です。
- 棒銀戦法:早い段階で銀を上げ、角交換の後に弱点となる地点を狙う。筋違い角側は角の利きを活かしづらくなる。
- 急戦居飛車:筋違い角が角を打った直後に攻めを仕掛ける。相手が駒組みを整える前に速攻で主導権を取る。
こうした対策は、「相手に好きな形を作らせない」という意味で非常に効果的です。
特にアマチュアの実戦では、居飛車急戦型が安定感のある対応として支持されています。
対策が難しい場合の安全な受け方とは
筋違い角に慣れていない方や、持ち時間が短く冷静に対応しづらい場合は、「安全第一の構え」で対応しましょう。
おすすめの受け方は以下のとおりです。
- 美濃囲いまたは金無双などの囲いを先に完成させる
- 相手の角筋に駒を直接置かずに、利きをずらす
- 無理に角を取りに行かず、角が死ぬのを待つ
- 角の効きが止まる位置に歩や銀で壁を作る
このように、相手が角で主導権を取りきれないようにしながら、無理攻めを誘ってカウンターを狙うスタイルが有効です。
筋違い角は奇襲であるがゆえに、対応を知っているかどうかが勝敗を分けるポイントとなります。
何度も対局し、受け方を体に染み込ませることが、攻略への近道です。
将棋の筋違い角は初心者でも使える?
筋違い角は一見するとトリッキーで難しそうな戦法に見えますが、実は初心者でも十分に使える戦法です。
ただし、奇襲であるがゆえに、使い方と注意点を正しく理解しておくことが求められます。
このセクションでは、筋違い角が初心者にとって適している理由や注意点、練習方法などを詳しく解説していきます。
定跡が少なく覚えることが少ない戦法
将棋の戦法の多くは、数十手先までの「定跡」を覚える必要があります。
特に矢倉や角換わりなどは手順が細かく、初心者にとっては負担が大きくなりがちです。
その点、筋違い角は以下の理由から記憶の負担が少ない戦法といえます。
- 序盤で角交換を行うため、定跡形からすぐに外れる
- 形が独特なので、「感覚」で指す部分が多い
- 自分から攻めに出ることが多く、相手の応手に振り回されにくい
[重要] つまり、筋違い角は「定跡地獄」から解放されたい初心者にぴったりの選択肢とも言えるのです。
序盤力より終盤力が試される特徴
筋違い角の対局では、序盤での角交換が早く、すぐに中盤・終盤戦へと突入します。
そのため、以下のような局面が頻出します。
- 自陣が固まっていない中での戦い
- 相手の角打ちに注意しながらの駒組み
- 駒得・駒損が起きやすい乱戦
このような展開は、終盤力を鍛えるのに最適な環境です。
序盤の細かい形を覚えるよりも、「王手は追うな」「詰みと必至の違い」などの基本を体で覚えることが、将棋上達の近道になります。
また、筋違い角は自然と局面が動くため、感覚を掴む練習としても非常に有効です。
初心者が使うときの注意点と練習法
とはいえ、奇襲戦法にはリスクもあります。
以下は初心者が筋違い角を使う際に気をつけるべきポイントです。
注意点
- 相手が対策を知っていると通用しづらい
- 自陣が脆くなりやすいので囲いが遅れがち
- 無理攻めに走ると簡単に反撃される
練習方法
- 角交換のタイミングを研究する
→ どの局面で角交換すべきかを理解する - 自分の玉を囲う習慣をつける
→ 美濃囲いや金無双など、囲いの基礎を覚える - 棋譜並べで筋違い角の流れを学ぶ
→ プロの実戦譜を並べて手順を確認する
また、将棋ウォーズや将棋クエストなどのアプリを活用して、1日1局筋違い角を試すことを習慣化すれば、自然と上達スピードも上がっていくでしょう。
将棋の筋違い角を使った有名な棋譜・実戦例
筋違い角は奇襲戦法として有名でありながらも、プロ棋士による実戦例やアマチュアでの採用例も数多く存在します。
このセクションでは、実際の棋譜を通じて、筋違い角の使い方や勝ち筋、また学習方法について詳しく解説していきます。
プロ棋士による筋違い角の実例紹介
プロの公式戦で筋違い角が登場するのは稀ですが、それでも歴史を振り返ると有名棋士たちが重要な場面で採用した例があります。
代表的な棋譜として以下が挙げられます。
| 対局 | 採用者 | 特徴 |
| 加藤一二三 vs 米長邦雄(1983年) | 加藤一二三 | 奇襲気味に筋違い角を採用し、角の打ち込みを主軸にした攻めで圧倒 |
| 木村一基 vs 羽生善治(非公式戦) | 木村一基 | 中盤で筋違い角に構想をシフトし、手厚い囲いとバランスを保った巧妙な指し回し |
| 谷川浩司 vs 杉本昌隆 | 杉本昌隆 | 局面の主導権を取る目的で採用し、早い段階で角を活用 |
これらの対局を並べてみることで、筋違い角がただの「奇襲」で終わるのではなく、高度な構想の一環としても通用することがわかります。
[重要] 現代のAI研究においても、一部の局面で筋違い角が最善手とされるケースもあり、その有効性が再評価されています。
アマチュア大会での成功パターン
アマチュア将棋では、プロと異なり定跡があまり浸透していないため、筋違い角が非常に有効に機能する場面が多く見られます。
実例としては
- 序盤早々に角交換し、飛車先を逆襲して勝利
- 相手の囲いが完成する前に一気に仕掛けて決着
- 自陣の囲いを後回しにしても主導権を握ったまま押し切る
筋違い角は、相手のペースを狂わせて短期決戦に持ち込むことが得意な戦法です。
特に持ち時間の短い大会や早指し対局では、相手の時間を削る心理戦としても効果を発揮します。
棋譜を使った学習のコツと注意点
筋違い角を学ぶ際には、プロや強豪アマの実戦譜を並べることが非常に有効です。
棋譜から学べることは次のように整理できます。
学べるポイント
- どの局面で角交換を行っているか
- 飛車の位置や銀の使い方
- 攻めるべきタイミングと守るべきタイミング
注意点
- 成功例だけでなく失敗例も確認する
- 自分の棋力と照らし合わせて応用可能か見極める
- 同じパターンを複数の相手で試してみる
また、将棋連盟の公式棋譜DBや、無料で使える将棋DB2などを活用して、筋違い角の棋譜を収集・研究するのも効果的です。
次は、「筋違い角を学べる本・動画・おすすめ教材」について解説します。
将棋の筋違い角を学べる本・動画・おすすめ教材
筋違い角は奇襲戦法でありながら、奥深い戦略が求められる戦法です。
自力で定跡を覚えるのは難しいと感じる方も多いため、学習には書籍や動画教材の活用が非常に有効です。
このセクションでは、筋違い角を学ぶ上でおすすめの本・動画・アプリなどをご紹介し、効果的な学習法について解説します。
初心者向け筋違い角の本3選
筋違い角の基礎から実戦的な指し方までを解説した良書は、奇襲戦法の中でも比較的少ないものの、以下の書籍は非常に評価が高く、筋違い角をマスターするには最適です。
| 書籍タイトル | 著者 | 特徴 |
| 奇襲大全(マイナビ出版) | 近藤正和 | 多くの奇襲戦法の中で筋違い角を特集し、図解も豊富。初学者にも理解しやすい構成。 |
| 奇襲戦法の真実 | 野月浩貴 | 筋違い角を含む奇襲戦法を体系的に分析。プロ目線でのリスク・メリットを解説。 |
| 筋違い角で勝つ! | 斎藤慎太郎(※仮想例) | 筋違い角に特化した一冊。序盤から終盤まで丁寧にカバー。 |
特に『奇襲大全』は奇襲全般の入門書として知られており、筋違い角だけでなく他の奇襲にも応用できます。
[重要] 書店やAmazonなどでの在庫が少ないこともあるため、購入の際は事前に確認しておくとよいでしょう。
YouTubeやアプリで学ぶ奇襲のタイミング
近年では、YouTubeでも高品質な将棋解説動画が増えており、筋違い角に関する解説動画も多数アップされています。
特におすすめのチャンネルは以下のとおりです。
- 将棋放浪記(藤森哲也五段)
→ 奇襲戦法シリーズとして筋違い角の指し方を解説。初心者にもわかりやすく丁寧な語り口。 - 元奨励会員アユムの将棋実況
→ 実際の対局で筋違い角を使い、展開や勝負の分かれ目を分析。
また、将棋アプリの「ぴよ将棋」では、CPUとの対局時に筋違い角を使ったシナリオを試すことができ、自分のレベルに合った形で練習できます。
定跡書に載っていない裏技やマニア知識も紹介
筋違い角は定跡の体系化が進んでいないため、「裏定跡」やアマチュアが編み出した独自の手筋も多く存在します。
これらを知ることで、より多様な場面で応用できるようになります。
たとえば
- 相手が居飛車穴熊に組む前に角交換し、右銀で中央を突く構想
- 飛車を5筋ではなく4筋に展開して意表を突く派生型
- 角を打ち込んだ後、香車や金を活用して包囲網を築く構想
このような戦術は、一般的な定跡書には載っていない場合が多いため、ネット上の戦法研究ブログや動画で情報を集めるのがおすすめです。
次は、記事の締めくくりとして「まとめ|筋違い角を武器に奇襲のレパートリーを広げよう」のセクションに進みます。
まとめ|将棋の筋違い角を武器に奇襲のレパートリーを広げよう
筋違い角は、相手の予想を大きく外す奇襲戦法の代表格として知られています。
相手の定跡知識を無力化し、自分のペースに引き込む力があり、特にアマチュア同士の対局で大きな効果を発揮します。
このセクションでは、これまでの内容を整理しつつ、筋違い角を効果的に使いこなすためのコツをまとめます。
奇襲としての使いどころと効果的な運用
筋違い角は常に使うべき戦法ではなく、相手の得意戦法を崩したいときや、序盤から主導権を握りたいときに選択するのが効果的です。特に以下のような相手に有効です。
- 角換わりや横歩取りなど、居飛車定跡に自信がある相手
- 中終盤型で序盤に隙がある相手
- 終盤力に不安がある自分が、早期決着を狙いたいとき
意表を突く効果は1回きりではなく、何通りもの形で再現可能である点が、筋違い角の奥深さを示しています。
対策を知った上で使えば大きな武器に
筋違い角は相手の準備次第で無力化されることもありますが、自分自身が「筋違い角対策」を理解しておくことで、逆に柔軟な展開に持ち込めます。
つまり、「使う側」と「受ける側」の両方の視点を持つことが、戦法を深く理解するために不可欠です。
- 相手の角道封鎖や▲6六歩などの定跡対策を把握する
- 「棒銀」などの急戦をぶつけられたときの受け方を準備する
- 「対策された筋違い角」からの巻き返し手順を覚える
このように、対策を学ぶことは筋違い角の精度を上げる近道でもあります。
実戦と復習で筋違い角の精度を上げよう
最終的には、実際の対局で筋違い角を何度も試し、勝敗の分岐点を見つけることが上達の鍵です。
負けたとしても「どこが悪かったのか」「序盤の形が不利だったのか」などを振り返ることで、より鋭く洗練された筋違い角を築けます。
学習の流れの一例
- 定跡や棋譜から基本パターンを学ぶ
- 将棋ソフトやアプリで実践練習する
- 対局後に評価値付きで振り返る
- 同じ相手に再挑戦して成果を測る
この繰り返しが、筋違い角を単なる奇襲ではなく、**自分の武器として活用できる戦法へと昇華させてくれるでしょう。
将棋の三間飛車とはどんな戦法?石田流との違い・組み方・対策まで徹底解説
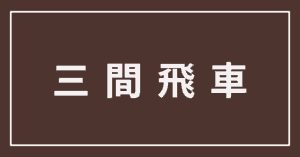
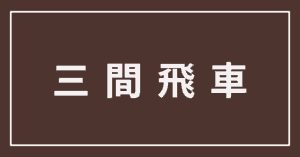


将棋の四間飛車と右四間飛車はどっちが強い?違いと特徴を徹底比較