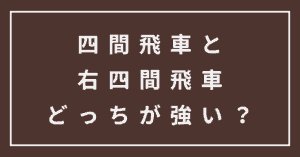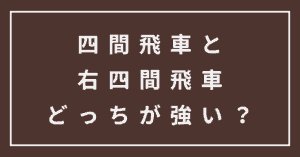将棋には数多くの戦法が存在しますが、その中でも異彩を放つのが「嬉野流(うれしのりゅう)」です。
プロの公式戦ではほとんど見られないにもかかわらず、アマチュアの間では密かに人気を集めているこの戦法。
一見すると定跡を無視したような指し方に見えますが、実はれっきとした奇襲戦法であり、相手の定跡研究を崩すのに非常に効果的です。
この記事では、嬉野流の基本的な指し方から、有効な場面、対策方法、学べる本・動画、実戦例までを詳しく解説します。
奇抜で自由なこの戦法に興味を持った方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
あなたのレパートリーに嬉野流が加われば、相手の意表を突く一手になるかもしれません。
将棋の戦法一覧|初心者向けから最強戦法・奇襲型まで完全解説!


◆アプリダウンロード数4,000万突破!


将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、
【 ABEMA
プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。
>> 将棋見るならABEMA
将棋の嬉野流とは?奇襲戦法としての特徴と由来
嬉野流(うれしのりゅう)は、一般的な将棋の定跡とは一線を画した“奇襲戦法”のひとつとして、アマチュアの間で人気を集めています。
プロ公式戦での採用例はほとんどありませんが、相手の研究を外し、自由な展開に持ち込めることから、特に初中級者にとって魅力的な戦法です。
嬉野流の名前の由来と誕生の背景
嬉野流という名前は、アマチュア将棋指しの「嬉野宏明」さんがインターネット掲示板(2ちゃんねる)などでこの戦法を紹介したことから広まりました。
具体的な誕生年は不明ですが、2000年代にネット上で話題になり、徐々に「定跡破りの奇襲」として知られるようになりました。
なぜ嬉野流は奇襲戦法と呼ばれるのか
嬉野流の最大の特徴は、「角道を止める」という一見するとセオリーに反する動きからスタートする点です。
この一手によって、相手が用意している定跡の流れを崩すことができ、自分のペースで将棋を展開しやすくなります。
通常の将棋では、角道を開けて序盤から角を活用しやすくするのが一般的です。
しかし嬉野流では、序盤で▲7六歩→▲7五歩と突く代わりに、角道をわざと止めたり、銀を早めに出したりすることで、相手の“よくある構想”を封じます。
以下は、嬉野流の代表的な進行です:
| 手順 | 内容 |
| ▲7六歩 | 初手で角道を止める |
| ▲6六銀 | 銀を早めに繰り出す |
| ▲7七角 | 角を自陣に引いて備える |
| ▲5八金右 | 玉の守りを意識した配置 |
このように、嬉野流は定跡から外れた変則的な構えであり、初見では対処に戸惑うプレイヤーも多く、まさに奇襲と呼ぶにふさわしい戦法です。
プロ公式戦での採用例はある?
プロ公式戦では、嬉野流が採用されることはほとんどありません。
なぜなら、定跡に基づかない不安定な構えは、研究が進んでいるプロの世界ではリスクが高いためです。
ただし、ABEMAトーナメントのような早指しイベントやネット対局では、ごくまれに「遊び心」や「意表を突く作戦」として類似の形が見られることもあります。
プロ棋士の「変則作戦」や「奇襲戦法集」の中でも話題になることがあり、まったく使われないわけではありません。
嬉野流の指し方と定跡の基本手順
嬉野流は明確な定跡がある戦法ではなく、「型破り」であることを前提に展開していきます。
しかし、一定のパターンや考え方が存在し、それに従うことで再現性のある奇襲戦法として活用可能です。
以下では、嬉野流の基本的な手順と展開のポイントを紹介します。
嬉野流の基本手順と狙い
まず、嬉野流の代表的な序盤進行を一覧表にまとめました。
| 手数 | 指し手 | 狙い・意味 |
| 1 | ▲7六歩 | 角道を止める。普通とは逆の初手 |
| 2 | ▲6六銀 | 銀を前に出し、素早く攻めの形を作る |
| 3 | ▲7七角 | 角を引いて、6六銀との連携を強化 |
| 4 | ▲5八金右 | 玉の囲いを意識した金の移動 |
| 5 | ▲6八玉 | 最低限の囲いを目指す |
| 6 | ▲2八飛または▲4八飛 | 振り飛車や右四間飛車に移行する柔軟さ |
このように、「角道を止めて銀を繰り出す」という特徴的な形から始まり、相手の囲いや定跡構想を崩しにいくのが嬉野流の狙いです。
嬉野流の中盤構想|柔軟な戦型変化がカギ
嬉野流は序盤で奇をてらった形を作る一方、中盤以降は柔軟な構想が求められます。
以下のような形に変化することが多いです。
- 右四間飛車に変化して、6六銀との連携で速攻を狙う
- 飛車を2八に回して居飛車急戦に移行
- 振り飛車に構えて中央からのカウンターを狙う
このように、嬉野流=序盤奇襲+中盤の柔軟性というのが本質です。
中盤のポイントは以下のとおりです。
- 6六銀を活かす攻め筋を考える(▲6五歩から銀を繰り出すなど)
- 相手の玉の囲いが整う前に動く
- 守備を犠牲にしてでも先手を握る構想を取る
攻めのタイミングを逃すと、一気に不利になるリスクがあるため、タイミングとバランス感覚が非常に重要です。
嬉野流の終盤のコツ|速度勝負を意識せよ
嬉野流は玉の囲いが不十分になりがちで、守りに不安を抱えたまま中盤に突入します。
そのため、終盤では以下のような点に注意が必要です。
- 終盤に突入する前に決定打を狙う
- 玉の逃げ道(7八→6八→5八など)を確保しておく
- 「入玉」や「千日手」を視野に入れた戦略も
嬉野流を成功させるには、スピード勝負に持ち込んで攻め切ることが求められます。
嬉野流のメリットとデメリット|勝率・奇襲効果の検証
嬉野流は定跡から外れた指し回しで相手の動揺を誘うことができる一方で、リスクもはらむ戦法です。
ここではメリット・デメリットを具体的に整理し、どんな場面で有効か、また注意点は何かを解説します。
嬉野流のメリット|奇襲で主導権を握れる
嬉野流最大の強みは、相手の定跡知識を無力化できる点です。具体的には以下のような利点があります。
嬉野流の主なメリット
- 相手が定跡を外されたことで動揺しやすい
- 多くのアマチュアが定跡を前提に指しており、崩れると判断ミスが起きやすい。
- 序盤で主導権を握りやすい
- 6六銀という積極的な構えにより、序盤からプレッシャーをかけられる。
- 意外性のある攻撃でミスを誘える
- 「見たことない形だ…」と悩ませることで、時間や心理的余裕を削れる。
さらに、嬉野流は振り飛車にも居飛車にも転じられる柔軟性があるため、相手の形に応じて臨機応変に対応できます。
嬉野流のデメリット|囲いが不安定で形が悪くなりがち
一方で、嬉野流には大きなリスクも伴います。
特に囲いが脆く、玉が薄い形になることが多いため、受けの展開になると厳しい戦いになります。
嬉野流の主なデメリット:
| デメリットの内容 | 説明 |
| 玉の囲いが甘い | 最低限の囲いにとどまることが多く、終盤の寄せ合いに弱い。 |
| 相手に正しく対処されると不利になる | 定跡を知らない相手には効くが、慣れている相手には通じない。 |
| 構想が難しく崩れやすい | 銀の位置や角の引き方を誤ると、すぐに形が崩れて主導権を奪われる。 |
特に上級者になるほど、嬉野流に対する「受け筋」や「対応」が確立されており、逆にこちらが苦しい展開に追い込まれるケースもあります。
嬉野流の勝率データと評価の傾向
嬉野流の勝率に関しては、プロの対局でのデータはほぼ存在せず、主にアマチュア間やネット将棋での戦績が参考になります。
例えば、将棋ウォーズや将棋クエストのユーザー投稿・SNSなどから見えてくる傾向は以下の通りです。
- 勝率はやや低め(40~45%前後)
- 一定の層には刺さるが、対策されていると苦しい
- レート1500以下の相手には刺さりやすい
- 定跡に強く依存している層を崩せるため有効
- 中級者以上には通じにくい
- 対応力が高く、意図を見抜かれるケースが多い
また、将棋ユーチューバーによる実戦検証でも「刺さる時は一方的」「対策されると一気に崩れる」というピーキーな戦法という評価がされています。
嬉野流の対策と受け方|知っておくべき対応例
嬉野流は奇襲戦法のひとつとして知られていますが、対応策を知っていれば比較的冷静に対処できる戦法でもあります。
ここでは嬉野流に対する具体的な受け方や有効な対策を、戦型ごとに整理して紹介します。
プロ・アマでの代表的な対策パターン
嬉野流に対する基本的な対応として、以下のようなパターンが有効とされています。
| 戦型 | 対策の基本方針 |
| 居飛車党 | 早めに中央を制圧し、6六銀を狙ってプレッシャーをかける |
| 振り飛車党 | 自陣整備を優先し、無理攻めに付き合わない |
| 積極的な急戦型 | 端攻めや棒銀などで角の働きを封じる |
嬉野流は銀を早めに繰り出すため、6六の地点を中心に攻防が起こりやすくなります。
そのため、銀の進出に合わせて中央や角道の攻撃を意識した形を作るのが効果的です。
棒銀や居飛車急戦型での対処法
特に有効とされているのが、「棒銀」や「居飛車急戦型」での対応です。これは嬉野流の急戦に対して、より速い攻撃で先手を取る構想です。
有効な指し筋の例(対居飛車):
▲7六歩 △3四歩
▲6六銀 △8四歩
▲6八玉 △8五歩
▲7八玉 △3二金
▲5六歩 △4二玉
▲4八銀 △6二銀
このように中央を厚くしておき、5筋・6筋方面からの仕掛けを見せつつ、相手の無理攻めを誘導する形が理想です。
対策が難しい場合の安全な受け方とは
嬉野流は意表を突いてくるため、中盤以降の力戦に持ち込まれることもあります。
その場合は、無理に反撃せずに形を整えながら相手の攻めをいなす「安全な受け」も有効です。
安全に受けるためのポイント
- 早囲いを急がず、玉を中央に寄せておく
- 無理に角道を開けず、駒組みに専念する
- 銀が6六に来ても焦らずに、5七や7七で受けを固める
受け重視の構えにすることで、相手の早仕掛けを「空振り」にできれば、後手番でも十分に主導権を握ることができます。
嬉野流は初心者にも使える?成功のコツと注意点
嬉野流は独特な駒組みと意外性で人気の奇襲戦法ですが、「初心者でも扱えるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは、嬉野流が初心者向きかどうか、どのように学べばよいかをわかりやすく解説します。
定跡を覚えすぎず感覚で指せる魅力
嬉野流の最大の特徴は、序盤の定跡知識がほとんど不要な点です。
通常の戦法では「この場面ではこの手」と決まった形がありますが、嬉野流では相手の動きに応じて柔軟に対応するため、以下のようなメリットがあります。
嬉野流の初心者向けポイント
- 定跡書を丸暗記する必要がない
- 感覚で駒を動かしながら考える習慣がつく
- 「考える将棋」の基礎が身につく
したがって、序盤定跡に縛られたくない初心者にこそ向いている戦法とも言えます。
詰め将棋や終盤力が重要になる戦法
一方で、嬉野流は中盤以降が力戦(定跡にない自由な展開)になりやすく、終盤力や読みの深さが試される戦法でもあります。
序盤でリードを奪えないと、以下のような展開になりがちです。
| 状況 | 注意すべき点 |
| 角交換後に形が悪くなる | 無理に攻めず、じっくり受けに回る判断が必要 |
| 玉が薄い状態で終盤に突入 | 受けミスが即詰みに直結する |
| 相手が定跡を熟知していた場合 | 仕掛けが封じられて押し込まれる可能性がある |
そのため、詰め将棋や必死問題などの練習を併用しながら嬉野流を使うことで、より強く・実践的な棋力が身につきます。
初心者が使うときの注意点と練習法
初心者が嬉野流を取り入れる場合、以下のような点に注意すると、戦術として安定しやすくなります。
使う前に知っておきたい注意点
- 角道を不用意に開けすぎない
- 銀の位置取りを常に意識する(6六に早く出すと対策されやすい)
- 玉の囲いを忘れずに構築する(片美濃や金無双など)
また、練習法としては次の3つが効果的です。
- 将棋アプリで嬉野流だけ使ってみる
→習熟度が高まり、手順が自然と体に染みつく。 - YouTubeでプロの実戦解説を視聴
→嬉野流の形がどう崩されるのか、また勝ち筋はどこかがわかる。 - オンライン対局で10分切れ負けを繰り返す
→実践で咄嗟の判断力が身につく。
嬉野流の棋譜・実戦例とプロ棋士の評価
嬉野流は奇襲戦法の中でも知名度が高く、多くの将棋ファンが関心を持っています。
実際の棋譜を見てみることで、嬉野流の魅力や限界、どのような場面で力を発揮するかがより明確になります。
この章では、プロ・アマチュアの実戦例や棋譜から見える戦術の特徴、プロ棋士の評価について解説します。
プロ公式戦での嬉野流の採用例はある?
嬉野流は主にアマチュアで広く使われている戦法ですが、プロ棋士の公式戦で使われることはほとんどありません。
その理由としては以下が挙げられます。
| 理由 | 内容 |
| 再現性の低さ | 相手が対応を知っていると成立しにくい |
| 攻守のバランス | 序盤から玉が薄くなるリスクがある |
| 序盤の奇襲性 | 一度読まれると同じ仕掛けが通用しない |
ただし、研究会や練習対局、企画対局では採用されることもあり、ネタ戦法としてプロも一度は試すことのある「知名度の高い奇襲」という立ち位置です。
アマチュア実戦例で見せた鮮やかな勝利
アマチュアの実戦では、嬉野流がハマると鮮やかな勝利を得られる例が多くあります。
例えば、以下のような流れが典型的な勝ちパターンです。
【嬉野流アマ実戦パターン】
- 角交換から相手の囲い構築を妨害
- 銀を早めに前線に出して牽制
- 相手の陣形が整う前に▲7五歩などで仕掛け
- 玉形が乱れたところに飛車や角で一気に寄せる
このように、相手が定跡外の進行に慣れていないと、あっという間にペースを握れるのが嬉野流の強みです。
実戦では勝率も高めで、特に10分切れ負けなどスピード勝負の将棋で効果を発揮します。
棋譜を通して学べる嬉野流のポイント
棋譜を並べることで、嬉野流の流れや注意点を視覚的に理解することができます。
おすすめの学習方法としては以下の通りです。
- 将棋DB2や将棋ウォーズの棋譜検索機能を活用
- 嬉野流のキーワードで絞り込み、勝ちパターンを研究
- 局面ごとの感想戦を行い、「どこがポイントだったか」を分析
特にアマチュア間では、「初手▲7六歩、△3四歩、▲6六歩」という独特な出だしから始まる棋譜が多く、嬉野流の特徴が色濃く出ているため、勉強に適しています。
[重要] 棋譜学習では「勝った将棋」だけでなく「負けた将棋」も確認することで、リスクや反省点も身につきます。
嬉野流を学べる本・動画・おすすめ教材
嬉野流はマイナーな奇襲戦法であるため、定跡書や専門書籍が少ないのが現状です。
しかし、YouTubeや棋譜サイト、個人ブログなどで多くの解説が公開されており、独学でもしっかり学べる戦法です。
このセクションでは、嬉野流を学ぶのに役立つ本・動画・アプリ・棋譜サイトなどの教材を紹介します。
嬉野流の特徴を解説したおすすめ書籍
嬉野流に特化した書籍はほとんど存在しませんが、以下のような本に一部記述や類似形の紹介があります。
| 書籍名 | 特徴 | 対象者 |
| 奇襲大全(マイナビ出版) | 嬉野流を含む様々な奇襲戦法を網羅 | 奇襲を広く学びたい人 |
| アマの知らない急戦のウラ定跡(浅川書房) | 急戦・奇襲対策としての考え方も掲載 | 嬉野流への対策を知りたい人 |
| ひと目の奇襲戦法(日本将棋連盟) | 筋違い角や端攻めなどとあわせて紹介 | 初級〜中級者向け |
※2025年時点で「嬉野流」に特化した専門書は未出版です。
YouTubeで学べる嬉野流の動画講座
YouTubeにはアマチュアや元奨励会員による嬉野流の解説動画が複数あり、無料で学べるコンテンツとして非常に充実しています。
人気チャンネル例
- 将棋放浪記
→ 実戦形式で嬉野流の基本や応用を解説 - アゲアゲ将棋実況
→ 嬉野流 vs 各戦法のリアル対局例が見られる - 元奨励会員アユムの将棋実況
→ 細かい狙いやリスクについて詳しい解説あり
また、将棋ウォーズ実況動画でも「嬉野流で勝つ」企画が多く、実戦の流れや組み方がイメージしやすくなっています。
アプリ・棋譜サイトで研究しよう
スマホアプリや将棋データベースを活用すると、嬉野流の勝率や指されるタイミングなどのデータ分析も可能です。
| ツール名 | 活用方法 |
| 将棋ウォーズ | 嬉野流で実戦→振り返りが可能 |
| 将棋DB2 | 嬉野流の棋譜を検索、再生可能 |
| ぴよ将棋 | 嬉野流の形にしてAIと対戦、分析可能 |
| Kento(PCソフト) | 棋譜解析と局面評価に優れる |
[重要] 嬉野流はAI評価が低く出やすいため、実戦で使うことを前提に「人間同士の感覚」で評価することが大切です。
まとめ|嬉野流を武器に奇襲の幅を広げよう
最後に、嬉野流の特徴や使いどころを振り返りつつ、実戦で活かすためのポイントを整理します。
嬉野流の特徴と狙いを理解しよう
- 独特な玉の囲い方(右玉風)
- 角交換から銀を繰り出す攻撃型
- 相手の定跡や囲いを乱すのが目的
嬉野流は定跡を無視した序盤構成が特徴であり、相手の対応力を試すような将棋になります。
奇襲としての効果と注意点
- 奇襲として一発勝負では強力
- ただし、一度読まれると効かない
- 「使いどころ」と「タイミング」が重要
初対面の相手や級位者には効果的ですが、同じ相手には通じにくくなるため、奇襲としての運用が理想です。
嬉野流を成功させるための練習法
- 実戦→振り返り→改善のサイクルが大事
- 局面ごとに複数の変化を想定しておく
- 囲いと攻めのバランスを意識する
「嬉野流を主力にする」よりも、「嬉野流をレパートリーの一つとして持つ」方が実戦的です。


将棋の四間飛車と右四間飛車はどっちが強い?違いと特徴を徹底比較