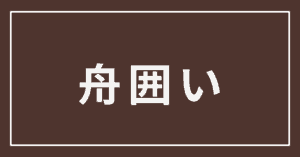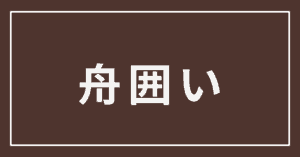将棋にはさまざまな囲いがありますが、「右玉(みぎぎょく)」はその中でも独特の存在感を放つ戦法です。
王将を右側に残したまま戦うという、他の囲いとは一線を画した構えは、柔軟性と奇襲性を併せ持つため、プロ・アマ問わず注目されています。
この記事では、右玉の読み方・歴史・特徴・組み方・メリットと弱点、さらに糸谷流右玉や対策方法、おすすめ棋書や定跡本までを網羅的に解説します。
初心者でも理解できるように図やリストも交えて紹介していきます。


◆アプリダウンロード数4,000万突破!


将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、
【 ABEMA
プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。
>> 将棋見るならABEMA
右玉戦法とは?読み方・特徴・歴史を解説
右玉は、王将を定位置より右側に構えたまま戦う戦法です。
居飛車の変則的な囲いとして扱われ、時に相手の虚を突く一手として採用されることがあります。
ここではまず、右玉の基礎知識として「読み方」「特徴」「歴史」を押さえておきましょう。
「右玉」の読み方と意味とは?
「右玉」は“みぎぎょく”と読みます。これは単純に、「王将(玉)を右側に置いたまま戦う形」であることから名づけられました。
多くの囲いでは、王将を左(玉頭)側に移動して守る形が基本ですが、右玉ではあえて初期位置付近に残し、中央や右辺での戦いに備えるのが特徴です。
右玉戦法の歴史と生まれた背景
右玉戦法の起源は明確ではありませんが、古くは江戸時代の将棋指南書にもその形が記されていたと言われています。
昭和以降になると、アマチュアの大会などでしばしば採用されるようになり、特に1990年代以降はプロ棋士・糸谷哲郎八段が積極的に採用したことで脚光を浴びました。
また、振り飛車党の棋士が右玉を使うことで居飛車党に奇襲をかけたり、力戦模様に持ち込む意図でも使われるなど、柔軟性と意外性を併せ持つ囲いとして注目されています。
初心者にも使いやすい囲い?特徴と基本の考え方
右玉の最大の特徴は「構えがシンプルであること」と「柔軟な指し回しが可能なこと」です。
【右玉の特徴まとめ】
| 特徴項目 | 内容 |
| 王将の位置 | 初期位置から右側に動かし、金銀でカバーする囲い |
| 柔軟性 | 中央〜右辺の戦いに強く、変化に対応しやすい |
| 奇襲性 | 相手が左玉を想定している場合、戦型の読みを外せる |
| 構えの簡素さ | 複雑な囲いより組みやすく、初心者にも手順がわかりやすい |
ただし、王将の周囲が狭くなるため、端攻めや斜めからの攻撃に弱いという側面も持っています。
そのため、玉の囲い方と銀・金の配置に注意を払う必要があります。
右玉囲いのメリットと弱点|どんな戦型に有利?
右玉囲いには他の囲いにはないメリットがありますが、当然ながら明確な弱点も存在します。
このセクションでは、それぞれの特徴を具体的に解説し、右玉が活躍しやすい局面や戦型についても紹介します。
右玉のメリット|柔軟性・意表を突ける構え
右玉囲いが評価される最大の理由は、その柔軟性と意外性にあります。
以下に具体的なメリットを整理します。
【右玉のメリット】
| メリット | 説明 |
| 柔軟な攻守 | 玉を中央に近い位置に置くことで、左右どちらにも動ける構えになる |
| 奇襲性 | 相手が玉を左に寄せる前提で対策している場合、構想を外せる |
| 構えの簡潔さ | 金銀の移動が少なく、初心者でも組みやすい |
| 時間短縮 | 駒組みに時間がかからず、速攻に移れる |
| 駒の連携が良い | 中央〜右辺での攻防が多いため、飛車や角の展開がスムーズ |
特に短時間将棋や将棋ウォーズのような早指し対局では、複雑な囲いを組む余裕がなく、右玉の簡便さが活きてきます。
また、「あれ?囲ってないぞ?」と相手に違和感を与えることができる点も、隠れた強みです。
右玉の弱点|囲いとしての脆さとリスク
一方で、右玉は「囲い」としての堅牢さに欠けるため、過信は禁物です。
以下に代表的な弱点を整理しました。
【右玉の弱点】
| 弱点項目 | 内容 |
| 横からの攻めに弱い | 王将の周囲が狭く、端攻めや飛車先突破に対して脆い |
| 寄せに耐えにくい | 金銀の密集度が低く、持久戦になると押し切られる可能性がある |
| 対策されやすい | 右玉に慣れた相手には棒銀や角交換を含む攻め筋で弱点を突かれやすい |
| 振り飛車に不向き | 振り飛車相手では守備駒が偏りやすく、バランスが崩れる可能性がある |
特に棒銀や角交換からの速攻には注意が必要で、右玉にしていることで玉の逃げ道が確保できずに詰まされるリスクもあります。
守りを固めるために金銀の配置を工夫しつつ、場合によっては途中で囲いを変化させる柔軟さも必要です。
右玉が有利に働く局面や戦型とは?
右玉は力戦模様や相手の形が定まっていない中盤戦で真価を発揮します。
特に有効とされる局面を以下にまとめました。
【右玉が有利に働く局面】
- 居飛車 vs 居飛車の力戦型
- 相手が囲いに時間をかけすぎた場合
- 早囲いで速攻を仕掛けたい場面
- 右四間飛車や片美濃を狙う布石として
また、「糸谷流右玉」など一部の流派では、右玉からの急戦仕掛けを戦術の中心に据えており、構えから攻めへの展開が非常にスムーズです。
右玉囲いの基本の組み方と手順|初心者でもわかる解説
右玉囲いは、初心者にも比較的簡単に組める囲いの一つです。
ここでは、実際の手順や注意点を図やリストを交えてわかりやすく解説します。
右玉の駒組み手順|最短6手で完成する基本形
右玉囲いは、「玉を右辺に移動させる」だけで成立する非常にシンプルな構えです。
以下が、基本の右玉囲いの駒組み手順です。
【右玉囲いの基本駒組み(先手の場合)】
| 手順 | 指し手 | 解説 |
| 1 | ▲7六歩 | 角道を突いて通常の居飛車開始 |
| 2 | ▲6八銀 | 左銀を上げて玉を右へ動かす準備 |
| 3 | ▲7八金 | 金を右に上げて玉の逃げ道を確保 |
| 4 | ▲5八玉 | 玉を中央に寄せておく |
| 5 | ▲4八玉 | さらに右へ移動 |
| 6 | ▲3八玉 | 右玉囲いの基本形が完成 |
この形を取るだけで、右玉の構えとして成立します。
そこから先は攻めの展開や相手の囲いに応じて柔軟に変化させていくことになります。
右玉を囲いとして安定させるには?金銀の配置の工夫
右玉囲いの初期形は簡単に作れますが、そのままでは守りが不十分です。
玉の周囲に金銀を配置して安定させる工夫が必要になります。
【補強の駒組み案】
- ▲2八銀 or ▲3八銀:玉の横を守る
- ▲2八金:端攻めへの備え
- ▲4八金:中央からの攻めをケア
これにより、右辺の防御力を高めつつ、中央や左辺へも柔軟に対応できます。
以下は補強した形の例です。
※実際の図面は将棋ソフトなどを使って確認するのがおすすめです。
初心者が右玉を使うときの注意点とコツ
初心者でも右玉囲いは使えますが、いくつかの注意点があります。
以下のポイントを意識しましょう。
【初心者が意識すべきポイント】
| 項目 | 内容 |
| 1. 玉の位置 | 玉は端に寄せすぎず、逃げ道を確保する |
| 2. 金銀の連携 | 金銀がバラバラにならないように並べる |
| 3. 攻め急がない | 守備が整うまでは不用意に攻めない |
| 4. 定跡を覚える | 糸谷流や基本定跡を軽く頭に入れておくと有利 |
| 5. 組み替えに慣れる | 途中で矢倉や舟囲いに変化させるパターンも練習しておくと柔軟に対応可能 |
右玉は「守りの囲い」と「攻めの起点」を同時に満たす非常に戦略的な構えです。
基本形を習得しておくだけで、序盤の選択肢がグッと広がります。
右玉囲いの歴史と有名棋士|糸谷流右玉とは?
右玉囲いは近年注目を集めている戦法ですが、実は古くから存在していた構えです。
ここではその歴史と代表的な棋士、そして現代将棋で注目された「糸谷流右玉」について解説します。
右玉囲いの歴史|古典から現代までの変遷
右玉囲いは、江戸時代の古典将棋書にも登場する伝統ある構えです。
元々は定跡化されていなかったものの、独自性や柔軟性のある戦法として少数派ながら研究されてきました。
【右玉囲いの歴史の流れ】
| 時代 | 内容 |
| 江戸時代 | 変則囲いのひとつとして一部の指南書に登場 |
| 昭和〜平成初期 | 基本的にはマイナー戦法。一部のアマ強豪やプロが研究していた |
| 平成中期 | 糸谷哲郎八段(当時)が公式戦で右玉を多用。知名度と評価が高まる |
| 現代 | 対振り飛車・棒銀対策として、初心者にも注目される実践的な囲いに進化 |
このように、右玉は長い間「変則的な構え」として扱われてきましたが、近年は実戦的な有力戦法として評価されています。
糸谷哲郎八段と「糸谷流右玉」の登場
現代将棋において右玉囲いを一躍メジャーにしたのが、糸谷哲郎八段(当時)です。
独創的な棋風で知られる糸谷八段は、公式戦で右玉を駆使し、プロ間でも注目される存在となりました。
【糸谷流右玉の特徴】
- 初手▲7六歩からの居飛車志向
- 玉を3八に早く囲うことで、中央・右辺の攻防に備える
- 角交換・急戦への柔軟な対応力
- 囲いより攻撃重視の構え(バランス型)
糸谷流は特に角交換振り飛車に対して高い勝率を誇り、「攻めながら囲う」スタイルが現代将棋とマッチしました。
右玉囲いを得意とするプロ・アマの棋士たち
糸谷八段の影響で右玉は広く注目されるようになり、以下のようなプロ・アマ棋士が使用しています。
【右玉を多用する棋士】
| 棋士名 | 使用例/評価 |
| 糸谷哲郎八段 | 代表格。多数の公式戦で使用し右玉=糸谷流として浸透 |
| 畠山成幸八段 | 早い段階から右玉に着目し独自の解釈を披露 |
| アマ強豪 | 対振り飛車で右玉を好むアマチュア強豪多数 |
近年は女流棋士やネット将棋の強豪たちも研究を重ねており、定跡の一部として右玉を使う機会も増えています。
右玉囲いのメリットと強み|他の囲いとの比較
右玉囲いは一見するとシンプルな構えですが、戦術的に非常に柔軟性があります。
ここでは、右玉のメリットや他の囲いとの違いを掘り下げ、なぜ注目されるようになったのかを具体的に見ていきましょう。
右玉囲いの主なメリットとは?
右玉の最大の魅力は、その柔軟性とスピードにあります。以下に、右玉の代表的なメリットを挙げます。
【右玉囲いのメリット一覧】
| メリット | 解説 |
| 囲いの構築が早い | 玉を右に移すだけで形が整うため、囲いに時間をかけず攻撃に移行できる |
| 中央からの攻めに強い | 玉が右にあるため、中央・左辺からの攻めを受けやすく、バランスが取れている |
| 対振り飛車に有効 | 特に角交換型や三間飛車に対して堅実に対応できる |
| 奇襲戦法に対応しやすい | 柔軟な陣形のため、急戦や変則型にも自然に対応できる |
| 攻めと囲いの一体化が可能 | 攻めを意識しつつ、自然と囲いが完成する構成が多い |
このように、右玉は構えを完成させるまでが早く、その後の展開にも多彩な対応ができるため、実戦派にとって非常に扱いやすい囲いといえます。
他の囲いとの違いと比較
他の有名な囲い(美濃囲い、舟囲い、矢倉囲いなど)と比較すると、右玉には独自の長所があります。
【囲い比較表|右玉 vs 他囲い】
| 囲い名 | 安定性(受け) | 速さ(囲い完成) | 攻撃との両立 | 対振り飛車相性 |
| 右玉囲い | △ 中程度 | ◎ 非常に速い | ◎ 高い | ◎ 良好 |
| 美濃囲い | ◎ 高い | ○ 速い | △ 受け重視 | ◎ 非常に良い |
| 舟囲い | ○ 平均的 | ◎ 速い | △ 守備重視 | ○ 良好 |
| 矢倉囲い | ◎ 非常に高い | △ 遅い | ○ バランス型 | △ 苦手 |
右玉囲いは全体的に「速さと攻撃力」に特化しており、「美濃囲い」「舟囲い」「矢倉」と比べても対振り飛車との相性が非常に良いことがわかります。
特に優れているのは対振り飛車と棒銀対策
右玉囲いが実戦で注目されるのは、対振り飛車に対する優位性と、棒銀対策としての機能です。
【右玉囲いが強い理由】
- 振り飛車の端攻めに強い: 右に玉を構えることで左辺の端攻めが効きにくくなる。
- 中央からの反撃が速い: 中央に厚みを作りやすく、角道・銀桂が連動しやすい。
- 棒銀に対しては引き角+金銀連携が有効: 相手の一直線の攻めを受けやすく、カウンターも可能。
これらの特徴は、角交換型の将棋や急戦系の戦型で非常に力を発揮します。
初心者にもおすすめできる囲い
右玉囲いは初心者でも扱いやすいという評価もあります。
特に、「玉を囲う」ことを覚える初期段階において、シンプルで形がわかりやすいため、導入に最適です。
【初心者に向いている理由】
- 駒組みが単純で覚えやすい
- 囲いに時間がかからないので中盤の学習に集中できる
- 対応できる戦法が多く、学びながら実践経験を積みやすい
このような利点から、右玉は実戦経験を積むための最初の囲いとしても重宝されます。
右玉囲いの組み方と定跡・基本形を図解で解説
右玉囲いは、実戦にすぐ使える実用的な囲いとして知られています。
ここではその作り方や基本定跡、典型的な駒組みのパターンを丁寧に紹介していきます。
右玉囲いの基本的な駒組み手順
右玉囲いを組む手順は非常にシンプルで、駒の配置も覚えやすい構成になっています。
以下に標準的な組み方をリスト形式で示します。
【右玉囲い 駒組み手順(先手の場合)】
- ▲7六歩(角道を開ける)
- ▲6八銀(銀を上がる)
- ▲5六歩(中央を押さえる)
- ▲5八金右(金を中央に)
- ▲4八玉(玉を右に寄る)
- ▲3八玉(さらに右へ)
- ▲2八銀 or ▲2八金(玉の右に壁を作る)
この手順により、右側に玉を寄せた簡易な囲いが完成します。
金銀のバランスも良く、すぐに攻撃態勢に入れるのが特徴です。
図解で見る右玉囲いの基本形
以下は、右玉囲いの基本陣形を視覚的にイメージできるよう図解したものです(先手番)。
このように、玉を3八(または2八)まで移動し、周囲を金銀で守る形が右玉の基本です。
右玉の定跡パターンと組み替え例
右玉は柔軟な囲いなので、定跡といっても決まった一本道があるわけではありません。
対戦相手の戦型に応じて、以下のような組み替えが可能です。
【右玉からの発展パターン例】
| 相手戦法 | 推奨囲い変化 | 解説 |
| 四間飛車 | 金銀を中央に寄せて中住まい風 | 中央からの反撃力を高める配置 |
| 三間飛車 | 金を高く上げる高美濃風 | 銀桂の連携で中央・左への対応力を確保 |
| 相掛かり・棒銀 | 引き角+銀の連携で堅守 | 右銀を5七、角を8八に構えると受けに強い |
| 居飛車急戦 | 金を6七、銀を7六へ展開 | 相手の急戦に備えて受けを固める |
このように、右玉はそのままでも戦えますが、相手の動きに応じて変化させやすいのも大きな強みです。
糸谷流右玉と基本右玉の違い
プロ棋士・糸谷哲郎八段が実戦で用いる「糸谷流右玉」は、基本形とは少し違う構えになっています。
ここでは両者の違いを簡潔に比較してみましょう。
【糸谷流 vs 基本右玉】
| 項目 | 基本右玉 | 糸谷流右玉 |
| 玉の位置 | 3八または2八 | 2八または1八 |
| 銀の構え | 6八銀~5七銀 | 6八銀~7七銀(角の動きと連動) |
| 角の位置 | 基本は8八に待機 | 積極的に角交換し、角を活用 |
| 戦法の性質 | 受け重視/柔軟に対応可能 | 攻撃的/角のラインからの圧力が特徴 |
糸谷流は、角の早期交換や積極的な桂の跳ねが特徴で、やや上級者向けの右玉戦法といえます。
右玉を使う際に気をつけるべきポイント
囲いが速くできる右玉ですが、当然ながら注意点もあります。
- 玉の位置が浅く、終盤に詰まされやすいことがある
- 相手の攻め筋にすぐにさらされやすい
- 受けが不十分なまま攻めに出ると即反撃を受ける
そのため、金銀の連携を強化し、守りのバランスを保ちつつ攻めに転じることが重要です。
右玉の弱点と対策|どう崩すか・どう守るか
右玉は自由度が高く柔軟な囲いですが、いくつかの明確な弱点も抱えています。
このセクションでは、右玉の防御面の脆さや、相手が採用してきた場合の効果的な対策方法を紹介します。
右玉囲いの主な弱点とは?
右玉には初心者でも扱いやすいという利点がありますが、守りにおいてはいくつかのリスクがあります。
以下に代表的な弱点を整理します。
【右玉の弱点一覧】
| 弱点項目 | 説明内容 |
| 玉の囲いが浅い | 玉が3八・2八に位置するため、終盤での寄せに弱く、詰みに持ち込まれやすい |
| 攻めと守りの分離 | 玉と攻め駒の距離が遠いため、カウンターを受けると守りに戻りにくい |
| 右側からの攻撃に脆い | 相手の左銀や桂馬の進出で、玉の真正面から攻められると受けが困難 |
| 成り駒が集中しやすい | 駒を捌かれて敵陣に侵入されると、狭い陣形に成り駒が集中してしまう |
これらを理解した上で、自分が使う際にも守りの意識を持ち、相手が使う際にはこれを突くような展開を意識しましょう。
右玉の典型的な崩し方・攻略法
右玉を崩す際には、その特有の「浅い玉形」や「右側の壁の弱さ」に注目します。
特に有効とされるのが「棒銀」や「左美濃急戦」などの直接攻めです。
【右玉への有効な攻め筋】
- 左からの棒銀(▲7五歩~7四銀)で壁銀を崩す
- 飛車を5筋や6筋に回して横から圧力をかける
- 角交換からの8六馬(後手なら2四馬)で玉頭を押さえる
- 桂馬を跳ねて頭を狙う(7七桂や2二桂)
これらの攻め筋を使うと、玉が逃げるスペースが狭い右玉に対して詰み筋が見えやすくなります。
右玉に強い戦法|棒銀対策にも注目
右玉を使っている時、相手が棒銀で襲ってきた場合の対処法を理解しておくと安心です。
ここでは、右玉を崩しにくくする対抗手段をいくつか紹介します。
【右玉で棒銀を防ぐには?】
| 対策 | 説明内容 |
| 金を5七→6六に | 銀の頭を守る位置に金を置くと、壁を強化できる |
| 角を8八→7七に | 角で銀の頭を間接的にカバーし、飛車との連携も取りやすい |
| 銀を7七に上げる | 銀が前に出ることで、銀桂の連携が生まれ、攻めにも使える |
| 飛車を8八に戻す | 防御飛車として飛車を玉側に配置し、受けと攻めを両立する |
こうした工夫により、右玉の持ち味を損なわずに守りを補強することが可能です。
右玉を安全に使うための工夫と心構え
右玉を使う上で最も大切なのは、無理な攻めに出ないことと玉の逃げ道を確保しておくことです。
守りを固めながら、中央や左サイドに攻めの拠点を作ることで安定感が増します。
【右玉運用のポイント】
- 玉の周囲に金銀をバランス良く配置する
- 玉の後ろにスペースを空けて、詰みにくくする
- 相手の攻撃ラインに早めに備える(歩や角を使ってコントロール)
- 駒が玉から離れすぎないように展開する
これにより、終盤でも粘り強く戦える布陣となります。
右玉に強い戦型とは?相性の良い指し方を知る
右玉は居飛車・振り飛車のどちらにも柔軟に対応できますが、特に相性が良いのは「急戦型」や「中央突破型」です。
右玉は自玉の囲いが早く完成するため、速攻にも対応しやすい構造です。
【右玉に合う戦型】
| 戦型 | 理由 |
| 急戦型 | 玉が早く囲えるため、相手よりも先に仕掛ける展開に持ち込める |
| 右四間飛車 | 自陣に玉を寄せつつ、左翼から速攻できる |
| 中央突破型 | 玉を安全に囲いながら中央の歩を押して主導権を得られる |
自分のスタイルに合う戦型と組み合わせることで、右玉の可能性を最大限に引き出せます。
右玉の棋譜と定跡を学べるおすすめ書籍・棋書・動画
右玉を深く理解するには、棋譜の研究と定跡知識が欠かせません。
このセクションでは、右玉を体系的に学びたい方に向けて、書籍・棋譜・動画といったリソースを紹介します。
右玉の定跡を学ぶのに最適な書籍・棋書
右玉は一般的な囲いとは異なり定跡書の数も限られていますが、いくつかの名著や特化型棋書が存在します。
特に「糸谷流右玉」に関しては、プロ監修の定跡解説本も出版されています。
【右玉に関するおすすめ棋書一覧】
| 書籍タイトル | 著者 | 特徴と内容 |
| 右玉伝説 | 糸谷哲郎 | 糸谷流右玉の基本と応用、戦術まで解説された唯一の専門書 |
| 右玉入門 | 杉本昌隆 | 初心者向けの右玉解説。基本的な指し方と陣形、狙いを図解で学べる |
| 対振り飛車の右玉戦法 | 所司和晴 | 対振り飛車に特化した右玉の指し方と対策が網羅された1冊 |
| プロの実戦から学ぶ変則囲い | 屋敷伸之 他 | 右玉を含む変則囲いの実戦活用法と崩し方を解説 |
※一部書籍は絶版となっているため、中古市場や電子書籍での入手をおすすめします。
右玉の代表的な棋譜|プロの実戦から学ぶ
右玉を実際の対局でどのように活用しているかを見るのが、上達への近道です。
特に糸谷哲郎九段の実戦や、右玉マスターとされるプロ棋士の棋譜は、学ぶべきポイントが多く含まれています。
【注目の右玉実戦棋譜】
- 糸谷哲郎 vs 藤井聡太(非公式戦)
→ 糸谷流右玉の本格的運用と、急戦への対応が見どころ。 - 久保利明 vs 豊島将之(王位戦)
→ 相振り飛車戦における右玉の粘り強さが光る一局。 - 羽生善治 vs 佐藤天彦(NHK杯)
→ 定跡外の攻防と右玉特有の柔軟な駒組みに注目。
棋譜は「将棋DB2」「将棋ウォーズ棋譜検索」「81道場棋譜検索」などの無料サイトでも閲覧可能です。
右玉を学べるおすすめYouTube・動画講座
映像で学びたい方には、YouTubeをはじめとする動画教材も非常に有用です。
右玉の組み方から定跡、実戦譜の解説まで、さまざまなレベルに対応しています。
【YouTubeでおすすめの右玉動画】
| チャンネル名 | 動画内容と特徴 |
| 将棋放浪記 | 糸谷流右玉の解説シリーズ、プロの実戦を初心者向けに分かりやすく解説 |
| 元奨励会員アユムの将棋実況 | 組み方や定跡、対策を実戦形式で紹介。右玉に対する有効な戦法もあり |
| あゆチャンネル | 対振り飛車右玉や中央突破型などの右玉展開が中心 |
| 木村一基チャンネル | 講座形式での右玉入門動画あり。考え方や囲いの歴史も解説 |
動画で学ぶ利点は、視覚的に駒組みや崩し方を理解しやすい点にあります。
特に初心者には非常におすすめです。
右玉の組み方を練習できるアプリ・ソフト
右玉は指し慣れないと陣形を崩しやすいため、反復練習が重要です。
スマホアプリや将棋ソフトを使って、自分で右玉を何度も組んでみるとよいでしょう。
【右玉学習に使えるツール】
- 将棋ウォーズ(スマホアプリ)
→ 実戦で右玉を試せる。棋神解析で自分の弱点も分析可能。 - 将棋クエスト
→ 短時間で数多く対局でき、右玉の練習に最適。 - 将棋所+やねうら王
→ 強力なAIとの練習が可能。定跡書を自作して右玉を学習できる。
右玉を学ぶ上での注意点とおすすめの学習順序
右玉は自由度が高いため、学び方に順番をつけることが大切です。
いきなり応用から入るのではなく、基本的な組み方からスタートしましょう。
【右玉習得のステップ】
- 右玉の基本陣形を覚える(囲い方)
- 糸谷流右玉などの定跡型を学ぶ
- 代表的な崩し方と対策を覚える
- プロの棋譜や動画を繰り返し観る
- 自分で実戦で使ってみる
右玉は一見シンプルに見えて、奥が深い戦法です。
何度も繰り返して指すことで、自分だけのパターンを確立できます。
まとめ|右玉戦法の魅力と今後の活用法
右玉戦法は、その独自性と柔軟性から、多くの将棋ファンや上達を目指す学習者に支持されています。
このパートでは、右玉戦法を学ぶ意義や魅力、今後の実戦への活用方法を整理します。
右玉戦法の魅力とは?
まずは右玉がなぜ多くの棋士・将棋ファンに支持されるのか、その理由を明確にしておきましょう。
【右玉の魅力をまとめた表】
| 魅力ポイント | 内容 |
| 柔軟性が高い | 囲いの形を状況に応じて変化させられる |
| 構えがバレにくい | 一般的な定跡にハマらず、相手に狙いを読まれにくい |
| カウンター狙いが可能 | 相手の攻めを受け止めてからの反撃が得意 |
| 対振り飛車に有効 | 対抗形でも角道を止めずにバランス良く構えられる |
| 詰み筋の応用が豊富 | 王様が自陣右側にいることで詰みパターンが広がる |
| プロでも採用される戦法 | 糸谷哲郎九段など、実戦での採用例が豊富で、参考棋譜が多い |
これらの理由から、右玉は“相手に合わせた変幻自在の布陣”として、実戦向きの戦法と言えるでしょう。
右玉戦法を活用するシーンと戦術
右玉は特に以下のような場面で活躍します。自分の棋風や得意な展開と照らし合わせて活用してみましょう。
【右玉が効果的なシーン】
- 相手が角換わりや早繰り銀など、急戦気味な構えを見せた時
- 振り飛車党と当たった時の柔軟な対応型として
- 棒銀や早囲いに対して、受けつつ反撃する構えとして
- 玉を安定させつつ中央や右辺から反撃を狙う形にしたい時
特にカウンターを狙いたい棋風の方には相性がよく、囲いの完成を待たずに攻めに転じられる点は大きな利点です。
右玉の学習を継続するためのコツ
戦法は一度覚えても、すぐに忘れてしまったり、自分の指し手として定着しないこともあります。
右玉を「自分の武器」として身につけるために、以下の学習法をおすすめします。
【右玉上達のための5ステップ】
- 基本的な組み方を毎日1局確認する
- プロ棋譜を1日1局、右玉に注目して並べる
- 崩されやすい弱点や対策手順をメモする
- 将棋アプリで右玉を毎日実戦投入して慣れる
- 定期的に動画や書籍で知識をアップデートする
毎日の習慣が、あなたの「右玉脳」を育てていきます。
右玉は初心者にもおすすめの戦法
右玉は一見難しそうに見えますが、実は初心者にこそ向いている戦法です。
なぜなら、次のような理由があるからです。
【初心者に右玉をすすめる理由】
- 序盤のパターンが少ないので覚える量が少ない
- 囲いがシンプルで配置の自由度が高い
- 相手の作戦に合わせて柔軟に指せるため、勉強になる
- 自分で考えて組み立てる力がつく
序盤から定跡通りに進む戦法と違って、右玉は「考える楽しさ」があります。
だからこそ、楽しみながら上達したい初心者にはうってつけなのです。
将来的に右玉をどう活かしていくか
右玉を覚えたあと、その戦法をどう将棋ライフに活かすかも重要です。
【右玉戦法の今後の活用法】
- 勝率を上げるための武器として使う
→ 他の囲いと使い分けることで、相手の対策を困らせられる。 - 大会・ネット対局で持ち時間が短い場面に使う
→ 柔軟性があるので相手の出方次第で対応がしやすい。 - 右玉→右四間など、他戦法との複合運用にする
→ 組み替え自由な特性を活かして他戦法に発展させられる。
右玉は「一発屋」ではなく、長期的に使える引き出しになる戦法です。地力をつけたい方にこそ向いています。
右玉を学ぶ人へのメッセージ
右玉は華やかさはありませんが、勝つための現実的な選択肢です。
糸谷流のような独創的な右玉を目指すもよし、自分なりの工夫を凝らして“マイ右玉”をつくるもよし。
将棋の魅力は、自分の発想と工夫を指し手に込められることです。
右玉を通じて、その楽しさをぜひ味わってください。
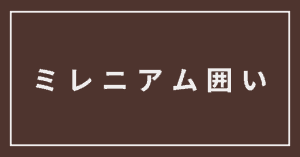
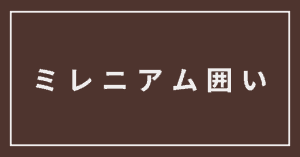


将棋の矢倉囲い完全ガイド|組み方・戦法・攻め方・崩し方まで徹底解説
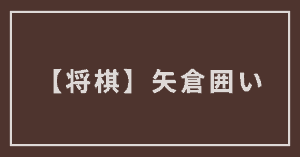
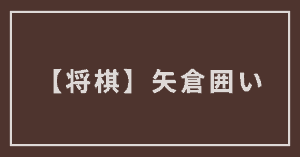
将棋の美濃囲いとは?種類・作り方・崩し方・銀冠との違いまで完全ガイド
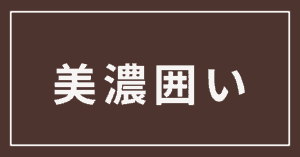
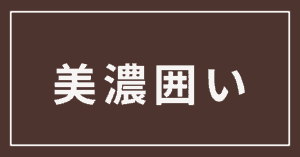
将棋のエルモ囲い完全ガイド|組み方・メリット・崩し方まで解説
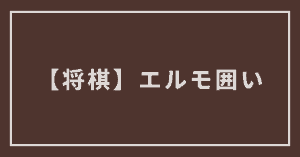
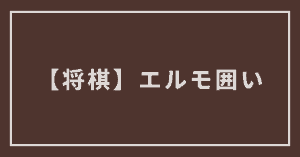
将棋の舟囲いとは?作り方・攻め方・他の囲いとの違いを徹底解説!